


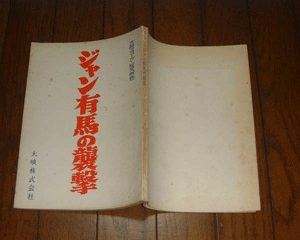
翌日、家康は始めて晴信に目通りを許した。傍らには頼姫が嬉し気に控えていた。老獪な家康は、晴信が兼ねて書面で、御朱印船免許の嘆願をしているのを知り乍ら、わざと素知らぬ態で、よも山話を持ち出したり、晴信の父の思い出話をはじめたり、容易に話の核心にふれようとしなかった。しかし、晴信はそうした家康の言葉尻をつかまえては、歯に衣きせぬ率直な言辞で、一々家康をへこまし、そのようなことより兼ねてお願いの御朱印船の件を・・・と云うと、家康はそのようなものは見たこともないと空とぼけた。然らば改めて御披見の程を・・・と用意の書状をつきつけるに及んで、流石の家康もとぼけ切れず、内心、天晴れの若者と舌を巻いた。晴信にすっかり好意を寄せる頼姫は、そうした家康の態度に、しびれを切らし、御朱印船の免許下げ渡しを、傍らからしきりと口添えした。 「折角の孫娘の頼み故、そちに免許をとらそうか」と云った。晴信の背後では寺沢広高や左兵衛らが、敵意に満ちた冷たい眼で、じっと彼を睨みつけていた。頼姫の願いで・・・と聞いた晴信は、即座に「恐れ乍らお断り致します」とキッパリと言い放った。家康も頼姫も、更に居並ぶ大名小名等しく、意外な晴信の言葉に息を呑んだ。
「不肖有馬晴信、御朱印船の免許を願うは私事にあらず、日本国の勢威を海外に示さんため。頼姫どののお口添えで頂く筋合のもでは御座いませぬ。一婦女子の言で左右されるごとき免許なら頂こうとは思いませぬ。南蛮の交易ならば、それがしの独力にて必ず切り開いてお目にかけまする」
余りの不遜な言葉に、幕閣の要人たちが、憤然色をなして晴信につめよった。だが老獪な家康はそれを制し、朱印船の免許の有無は、南蛮交易上、大きな利害得失がある筈、その悪条件克服して、見事交易をなし得るかと念を押し、さらば独力にて高砂国にゆきて、彼の地の伽羅を求めて参れ、事成功の暁は、改めて朱印状をそちに限って与えよう、但し事ならざる時の覚悟はあろうと云った。
「御念には及びませぬ。海外との交易はわが国発展のため、万難を排しても押しすすめねばならぬもの、只今の大御所様の言葉、後日の証として御墨付にて賜りましょう」と毅然として云ってのけた。
列座の大名小名、ことごとく晴信の烈々たる気魄と、その決意にうたれ、頼姫は心中この男こそ将来を托すに足る・・・と改めて惚れ惚れと晴信の顔をみつめた。
「天晴れの気構え・・・どうじゃ事成就の暁は、引出物としてこの頼姫を遣わそうか」と家康は云った。
「それがしすでに心に定めた妻が御座りまする」権勢に媚びず、何ものにも屈しない晴信の態度は、千代田の大広間を凛として圧していた。
こうして晴信は、高砂国へ伽羅を求める大役を帯びて日野江の城に帰って来た。彼の帰りを一日千秋の思いで待ち侘びるのは、彼の許婚、隣藩大友純忠の息女愛姫であった。 しかし彼女は晴信が、大御所から孫娘を娶わそうかと云われたことを聞き知り、乙女心を痛めた。天下を一手に掌握する大御所家康の命令は、絶対至上のものであったからである。許婚のこの杞憂を、晴信は一笑した。
「そなたを置いて予の妻は他にない、そなたへの愛が嘘いつわりでないことを神に誓うぞ」と、晴信は胸間の銀の十字架をかざして云った。“ジャン・有馬”という、クリスチャン・ネームをもつ晴信の、神への誓いを、愛姫もまた、涙の中で自らの十字架を抱きしめ、彼へのかわらぬ献身を誓うのであった。こうして晴信は、直ちに出帆の準備にとりかかった。
こうした時、最も頼みになる側近に、小畑三郎兵衛と云う若侍がいた。三郎兵衛は五年前晴信が、印度支那の占城(チャパン)から帰国の海上で、漂流していたのを助けてやった漁師の息子であった。生れ乍らに海の男として育った三郎兵衛は、航海の度毎に、機敏な働きをして、よく晴信の信頼と恩顧に応えた。
彼には有馬家持船の船長の娘で、おさきと呼ぶ恋人があった。それと知った晴信が、仲人をしてやろうと云った時、「殿様が奥方をお迎えになりますまでは・・・」と頑として聞かなかった。三郎兵衛をこの度の船長として赴かすことにきめた晴信は、この船が無事帰って来次第、自分も愛姫を迎え、三郎兵衛もおさきと一緒にしてやろうと心にきめた。