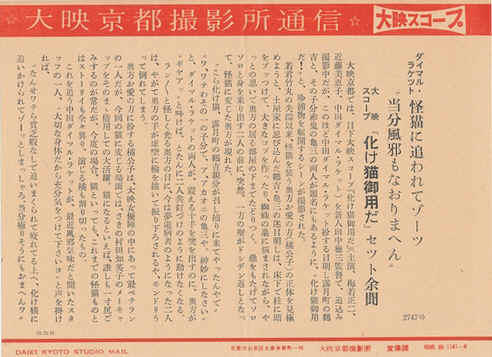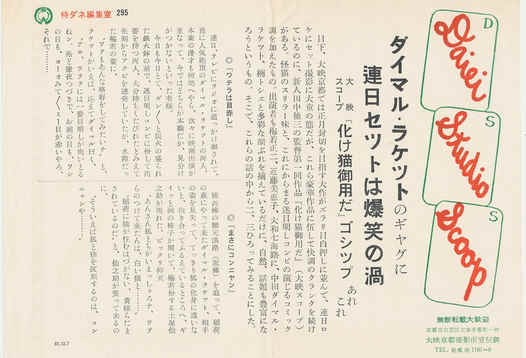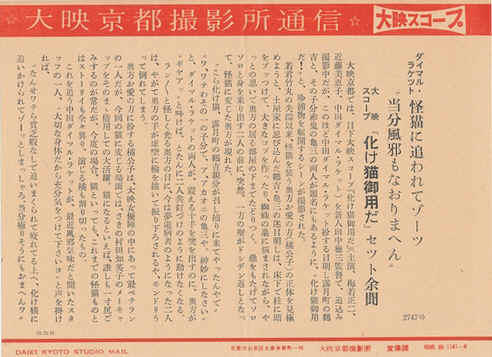

映画にほれて
聞き書き 田中徳三監督
|
喜劇タッチになった第一作『化け猫御用だ』の撮影は、二週間程度で完了しました。標準的な1時間半程度の作品のほぼ半分の日数です。準備期間も、撮影にかかった時間も本当に少ないものでした。監督としてやっていけるかどうか試されるテスト版で、答案を会社に提出したような気分でした。頼れるのは自分しかいない。そんなギリギリの思いで無我夢中で撮り終えました。
ひと区切りついてもなかなかほっとできません。編集などの作業をへて、スタッフだけの試写があり、そのあと、東京の大映本社で社長以下の重役連中が見ます。そこで「もうちょっと助監督で勉強させなあかんな」となるのか、「次も監督でいけそうや」となるのか、運命の分かれ道です。京都撮影所で試写が行なわれたあと、所長に呼ばれひどく怒られました。市川雷蔵をこっそり登場させたことが、すぐにばれたのです。 「大スターを何という使い方をしたのか」と責められました。「“トクさんのデビュー作だから”と雷ちゃんがご祝儀のつもりで出てくれた、断るわけにはいかない」。そう反論しました。結局うやむやのまま、それっきりおとがめはありませんでした。所長も示しをつけるために形式的に怒ってみただけで、雷ちゃんの気持は十分にわかってくれていました。 作品の出来に初めて手応えを感じたのは、スタッフの試写が終わってからです。身内だけに批評は辛らつなんです。遠慮などせず、悪いものは悪いと決めつけられます。それが割りと「おもろいやないか」とほめてくれたんです。漫才師の中田ダイマル・ラケットが登場する場面では笑いも起きました。本社の試写も好評でした。その場に私は立ち会っていません。後から所長に聞いた話ですが、作品を見た社長が「田中はどういう男か。いままでだれについていたのか」と尋ねたそうです。黒澤明や市川崑監督のもとで働いたといっても、社長は私の存在などまったく知りませんでした。助監督なんてそんなものなんです。 第一作を乗り切り、監督として次の階段をもう一歩上りました。でもその後何本撮っても、安心することはできませんでした。面白くない作品を撮ったら助監督に逆戻り。いつも不安を抱えていました。監督の仕事の宿命なのかもしれません。 |