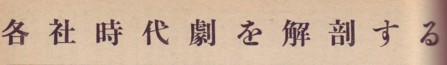
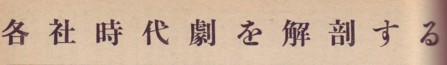
|
|
| 古いノレンの松竹、新しいジャンルを狙う東宝、画一的になりかかった大映、娯楽に徹した東映、大蔵色の強い新東宝
-各社カラーに今や転換期が来たのではないか- |
|
|
永田規格版の悲劇
ところで、再び筆を、ワンマン社長永田雅一にもどすが、こういう一代で成功した人のくせとして、えてして、我流のモラルをもつものである。大体成り上りの社長の応接室には、そういう標語が壁にかかっている。ぼくは永田氏には、親しく語る機会を一度ももたなかったので、直接にこの人の人生観をきいたわけではないが、『日蓮と蒙古大襲来』をみると、大ヘン頑固で、熱烈な愛国主義者であり、同時に、おなじように頑固で熱烈な日蓮宗の信者であるらしい。愛国主義者であり、日蓮宗の信者であっても、それは彼の自由であり、別にとがめることはない。
だが、そこに一種の警世的な要素が押しつけがましく顔を出していることはどうか。そこには、保守的な色彩が濃い。時代は、激しく動いている。その中で、特に若い世代にアピールしなければならぬ映画企業の統率者が、こういった硬化した、しかも強圧的な態度を見せることは疑問である。sこれはまた聞きだから、真偽のほどは保証しないが、何でも彼は、姦通を主題とした『藤十郎の恋』をとるとき、道徳的な解決を求めて、スタッフ連中を驚かせ、かつとまどいさせたときいているが、少なくとも、よき映画、よき芸術を生もうと思うのならば、もう少し柔軟な態度が必要なのではないか。
前に永田社長は、新平家物語の『義経と静』の思いもよらぬ不評をみて、「驚いた、驚いた」という世の笑を買った一文を発表したことがあるが、このときに、一般大衆との感覚的ズレを反省すべきだった。何も大衆に媚よというのではないが、世代の潮流に逆行するような態度は、孤高をめざすのならいざしらず、大衆とともに手をとってゆくべき映画製作者としては、決して賢明なこととはいえない。どうも大映時代劇には、この愚かしい欠点が非常に顕著である。
ここで惜しまれるのは、溝口健二の死去だ。内幕のことはよく知らないから、或いは見当ちがいであるかもしれないが、この人だけには、永田社長も敬意を払って、その自由をゆるしていたのではないかという気がする。とにかく彼だけは、大映時代劇のワクの中で、過去と現代とをみごとに結びつけていた。『山椒太夫』から、『近松物語』への彼の歩みは、多分、大映時代劇の黄金期を画するものであろう。
実力をもって、永田社長のワンマン的独裁に抵抗したこの人がなくなったあと、大映時代劇が、低迷を続けるのは当然である。
第一に、今や大映時代劇の監督には、企画版的作品をつくる監督だけで、これといって、シンのある人が見当たらない。前にいった、これただ無事を念ずるだけのサラリーマン的監督ばかりである。そのひとりひとりには、あって話をきくと、芸術的な野心を胸に燃やしている人もあるが、自由という空気のない真空鐘のなかでは、この熱情も発火しないらしい。

伊藤大輔作品『弁天小僧』
さらに、俳優を眺めると、これも今やそう大して興味が持てないのが、事実である。なかで、市川雷蔵だけが、自由を求めてあがいているようだが、はたして彼も、この規格版的統制のワクを破れるかどうか、心配である。彼が、去年方々で演技賞をえたのが、現代劇『炎上』であったことは皮肉な現象である。
長谷川一夫は、年令の限界に直面して、いま苦悶している。この人の苦しみを、そのまま、映画のイメージに直結させるのが、彼の生きる道だと思うが、そういう大胆な試みは恐らく許されないだろう。
女優では、山本富士子の一枚看板だが、この人の重たい美貌をはたして時代劇のジャンルのなかで生かし切れるかどうか、それも疑問。
要するに、大映映画は、いま危険な曲り角に立っているといっても、いいすぎではない。この危機を切りぬけるには、企画の柔軟性と、俳優、監督の養成の一途しかないが、結局ワンマン社長が、自ら自分の欠点に眼をあけて、もっとハツラツとした働きの場を与えることが先決問題である。