
江戸へ百七十里

1962年7月29日(日)公開/1時間23分大映京都/白黒シネマスコープ
併映:「宝石泥棒」(井上梅次/山本富士子・川口浩)
| 企画 | 財前定生 |
| 監督 | 森一生 |
| 原作 | 山手樹一郎 |
| 脚本 | 笠原良三 |
| 撮影 | 今井ひろし |
| 美術 | 西岡善信 |
| 照明 | 岡本健一 |
| 録音 | 林土太郎 |
| 音楽 | 渡辺浦人 |
| 助監督 | 井上昭 |
| スチール | 三浦康寛 |
| 出演 | 嵯峨三智子(松平福姫)、中村鴈治郎(塚越助左衛門)、真城千都世(楓)、島田竜三(宍戸丈之進)、柳永二郎(土井信濃守)、五月みどり(桔梗)、千葉敏郎(関屋十三郎)、細谷新吾(中橋茂太郎)、千石泰三(小堀孫作)、香川良介(大坪兵太夫)、荒木忍(中橋茂右衛門)、市川謹也(手塚勘解由) |
| 惹句 | 『ニセ若君とジャジャ馬姫が、喧嘩しながら恋をする!歌も流れる剣も飛ぶ!』『明朗若様とジャジャ馬姫が、陰謀破りの痛快道中!敵も味方も大混乱!』『ジャジャ馬姫は一目惚れ!敵をあざむく濡れ髪変化!暗殺団に狙われてどの手で斬るか剣の冴え!』『アタマに来るほど痛快!雷蔵若君濡れ髪姿で大暴れ!』 |


■ 解 説 ■
小森藩世嗣をめぐり大騒動、折りしも瓜二つのニセ若殿は松平家のジャジャ馬姫と東海道はお江戸へ。歌あり恋あり剣ありの痛快時代劇。
この映画『江戸へ百七十里』は、当代最高の人気作家山手樹一郎が、一年有余に亘って「週刊読売」に連載、大好評を博した同名小説の映画化で、原作は原作者みずからも近来にない作と自負するほどの力作である。
物語は、津山藩主小森高久の落し胤として生れ、江戸の町道場の主人に育てられた長谷部平馬(市川雷蔵)は、固苦しい武家の生活を嫌って完全に市井の人間にかえろうとするが、時たまたま小森家は世嗣をめぐって平馬の双児の兄、亀之助(市川雷蔵−二役)は毒薬を盛られて倒れたとあって、平馬は仕方なく亀之助の身代りとして立ち、お見合相手の松平家のジャジャ馬娘、福姫(嵯峨三智子)と相協力して悪を討つといった風のもので、これに亀之助の腰元桔梗(五月みどり)が絡んで、江戸へ上る百七十里は、歌が、恋が、剣がいっぱいといった文句なしの痛快明朗時代劇です。
主演の市川雷蔵は、『破戒』『中山七里』『斬る』と割合暗い内容の作品が続いたあとの、水もしたたる若様スタイルに大喜び、しかも四年ぶりに仲のよい嵯峨三智子とコンビを組むとあって頗るごきげん。この二人の初顔合せは、昭和二十九年末の“美男剣法”だが、以来、一連のコミックな時代劇を九本、五年に亘って発表、その後五社協定等の理由で大好評を博したこのコンビも惜しまれながら解消、こんど嵯峨が松竹の専属を離れたところでやっと復活をみたものです。亀之助の腰元には、最近レコードに、テレビに爆発的な人気を誇るコロムビアのトップスタア五月みどりが扮し、篇中主題歌「いゝから いゝから」を歌います。

■ 物 語 ■
ある日のこと、津山藩十万石の留守居を預かる国許家老、中橋茂右ヱ門を訪れた一人の浪人風の若者があった。男は、藩主小森佐渡守高久の落胤、長谷部兵馬(市川雷蔵)と名乗るや、血筋のあかしと称する銘刀“藤四郎兼光”を百両で引き取って欲しいと申し出た。この落胤の突然の出現に、茂右ヱ門は周章狼狽。というのは、小森家は、正嫡亀之助(市川雷蔵二役)を推す茂右ヱ門一派と、妾腹の千代五郎を後嗣にという次席家老手塚勘解由を支持する一派とが四つに組んでお家騒動にてんやわんやであったから、この上更に、平馬に落胤などと名乗り出られては大いに困るのだった。
とまれ、平馬は、小森家との絶縁を条件に、手にした大金を懐に気儘な独り旅に出るが、途中、ヒョンなことから姫路の別荘に遊ぶ松平福姫(嵯峨三智子)と知り合い、忽ち意気投合、姫の口から明日半強制的にお見合いさせられると聞いて、兵馬は若者らしく軽い義憤を覚える。−が、その相手が、意外にも小森家の嫡男亀之助と知って、平馬はその奇妙な縁に独り微苦笑した。
折りも折り、その夜、平馬は、屈強な武士を共にした茂右ヱ門の倅、中橋茂太郎(細谷新吾)の訪問を受け、双児とは云え、瓜二つの嫡男亀之助の替え玉として、明日のお見合いを無事済ませて欲しいと懇願されるのだった。このお見合は、小森家の安泰をひたすら願う茂右ヱ門が、最後に選んだ手段だったが、当の亀之助が何ものかに毒薬を盛られ、翌日のお見合までには到底回復しないときいては、平馬は迷惑を承知でこの大役を引き受けざるを得なかった。
さて、当日。さんざん駄々をこねた挙句、最低のごキゲンで見合の席に臨んだ福姫は、相手が過日の浪人風の武士と分るや、用人の塚越助左ヱ門(中村鴈治郎)や、腰元たちの訝かしげな表情を尻目に大はしゃぎ。この姫の様子を見た茂右ヱ門は、してやったりとばかり、このまま江戸表に居る主君へ報告かたがた、ご公儀に正式の認可を得るため江戸へと旅立たせた。
亀之助、福姫の一行が江戸へ発ったと聞いて不審を抱いた手塚勘解由は、これが茂右ヱ門の打った芝居と知るや、直ちに武芸指南役関屋十三郎(千葉敏郎)らに一行を追わせた。美しい松並木を背景に、姫の駕籠を守って兵馬の剣は冴えに冴える−。が、平馬は、これらの刺客の、葵の御紋も目に入らぬ無法ぶりに、姫とこれ以上共に旅をつづけることは危険と悟るが、姫の方は婚約解消を振りかざして、二人きりでしのび旅に出るよう逆に掻口説き、夜半密かに本陣を出奔する。
亀之助(実は平馬)、福姫の失踪に狼狽した助左ヱ紋らは、二人の行方を探索する一方、空駕籠の行列を仕立て、追手の目を眩まそうとした。それとは知らずにこれを見えかくれに追う一人の怪しい鳥追い女−。行列を待ち受けていた関屋は、それが亀之助の元腰元で、亀之助と恋仲にあった桔梗(五月みどり)と知るや、一計を案じて味方になるよう奨める。まさか、ダマされているとは知らぬ桔梗は、箱根の関所を目の前に三島の宿で最後の別れを惜しむ平馬を見つけるや、てっきり亀之助と思い込み、女心の嫉妬心から福姫を関屋の一味に手渡したあと、平馬の部屋へ勇を鼓して乗り込む−。
涙ながらに男の心変りを責める桔梗に、いまは、やや持て余し気味の平馬は、仕方なく自分の素性を打ちあけるが、漸く事の重大さに驚いた桔梗は、慌てて平馬と一緒に福姫の許へかけつける。激闘数合−。平馬は居合わせた剣の達人、宍戸丈之進(島田竜三)の救けを借りて一味を悉く薙ぎ倒すが、最後に二人は静かに向かい合う。一声高く咆吼して斬り込む丈之進。しかし、平馬の刃が僅かに早かった−。
駈け寄る平馬の腕の中に、今は全てを越えてとび込んでゆく福姫…。ところが、そこへ手塚勘解由の報せを受けた江戸家老大坪兵太夫の訴えで、三島代官長島権之助が助左ヱ門を従えて現らわれ、亀之助の名を騙り福姫をかどわかした罪で平馬を捕える。だが平馬の取調べに当った土井信濃守(柳永次郎)は、福姫とも直々話合った結果、全ては私服を肥やさんとする大坪兵太夫らの陰謀と分り、小森家の正嫡には亀之助を推し、大坪らに謹慎を命ずる−。
数日後−。全快した亀之助の行列がいかめしく通りすぎる脇を、面を、伏せて秘かに見送る兵馬と福姫の二人−。だが福姫の顔は、不行跡のかどで、松平家を除籍、姫路の別荘に謹慎を命ぜられたにしては、晴れゞと明るかった。

「いいから いいから」
作詞:星野哲郎 作曲:遠藤実 編曲:山路進一 唄:五月みどり
一、いゝからいゝから 止めないで
いゝからいゝから 放っといて
私のえらんだ 恋の道
ひとりで歩いて 行きたいの
それが私の しあわせよ
いゝからいゝから 止めないで
二、いゝから何も 云わないで
いゝから黙って みておいて
子供じゃないから わかってる
誰にも涙は みせないわ
そっと一人で 泣きますわ
いゝから何も 云わないで
三、いゝから勝手に 行かせて
いゝからツンツンしないでよ
山路 坂路 茨道
はじめて恋した あの日から
みんなわかって いたことよ
いゝからいゝから 行かせてよ

|
| 随談第214回 わが時代劇映画50選(その12) 『江戸へ百七十里』 昭和37年大映、監督・森一生 |
| 附・ライゾロジイ(Raizology)入門 |
タイムリー性を求められない記事はつい後回しになるため中断が長くなってしまったが、時代劇50選をそろそろ再開しよう。初期の雷蔵物のこれも一典型。この前挙げた『怪盗と判官』もそうだが、殿様とやくざ者、あるいは浪人者を早替りよろしく演じて、貴公子ぶりと自由人ぶりとの両面を見せようという、この種の趣向は昔から時代劇の一定型だが、とりわけ初期の雷蔵ものにそれが多いというのは、ライゾロジストの方々にとっては、雷蔵研究(Raizology)の欠かせぬテーマだろう。勝新では、どうしたってこうはいかない。
この手のものの、最も華麗で、配役も手揃いで、演出も堂に入っているという意味からは、『江戸へ百七十里』を最も典型にして最も代表的な作品として挙げるのが常識だろう。雷蔵狂四郎・勝新座頭市を中心とする後期大映時代劇が成立するのが、長谷川一夫御大の退場と東映時代劇の撤退と入れ替わる昭和38年前後をメルクマールと考えるとすれば、奇しくもその前年制作の『江戸へ百七十里』は、いわば前期大映時代劇における定番雷蔵映画の集大成ともいえる。
原作である山手樹一郎の明朗青春時代小説というのは、昭和30年代に隆盛だった貸し本屋文化を象徴する存在で、抜群の愛読者を有していた。有名な『桃太郎侍』をはじめ、およそどれを読んでも同じようなものだが、山手樹一郎ものでは錦之助にも『青雲の鬼』という佳作がある。こちらは題名通り、青雲の志を抱いて江戸に上る青年がその途次巻き込まれる事件と、それにまつわる人間関係から人生如何に生きるべきかを学んでゆくという、いかにも若き日の錦之助にぴったりのイニシエーション・ドラマである。
『江戸へ百七十里』は、瓜二つの兄弟の片方が世継ぎの若殿、片方が剣の達人の浪人者、そこに『ローマの休日』もどきのおしのびの姫君がからんでの道中物という、典型に典型を組み合わせたようなストーリイで、雷蔵が兄の若殿と弟の浪人者の二役、姫君が瑳峨三智子。いろいろな女優を相手役にしたが、結局のところ、前期における雷蔵には瑳峨三智子が他を圧してうつりがいい。後期における藤村志保と双璧ということになるが、姫から娘から堅気の女房から武家女房から遊女女郎から女賊から、役柄の幅の広さ、どれになってもツボにはまる多彩さと柔軟性、演技そのものの巧さ、素人臭さのなさ、この時点での時代劇全盛を支えた女優の中で瑳峨三智子の存在というものは抜群のものがあった。
世の時代劇論に女優を真っ当に論じたものをほとんど見かけないが、そうしたマッチョ趣味の固定観念は廃されねばならない。また瑳峨三智子というとすぐに山田五十鈴を持ち出すのも、「何とかの壁」の虜になって思考停止した論者の条件反射みたいなもので、お色気女優という固定観念の牢獄に彼女を押し込める結果となっている。瑳峨三智子に限らず、いずれ、定番時代劇の女優論をきちんとしなければなるまい。
『江戸へ百七十里』でもうひとつ、言い忘れてはならないのは、あの二世鴈治郎が姫君守護の老爺役で出ていることだ。これも、映画俳優中村鴈治郎の一風景として忘れがたい。(上村以和於の随談より)
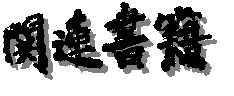

週刊読売連載山手樹一郎原作の映画化。春陽文庫山手樹一郎長編時代小説全集=55「江戸へ百七十里」で読める。−小森家当主の血筋をひきながらも、一生を浪人として生きようと決めた長谷部平馬だったが・・・。縁を切ったはずの生家は、お世継ぎ問題で揺れていて平馬も巻き込まれてしまう。そして狙われた若殿の替え玉となり作州津山へ。−
山手樹一郎(やまて きいちろう)1899年2月11日 - 1978年3月16日)栃木県生まれ。本名井口長次。
(旧制)明治中学校卒業。長男は同じく小説家の井口朝生。博文館に入社し、編集者を経て“少年少女譚海”編集長。1932年頃より兼業作家となり、1939年より専業作家。前後して長谷川伸の門下。翌年より新聞連載した「桃太郎侍」で人気を得る。
一貫して明朗、壮快な作風で、時代小説作家として支持される。唯一の歴史小説である「崋山と長英」で第4回野間文芸賞を受賞。1977年には、勲三等瑞宝章を受章。1978年3月16日、肺癌のため東京都内の病院で死去。享年79。
雑誌編集者との兼業作家として活動を始める。編集者としては山本周五郎などの担当をする傍ら、自身が編集に携わる雑誌を中心に作品を発表した。その際、編集者の「井口長次」では原稿料が支払われないため、筆名「山手樹一郎」を名乗った。このため、当初は素性不明の作家であり、“少年少女譚海”編集長時代に、ライバル誌であった“講談倶楽部”の編集長から執筆依頼の相談が来てしまい、たいへん困ったがさすがに断ったという逸話がある(専業作家となった後には“講談倶楽部”でも作品を発表している)。
大衆文芸に求められるものとして読み手側の爽快感を重視した作りで、大半の物語が明朗爽快・勧善懲悪・人情話・ハッピーエンドという要素でまとめられている。このため時に偉大なるワンパターン作家などと言われる事もある。(Wikipediaより)



![]()