|
四月の中座
道頓堀のゲテ味
昨年末、三回にわたって仁左衛門一座で開けた中座歌舞伎に、こんどは鴈治郎一座を持って来た。東京に比して、いつも継子扱いの関西歌舞伎が、本拠たるべき歌舞伎座を、芸妓のやる“女かぶき”に明け渡して、両頭目の双寿を休ませ、ここへ逼迫した、と見られぬこともない。
けれども、道頓堀五つの櫓の筆頭である中の芝居こそは、関西歌舞伎本来の居城だったのだから、その故里に帰って来たわけでもある。ここには幾世紀かの伝統と共に、手頃な大きさの舞台が待っている。歌舞伎座の野放図もない舞台に慣らされて、芸の寸法がゆるんで来た役者たちも、この手頃な大きさの中舞台に据えられれば、自然、締まりが出来て、よい芝居を見せられるはずである。
そうした期待が外されたわけではなかったが、舞台が小さくなるのに反比例して芸が大きくなった、とは決していえないし、むしろ小芝居めく格下げの感が深いのは、仁左衛門の場合と同様である。ここは戦後は松竹新喜劇の常打小屋となり、それでなければ安物しかかからないようになっている印象が、そのまま残っているからでもあるが、つまりはパチンコ屋とストリップ小屋が軒をならべるようになった、道頓堀の下落を反映しているわけで、「東西合同大歌舞伎」と構えても、所詮は小芝居たるに過ぎぬのである。
ところが、仁左衛門の場合のように、持て余した役者を集めて一座としたのと違って、小さいながらも座組みを整えた上、花見月ではたった一つの芝居として松竹も力を入れざるを得ないので、まず連日いい入りを続けているようだ。鴈治郎の仕合わせでもあり、これを思うと仁左衛門が可哀そうでもある。
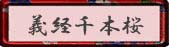
 ←クリック!拡大版へ ←クリック!拡大版へ
「義経千本桜」すしやは今の関西歌舞伎として標準的な舞台であろう。何故先月の延若追善に出せなかったのか、惜しい話である。鴈治郎の権太は延若ほどなだらかな愛敬がないにしても、にがみ走った顔もあまり泥くさからず粋にならず、ダミ声も苦にならず、眼玉の動きもよくきくようになった。母親への甘えぶりの形、鮨桶をかかえての引込みの足、後の出で妻子を想う秘かな涙、手負いになってからの真情吐露もいつもの通りよかった。例の「貧乏ゆるぎもー」を梶原が花道で振り向いた時にいうのも効果があったが、はじめに格子を入るとき、惟盛の絵図を展げて見るのは今更不要ではないか。扇雀のお里と延二郎の惟盛は美しくそれぞれに好演、訥子の梶原が意外に大きく見えたのも収穫だった。 |

