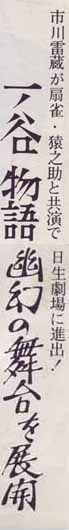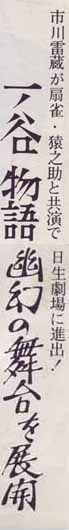| 或る日、敦盛が青い人魂であることを見た小之介は、きつく萩明を諫めるのだが、それを知った敦盛は二人の仲をさく言葉を封じようと小之介に切りつけた。小之介の一命は、他言せぬとの誓いで助けられた。敦盛との誓いに身をまかした小之介は身の怖ろしさに仏にすがりながらも、敦盛の正体を誰にも明かす訳にはいかなかった。彼を慕う桔梗にも-。
幻の館では、公達上臈の居並ぶ宴で、萩明と敦盛は舞っていた。その時、能登守教経(雷蔵)が現われた。乱れた髪、鎧に立った矢、血も乾かぬ傷の跡、壇の浦の戦の姿その儘である。教経のいうには、現の世の人に懸想する四郎敦盛のために、一門は浄界に浮かばれぬのだ。しかも萩明は、そなたの首をはねた熊谷直実の孫女ではないか・・・。
一部始終を垣間みた桔梗の知らせで、法主蓮明は、ものの怪から護ろうと、萩明と小之介の身体に経文を書きつけた。
その夜-、敦盛は最後の語らいのため萩明に会いにきたが、萩明の言葉は経文に封じられて敦盛には聞えない。取りすがろうとする萩明が転ぶはずみに、両手を軒下に溜った雨水の中につくと、両手の経文が水ににじみ、溶けて流れた。
呼びかけることのできない萩明は思いを琴に託して弾きはじめる。突然、弾き出された琴の音に、敦盛は立上がった。
「何故に二人のこの恋が、あまねき世界の掟に容れられぬと言うのだ。一門の成仏のために、わが身一人がかく苦しまねばならぬのだ・・・。」
四郎は、近づいて幽かに踊る萩明の手をしっかり捉えた。しかし萩明の声は聞えず、経文の力の失せた両手だけが萩明のすべてだ。
「そなたは私だけのもの。その証に、そして別れの形見にこの指をもらおう」
四郎は刀をかざして、萩明の指を切った。
「手の指ならずこの私も。さればあなたの国へ参れます」
萩明は叫び、そして生命を終えた。黄泉の国に落ち行く萩明。しかし、その時四郎敦盛は一門の裁きをうけて成敗され、黄泉の国より更に暗い闇の国に吸いこまれていった。
「お聞きなさいませ。黄泉の国の琴の音、更に遠い国からの笛の音、互いに離れて呼び合う二人の声でございます」
こう語る白髪の老人には小之介の面影が残っていた。落ちかけた月の光に松風が騒ぎ、老人は庭の奥へと消えていった。
|