芝居の面白さは全く淡島の芸妓ぽん太の好演にかかっている。特に、妾になってからすましこんで本宅伺いに来る前後で、母親から二代続いた芸妓の若さ、旧い表現でいえばおきゃんな明るさ、新町のお茶屋で大勢の芸妓と雑魚寝している喜久治が隣のぽん太を抱き、別室へしけこむときの風情は、水谷の巧さとはまた違った巧さだ。彼女のほかに霧立のぼるの仲居お福、桜緋紗子の舞妓小りん、渡辺千世ののキャバレの女比沙子が囲われていて、それぞれに喜久治の放蕩史を彩っているのだろうが、この脚色で添え物に過ぎないのは、舞台的制約のためだろう。全十場のうち、第四幕第一場を割愛し、最後は空襲で焼け残った商い蔵へ全人物を集めるのは、いかにも新派劇的な大詰である。それまでに二十五分の食事時間がはさまるが、暗転の間を入れてほぼ二時間、どの場も十分以下の短さで、或は暗転中の時間と三対二くらいかも知れない。
脚色者も心得て、テレビ劇的に息の長くなるのをさけたのであろうが、それにしても、ここのスライディング・ステージ・システムののろさは困ったものだ。主な場面である河内屋の店の間、中の間、隠居部屋(?)、旦那部屋を上手から下手へ装置でつないで奥深さを表わしているのだが、それを移動させるだけにも暗転せねばならぬのでは、劇の流れを阻害し、多幕物に向かぬことを痛感させた。
「祭ばやし」は神田祭を背景にした雷蔵の鳶頭清吉と淡島の芸妓お美代の濡れ模様というお景物。寿海も鳶頭でつきあい、新派女優連の芸妓・手古舞・町娘と、関西歌舞伎の若い者がからむ。風姿はなかなかよいが、踊りとなると、雷蔵の腰はあやしい。
「浮名の渡り鳥」は寿海・雷蔵の関係を旧作の股旅物にはめこんだ川口松太郎の書き卸しで、役者とヤクザとを結びつけ、劇中劇として寿海・雷蔵に歌舞伎の「鈴ケ森」をやらせる。これがこんどの最大の見ものであるし、雷蔵の実力試験みたいな興味もあるのだが、もとより歌舞伎の方は断念しているとはいえ、あの年齢で五年以上も舞台を離れていれば、雷蔵の権八は、いかにもニンにありながら、やはり落第といわねばならぬ。雲助共を斬り散して長兵衛に呼びとめられ、刃を改める時の腰が頼りないのだ。腰の不安定さは、大勢のヤクザとの乱闘でも花道の引込みでも蔽うことはできなかった。それにヤクザは新派の連中で、新派は近来こうしたマゲ物をやらないので、立廻りがいかにも心許ない。それにしては、まだよくやったといえるくらいだ。
これにまじって寿海の長兵衛が出るのだから、全くはきだめに鶴のような感じだ。寿海としては初役同然らしいが、貫録といい、台詞といい、仕料といい、やはり無形文化的演技である。あのような低く太い発声も、これまでの寿海になかった豪放さで、このような舞台でも、寿海は気を抜いているのではなかった。台詞といえば、雷蔵の蝶次としての発声と、劇中劇で権八としての発声を変えるためにしても、二枚目の声の基準がわからなかったらしい。
それにしても、雷蔵の実演に接して、もっとファンが湧くのではないかと思っていたのに、他の人気スターのような興奮は客席から遂に起らなかった。そこに雷蔵の本質があるのではなかろうか。やはり彼を映画にとられたままにしておくのは惜しいと思う。
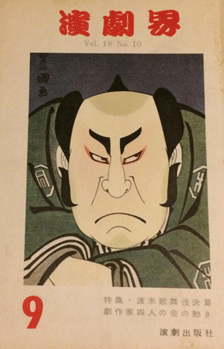 (演劇界60年8月号より) (演劇界60年8月号より)

|