


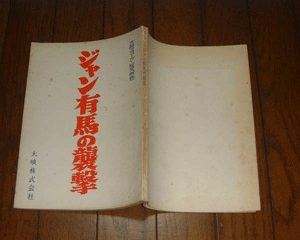
| 大映には企画審議会の制度があって、プロットの形で提出された企画が検討される。ここに掲載した『ジャン・有馬の襲撃』のプロットはその審議会に提出され「一切、史実には拘泥せず、お盆作品として、娯楽映画に徹すること」(原文のまま)という条件つきで製作の決定を見ている。
慶長十四年の長崎港外でのポルトガル船焼討ち事件は史実として残っている最初のもので、その史実をはずさないでプロットは書かれている。プロットのように勇壮活発なクライマックスシーンも、実際には、いろんな制約から実現不可能な面が多く、シナリオに見られるように変っている。それに、ポルトガルという実存した国名も、国際問題を引き起こさぬよう、イベリア王国と架空の国にかえられ、言葉も万国共通語であるエスペラント語が使用される。 |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 主題: 正義の勝利
製作意図: 慶長十四年ポルトガル船襲撃は、日本歴史上、最初の外国船焼打ちであります。この史実に題材し、更に、若き大名の忍苦と、華々しき活躍を配し、話題の時代劇大作として製作したいと思います。はる |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
人物:
|
梗概:
慶長十二年の春。
肥前日野江四万石の若き藩主有馬晴信は、大御所徳川家康に召されて江戸へ向った。弱冠二十三才の晴信であったが、その識見、その英邁ぶりは、九州諸藩の大名中、群を抜いて秀で、つとに目を南方にひろげ、南蛮諸国との交易も行っており、その将来は、まことに刮目すべきものがあった。
その晴信を、江戸へ呼んだ家康の真意は、彼の実体を自らの目で確め、若し自分の天下制覇の野望の邪魔になる存在ならば、何らかの理由をつけて有馬藩を取潰し、禍根を双葉のうちに刈り取ってしまおう、また利用価値があらば、制覇達成の道具に使おうと云う、まことに以って老獪至極な目的にあった。
また晴信の方は、家康からの召出しを幸いに、兼ねてから再三書面で懇請していた語朱印船の免許を、是非共貰い受けようと思っていた。日本国の勢威を広く海外に誇示し、世界の大勢に遅れぬためにも、南蛮交易を今以上に進展させる必要を痛感していた彼であった。
この晴信の出府を夫々異なった立場で待ちうける男女があった。男は同じ肥前唐津十二万石の城主寺沢広高で、晴信の勢威を嫉み、あわよくば彼を失脚させ、南蛮交易をも自分の一手に乗取ろうと企てていた。しかも、利害を同じくする長崎奉行・長谷川左兵衛と相語らい、家康の側近を味方に引入れて赤恥をかかし、有馬藩取潰しにまで持ってゆこうと画策していた。
好意と好奇心で待ち侘びている女は、人もあろうに大御所家康の孫娘で、家康が寵愛おくあたわざる頼姫であった。彼女は九州の大名中、その人ありと噂される有馬晴信と云うまだ見ぬ若大名に、異常なまでの関心を寄せていたのである。
こうした陰謀の魔手と、可憐な頼姫の待つ千代田城へ、晴信はのりこんでいった。
陰謀の第一弾は、彼が千代田城へ伺候した第一日に放たれた。寺沢や左兵衛から、多額の賄賂で買収されている側近は、言を左右にして彼を大御所に会わせぬのみか、これが従来の慣例だと、彼に千代田城の各控えの間全部に挨拶に歩けと云った。九州の田舎大名と侮っている悪意に満ちた言辞であった。しかし彼は、決して怒りを面に現わすことなく、静かに各部屋へ挨拶に廻った。「九州の田舎大名はまるで木偶のようだ」とか「大名の本分を忘れ、異国との交易に熱中するとは町人同然」とか。聞くに堪えぬ罵声が飛んだ。しかし、彼は些かも動ずる色はなかった。こうして彼の千代田城通いがはじまって五日たった。 有馬晴信出府の報は、家康の耳にもすでに入っていたが、老獪な彼は素知らぬ振りをして、自ら会おうとは云い出さぬのみか、側近にいやがらせをされている彼を、ある時は隣室で、またある時は庭前から、じっと観察していた。彼の出府を心待ちにしていた孫娘の頼姫は、あまりの彼の不甲斐なさに、落胆した。しかし頼姫が、そして彼にいやがらせをしていた側近たちがアッと目を見張る日が来た。
その日、書院に引出された晴信は、寺沢広高らから、風流の嗜みを見せて貰おうと云われた。晴信は一旦は固辞した。しかし執拗な彼らの言に、では真似事だけ・・・と立上った。金屏風の後では、頼姫を従えた家康が、身をひそめて、面白気に成行を窺っていた。やがて舞出すそのさす手、ひく手の鮮やかさに、一座の者は唖然として息を呑んだ。
完全にしてやられた彼らは、さらば・・・と傍らの書院番士六名を顧りみた。舞いが頂点に達し乱調子となった時、それに合せるように、書院番士が襷がけに袴の股立ちをとり、木刀をもって打ってかかった。晴信の武勇の程を試そうとの魂胆である。しかし晴信の舞の手は一糸乱れず、鮮やかに次々とかわし、襖のかげからくり出される真槍も間髪にして避け、その千段巻を掴んでキッと身構え、手にした白扇を、家康と頼姫のひそむ屏風に向ってハッシと投げるや、何事もなかったかのように静かに退出した。
屏風のかげの頼姫は、只うっとりと、その颯爽さに見惚れ、家康は苦笑いして首を縮めた。