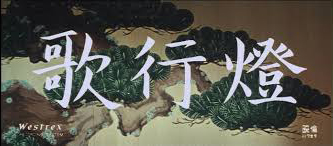
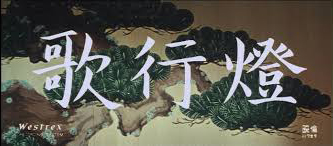

1960年5月18日(水)公開/1時間54分大映東京/カラーシネマスコープ
併映:「すれすれ」(瑞穂春海/川口浩・弓恵子)
| 製作 | 永田雅一 |
| 企画 | 中代富士男 |
| 監督 | 衣笠貞之助 |
| 原作 | 泉鏡花 |
| 脚本 | 衣笠貞之助・相良準 |
| 撮影 | 渡辺公夫 |
| 美術 | 下河原知雄 |
| 録音 | 橋本国雄 |
| 照明 | 泉正蔵 |
| 音楽 | 斎藤一郎 |
| 助監督 | 遠藤俊雄 |
| スチール | 宮崎忠男 |
| 出演 | 山本富士子(お袖)、倉田マユミ(おこま)、角梨枝子(おこい)、柳永二郎(恩地源三郎)、信欣三(辺見雪叟)、小沢栄太郎(今村屋彦七)、賀原夏子(お幸)、中条静夫(笹野)、荒木忍(宗山)、佐野浅夫(本田)、浦辺粂子(お秀) |
| 惹句 | 『島田の元結ふっつと切れ、肩に崩れる緑の黒髪 -鏡花文学の極致を描く悲恋の名作! 』『哀切にして艶麗!鏡花文学の最高傑作を描く衣笠、雷蔵、山本の最高トリオ!』 |
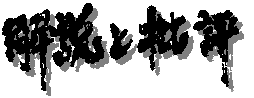
明治三十年代の伊勢。観世流家元の嫡子、喜多八は謡曲指南宗山を侮辱して自殺に追いやり破門されるが、宗山の娘お袖といっしか恋に落ちる。
[ 解説 ]

大映の“ゴールデン・コンビ” − 市川雷蔵と山本富士子が競演する明治情緒豊かな文芸作品。原作はいまさら云々するまでもなく泉鏡花。メガホンを握るのはこれまでも「湯島の白梅」「白鷺」と鏡花ものを手がけて名作を放って来た衣笠貞之助監督。このシナリオは本誌(キネマ旬報)の別冊“名作シナリオ集”に収録してあるのでストーリーもご存じの方が多いかと思うが、能の家元の嫡子・雷蔵と、盲目の謡曲師の娘・山本とが、運命の意図にあやつられながらも、その純愛をつらぬくというものである。( キネマ旬報より )

[ 略筋 ]
時は明治三十年代、所は伊勢の山田に東京から観世流家元恩地源三郎の嫡子喜多八を迎えて家元連中の奉納能が華やかに行われた。盲目の謡曲指南宗山は昔は娘のお袖と二人で町を歩いた按摩だったが、今は妾を二人もつ町一番の師匠だった。恩地親子の権勢を面白からず思う宗山を、旅姿に扮した喜多八が訪ね、田舎天狗の鼻をへし折って立ち去った。自分の芸に自信を失った宗山は古井戸に身を投げて果てた。源三郎は喜多八を謡曲界から破門して宗山に詫びた。焼香に来た喜多八は、美しいお袖を一目で愛したが、その日より諸国を門付して歩く身となった。
芸妓に身をおとしたお袖は、父を思うと一切芸事には身が入らなかった。芸の出来ない芸者は惨めだった。桑名の島屋に抱えられた或る夜、門付して地廻りに叩きつけられる喜多八に会った。安宿で介抱するお袖は父の仇も忘れて喜多八を愛した。お袖が仕舞の稽古を頼むと、以来父より謡を禁じられた喜多八は喜んで引受けた。早暁の裏山で二人のきびしい稽古は続いた。そして、お袖の舞う“玉の段”が仕上る時、それは二人の新しい生活の始る日だった。
お袖に睦屋の旦那の身請け話が起った。地廻りと喧嘩して留置された喜多八は、約束の朝、現われなかった。絶望したお袖は覚悟の殺鼠剤を帯にはさむと睦屋の座敷に出向いた。睦屋は急用で出かけた後だった。お袖が別の座敷に出たのは、能に関係ある客と聞いたからだった。客は恩地源三郎と小鼓の師匠辺見雪叟の二人だった。喜多八の父と知らず、お袖が“玉の段”を舞った時、その見事さに源三郎は地の謡を、雪叟は鼓をつとめた。鼓の音に魅入られたように、喜多八の姿が近づいた。かたくだき合ったお袖と喜多八の体に傍の白梅が散った。( キネマ旬報より )

明治は遠くなった。単なる年代の数字が示す以上に、観念的に遠くなった。昨今の加速度的な世相の移り変りは、時代のパースペクティブをおそろしいほど拡げて行く。明治的ロマンティシズムの精神ともいうべき、この泉鏡花原作のメロドラマも、怖ろしいほど拡大された時代のパースペクティブの前には、もはや手のつけようがなくなった形だ。
テンポが遅い。 ・・・もっともな非難である。だが、これをもういくらかでも早いテンポにしたら、どんなことになるだろうか。それでなくても御都合主義のの運びが、“偶然”という名のまわり燈篭と化してしまいはしないだろうか。これでも一部のジェネレーション、ある種の好みの人のハンカチをぬらすものがあるとすれば、それはむしろ、ここぞと思うところでのスロー・テンポによる沈潜である。桑名の料亭でのお袖の舞がその一例だ。
もともと過ぎし時代の、作られた甘美な恋の色模様である。それを映し出すには、それにふさわしい人工的なプリズムが必要だ。・・・もっともな意見である。そんなことは百も承知で、天然色ワイド・スクリーンに贅を尽した。朝もやをついて、喜多八がお袖に舞を仕込む場面には、もやを煙のようになびかせて、絵画的な美しさをかもし出した。それを演ずる若き二人が山本富士子と市川雷蔵とあれば、そのネーム・バリューに、今どき文句のあろう筈はない。
だが、そうした場面を別に“オイチニ”の薬屋や、当時の芸妓屋や、木賃宿が描き出されると、天然色ワイドの画面は、ちょうど蝋燭の照明のもとで発達した歌舞伎に、明るい電気照明をあてたときのような味気ない不自然感を与える。
一つの“約束された”布石としての明治の風物は、墨絵のようにぼかされた黒白の画面でないと、どうもボロが出るようだ。山本富士子の古典的な美しさに不足はないとしても“髷をつけない”市川雷蔵にひそむ現代的憂愁は、父の仇という拭いきれないしこりを持っている筈の二人の手放しのロマンティックな結びつきに抵抗する。
見る方が“新派”という名の約束づくめの“こひつ”の中に自分から好んでうずくまって、一歩も手足を出そうとしないならばともかく、そうでない限り、外形だけをどんなにつくろっても、どんなに彩っても今更どうにもならない距離が、ロマンティシズムの場としての明治との間には、感覚的に出来てしまっているとはいってはいけないだろうか。
それにしては、この映画、人間的な“何か”を現代に通じさせようとする内容的な工夫に欠けた厚化粧にすぎたようだ。興行価値:雷蔵、山本のコンビもよく、衣笠演出の重厚さで大作の貫禄をいかんなく発揮、『すれすれ』の併映もよく、封切はヒットした。(キネマ旬報)

|
4月21日五年振りの東京撮影所入りした雷蔵さんを迎えた、衣笠監督、山本富士子さん、小野道子さん お仕舞と謡曲によって描かれている作品だけに観世流の木原康次、康夫の両師匠に雷蔵さんも、山本さんもみっちりと習ったため絵の様な美しいシーンをくりひろげました。(よ志哉17号より) |
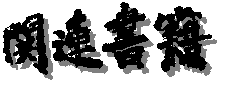
幽玄神怪、超理念の領域へ
飛騨天生(あもう)峠、高野の旅僧は道に迷った薬売りを救おうとあとを追う。蛇や山蛭の棲む山路をやっと切りぬけて辿りついた峠の孤家(ひとつや)で、僧は匂うばかりの妖艶な美女にもてなされるが……彼女は淫心を抱いて近づく男を畜生に変えてしまう妖怪であった。 |
泉鏡花(1873-1939) 金沢生れ。本名・鏡太郎。北陸英和学校中退。1890(明治23)年上京、翌年より尾崎紅葉に師事。'95年発表の「夜行巡査」「外科室」が"観念小説"の呼称を得て新進作家としての地歩を確立。以後、「照葉狂言」(1896年)、「高野聖」(1900年)、「婦系図」(1907年)、「歌行燈」(1910年)等、浪漫的・神秘的作風に転じ、明治・大正・昭和を通じて独自の境地を開いた。 生誕百年の1973(昭和48)年には、金沢市により「泉鏡花文学賞」が創設され、1999(平成11)年、鏡花生家跡地に「泉鏡花記念館」が開館した。 |
|
尚、「泉鏡花文学賞」三十周年記念"泉鏡花フェスティバル"2002(平成14)年11月7・8日では、『歌行燈』が上映された。
|

![]()



![]()