
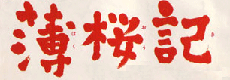

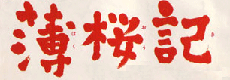
|
||
|
[ 元禄七年 ] 正月。丹下邸で謡初めの会を催すというので招かれた千春の父権兵衛、兄の長尾竜之進始め親類縁者、それに典膳の同僚や堀内道場の幹部級を混えた大一座の賑わい最中、矢庭に刀を執って座敷を飛出して行った典膳は一頭の古狐を仕留めて一座の人々に示した。(これは老僕嘉平次に命じてひそかに買求め飼育していたものである)「千春と瀬川某と密通の風評は、或いはお聞及びかとも存じまするが、密夫の正体は此の妖狐の仕業と判明しました。斯く成敗の上は、今後再びその惧れは起ることも御座いますまい。何とぞ御疑念をお霽らし下さいますように」妖狐変化の存在を信じ切っていた蒙昧な、迷信深い当時の人々は、見え透いた丹下の計略にコロリと乗せられて、頭ッから此の作り話を肯定し、噂は口から口に拡がって千春の姦通の汚名は払拭された。 それを見届けた上で、典膳は離別を宣言した。千春は覚悟の上だったが、兄の竜之進は断じて受付けない。千春の潔白は典膳自身が狐を退治して証明した。されば何を理由に離別するというのか?妻の不貞を認めるならば姦夫姦婦共に討ち果すべきだが、そうすれば、「寝取られ男」のさげすみを免かれる訳にはいかない。我が面目も保ち、妻の不名誉も救い、暗黙のうちに妻の実家の諒解も得て、三方都合よく納めたい・・・・・という典膳の算呂盤は、相手の感情を計算にいれていなかったので勘定に狂いが出来た。 (この辺の前後の運びは、作者も計算をあやまったらしい節々がある。例えば、小説の此の時期は犬公方綱吉による「生類憐れみの令」の一番厳しかった頃で、蝶々、蜻蛉、キリギリスの類を虫籠に入れてさえ罰せられる。況や狐を斬ったことなど表沙汰になれば家名断絶どころの騒ぎでは済まない。だから狐退治の場面に、絶対秘密の厳守される親戚以外の人物を列席させようなどしてはもはや処置無しというものである。) 離別した千春の身柄を、受取れ、受取らぬの諍論の揚句、憤怒に逆上した竜之進は抜討ちに典膳の片腕を斬落してしまった。その事件があって旬日後、高田ノ馬場の決闘。安兵衛、遠縁の菅野六左衛門に助太刀して村上兄弟の一党を討つ。 (巷談の俗説を排し、堀部弥兵衛とその娘が安兵衛を声援したりなどする場面無し。但、瀕死の菅野を背負って市ヶ谷まで辿り着いた時、此の作者によって生命を賦与されたお馴染の剣豪柳生連也斎と出会し、その計らいで尾州家の下屋敷に入ることを許され、菅野は安兵衛の介錯で武士の最後を潔ようする。) 安兵衛、忽ち江戸中の人気者となり縁談、仕官の申込み降るが如くで、堀部弥兵衛もまた勧誘員の一人として登場して来る。安兵衛につきまとう町娘の中にお豊とお志津の二人がある。二人とも安兵衛が内職にしている筆作りの卸元の筆屋の娘である。お志津は安兵衛が出入りしている書家の静庵に筆を納めている関係から特に安兵衛に馴馴しく、一方お豊の方はまことに古風に恋患いで臥ってしまっている。しかし安兵衛は両手に花のいづれをも振切って、堀部家へ入婿するというプラグマティズムの直線コースへ踏み切った。 (−と云風に作者は明解に割り切っていないので、解明が頗る厄介になる。結論は持って廻って結局そこへ到達するのだが人間心理の微妙な揺曳が文学の特質なのであり、映画とはその文法が違うのだから−議論は措く。) ここに、一代の豪商紀文こと紀伊国屋文左衛門が登場して来る。彼は幇間書家の静庵を通じて安兵衛に近づき、かねて抱懐する遠大な海外渡航の計画に安兵衛を同志の一員としてその陣営に誘致しようと働きかける。 一方、片輪者になった典膳は役向きを退き世上と交わりを絶って深川に隠栖し、老僕嘉平次と二人だけの生活に入るが、斬られた腕の疵はなお疼き、千春への尽きぬ未練とはいやさらに疼く。 一旦のあやまちこそ犯したれ、千春が典膳に対する思慕の念は、去られた後にいや熾り、見る目も不愍な有様に、親の方が堪らなくなって、何としてでも復縁させてやりたいものと(−どうも此の親子の考え方というものが私には納得行かない。典膳を不具者にしたのは誰なのか。その為に典膳が世間から葬り去られるに至ったそもそもの根源に就いて、千春は何と考えているのか?)親子で揃うてノコノコと典膳の隠宅を探し歩いて、やっとつきとめて、面会を懇請した。 典膳は作者の創成した主人公であるが、その言動の前後撞著には「最も不甲斐無い精神であった」と作者自身が歎ぜざるを得なかった(だからこそ面白いのであり、私もこの主人公を愛するのであるが、それをシナリオに表現するには私の力は及ばなかった)−そうした不甲斐無い典膳ではあったが、長尾父娘の来訪の趣旨に対しては、毅然たる武士の節度を崩さなかった。 典膳は嘉平次をして峻拒させた。権兵衛もさすがに面談を強要出来る筋合いの事では無いので不精々々諦めて帰りかけたが、典膳の窮乏を察し、手土産と称して若干の金を置いて行こうとした。これが硬骨嘉平次の土性骨にガン!と徹えた。 「以前の舅どのとて縁を切れば他人。他人様の施こしをお受けなさるほど丹下様の武士道は落ちぶれては居られませぬわい」と一蹴し、激昂した権兵衛は「下郎の分際で楯づくかッ」と、あわや引き抜きかけた肘を、通り掛りざまにぐィと掴んで制したのが安兵衛である。その臨機の働らきに、血を見ずして其の場は納まった。 問題のヒロイン千春を此時安兵衛は初めて見た。そうしてこれが縁となって典膳と知り合うことになって行く。 さて、先に述べた紀伊国屋文左衛門は、切角目星をつけた安兵衛が、堀部弥兵衛の娘幸と祝言して入婿となり、浅野内匠頭の家臣に納まってしまったので、今度は失意落魄の剣士典膳に目をつけて、海外貿易の大望に荷担させることに成功し、月々の生活費を支給する約定まで取結んだが、それが思いもかけぬ紛争のキッカケとなって(−経緯は複雑多端で簡単に説明出来にくいから省略する)一刀流に対抗する知心流道場の剣士十四、五名を相手に決闘しなければならない羽目になった。片腕を失って以来初めての立合いであるが、隻手縦横無礙、瞬く間に四、五人を斬り伏せたところへ、それと聞いて駈けつけた安兵衛が助勢に飛込んで残余の連中を潰走させたが、いくら封建殺伐の時代でも無闇に人を殺傷して其儘で済む筈が無い。 典膳は吟味五十余日の後、ようやく牢から放免された。「喧嘩両成敗」で「江戸一里四方追放」の裁定だったのを、裏面運動で司直を動かし「お構い無し」にまで持って行ったのは、一ツは例の紀文の財力、一ツは米沢藩の江戸家老千坂兵部の政治力。 千坂はかねて深い洞察力を以て、千春離別一件に就いての典膳の苦衷を理解し、惻隠の情を懐いていた上に、典膳を斬った兄の竜之進と同居して居なければならない千春の境涯を愍れんで我が屋敷に引き取ってやっていた−そうした関係もあっての援助だった。 しかも牢を出た典膳は、千坂の権勢と紀文の財力のいづれも忌避して、家財を売り払い、嘉平次にも暇を出し、浅草お蔵前の人足元締である白竿屋長兵衛の許に身を托した。長兵衛は、鳶の者との詰らぬいさかいでお咎めを受けて入牢中、典膳と相知ったのである。(これは有り得べからざる事であるが、上り座敷と町人牢の区別を無視して、現在の雑居房並みに解釈して書かれてある) この長兵衛の妹のお三というのが典膳に恋着するようになる。典膳もまたその心情にほだされてお三を妻と定め、千春への煩悩を断ち切って新生活へのスタートを決意したが、これには兄の長兵衛が真っ向から反対した。白竿組請負の工事現場へ出向いて現場のイザコザに対して睨みを利かすのが用心棒としての典膳の仕事であるが、時折り、遠くの物蔭からひそかに典膳を見守っている女人の姿があり、それを千春と知り、その事実を我が眼で見極めている限り、お三を差上げる訳にはいかないと云うのである。 「どんな事情があってお別れになったにしろ、奥様は今なお先生を慕っていらっしゃる。先生も心の底では奥様の事を忘れ切ってはいらっしゃらない。それを無理矢理思い切り断ち切る為の道具にお三を嫁になさりたいとは、あんまり惨酷というものです。お三はあッしの大事な可愛い妹だ。どうしてあいつを喜ばせるようなそんな罪な言葉をお吐きになったんでござんす。あッしゃ怨みに思います」 理の当然な長兵衛の直言は典膳の心魂に徹し、素直におのれの非を悟って頭を下げた。「悪かった。結局サムライ根性が抜け切れない上に、片輪者という自分に僻みながらも甘えていた訳だ。よし!この片輪者がこの片腕でどれまでやって行けるか叩き直して見よう。所詮、自分を生かす道は剣以外にはあるまい。隻腕果して剣聖に伍し得るか、それとも名も無き野辺に朽ちるか・・・・」 (この辺は全篇の圧巻ではないかと思う。愛する者のふとしたあやまちから自分の人生に蹉跌いた人間の歎きが浮彫りに描かれているが、映画化の方式の約束上、自分は此の点を掘り下げることが出来ないで割愛してしまった) かくて典膳は飄然として白竿組を去り、そのまま消息を絶ってしまった。 (自・元禄八年−至・元禄十三年)空白の六年間の歳月が流れる。 [ 元禄十四年 ] 三月。浅野内匠頭「松ノ廊下の刃傷」。浅野家取潰し。安兵衛再び浪人となる。 [ 元禄十五年 ] 赤穂浪士の復讐計画進捗す。 時の米沢藩の当主上杉弾正大弼は、吉良上野介の伜が養子に行ったものである。もし赤穂浪士が復讐を決行するとすれば、子として親の討たれるのを傍観している訳にはいかぬし、下手に介入すれば側杖を喰って上杉十五万石がフイにならぬとも限らない。この責任の一切が千坂兵部の双肩にかかる。 まず、上野介を護衛のため、いわゆる附人が本所の吉良邸に配置されたが、むろん上杉家にはいささかも関係も無い浪人者、いずれも天下の喰い詰め者で、烏合の衆のことだからこれを統監する人物が必要である。千坂は典膳をそのポストに置きたいので、千春に命じてその所在を探索させる。 この数年間の典膳の行動は詳述されていないが、とにかく此の際には江戸に帰って、谷中の瑞林寺という古刹に籠居していたのを千春に尋ねあてられ、結局、附人になって吉良邸に入り込む。(典膳の隠れ家を千春に教えたのが安兵衛であることや、其他いろいろ錯綜した顛末あれど、一切略す)典膳と安兵衛との交誼は至って浅かったが典膳は安兵衛に特別な親近感を懐いて居り、これを相手に闘うことに苦患の業のごときものを感じる。 安兵衛もまた同じ念いである。しかし典膳を生かしておくということは、討入りに際して同志五十人の生命を空しく失うということである。大事遂行の障碍をなすものは親を滅しても排除されねばならない。典膳討たざるべからず。しかも討入りの日時は目睫の間に迫りつつある。本所の吉良邸の修覆が終ったので、これまで上杉家で暮していた上野介が我が本宅へ年忘れの茶会をやりに帰って来る−その日を逸しては又の機会はいつ再び巡り来るとも判らないし、その日が都合によると明日かも知れぬし或いは明後日かも知れないのだ。同志の不安と焦燥は頂点にまで達した。 安兵衛はツテを手繰ってかねて見知り越しの白竿組の長兵衛に会った。「今度江戸を見切って故郷の越後新発田へ引籠ることになったので、丹下氏にお別れの挨拶をして発ちたいのだが、それがしは元浅野の家来、丹下氏は吉良殿の屋敷に居られるので世間の思惑にも憚りあり、お訪ねする訳に行かないのだ。そなたに橋渡しを頼みたいのだが・・・・」「場所は?」「どこでなりとも」「貴方様お一人で御座いますね?」「無論のこと!」「日時は?」「早いほど結構。明日にでも江戸を発ちたいから」典膳は安兵衛からの申入れを承諾したが、「明日では早過ぎる。会う日はこちらから改めて報せるから」と、長兵衛に返答させた。明日では早過ぎるの意味が安兵衛には呑み込みかねたが、同志の偵察でその謎は解けた。上野介は明日はまだ本所の屋敷へは帰って来ないのだ。「典膳は知っている!」さすがの安兵衛も動転した。 典膳から安兵衛に「会おう」とことづけのあった十四日は朝から雪だった。長兵衛を従えた典膳が約束の谷中七面宮へ出向くと、相手は安兵衛一人と思いの外、横川勘平、毛利小平太などの五人の赤穂浪士と知れた。 「卑怯だッ、約束が違う!」と長兵衛が叫んだ時、早くも五人は典膳を取巻いた。しかし典膳はかくあるべきことを承知の上で出かけて来ている。「拙者は他の諸氏を斬りたくない。この勝負、堀部氏と拙者だけに極めて貰えないか」「よかろう」と言ったが、言葉の下から中村清右衛門が斬ってかかり、続く鈴田重八、毛利小平太の三人ともども転瞬の間に典膳の刃に伏したが、結局安兵衛に脳天から割りつけられて典膳は死んだ。 その夜、赤穂浪士は吉良邸へ討ち入った。 [ 付記 ] この片々たるダイジェストを作るのに正味丸三日を要しました。それほど此の小説は錯雑多岐を極めて居り、前後十数年間の時間経過はあり、とても映画にアレンヂすることはむつかしいと思ったのですが「どの様に改変されても差支え無い」との五味氏の言質を得たので、思い切った歪曲と換骨奪胎を敢てしました。その結果、あまりにも原型と違い過ぎる話になりましたので、原作の概略を摘記することにしました。 いわゆる話のヤマは、吉良邸討入当夜に先立って白昼飛雪の裡に行われた安兵衛と典膳の決闘にあります。目的の為には手段を選ばない境地に追い込まれて行く安兵衛の心事も哀れです。一騎討ちの対決であるべきものを加勢を求めて典膳に挑まざるを得なかった己の劣等感、乃至卑劣さも人間的であって大へん結構だと思います。それに対する典膳の心理も(小説には説明されてありませんが)納得出来ないではありません。たとえ彼の精妙剣を以ってしても赤穂浪士の討入りをその隻手に支え切れるものでは無く、いづれは死ぬに極まっているものなら、せめて心友の安兵衛と事前に雌雄を決したい。成ろうことなら上野介在宅の日を告げてやっておいた上で、剣一筋に生死を賭けたい、その気持ちは十分察せられます。作者の狙いもそこにあったと思われる。 ただ、小説の上では、典膳をその心境にまで持って行く必然性が希薄であり、具象的に展示されていない。端的な視覚化を性急に要求する映画の上に、そうした心理の隠微な揺曳を描出することは至難であるが、それこそがシナリオに課せられた当然の責務なのであり、そうして自分の能力では手に負えなかったのである。 脱稿までに五十日かかりました。まだかまだかと撮影所からは矢の催促だし、そのうちの十二日間は病臥して炎熱の日々を呻吟し、執筆どころではなかったのですが、遂に力及ばず、安易な、常套的な方式論に従って糊塗する始末となった。 「脚色者は斬ってやったが、こんな殺され方では死に切れないねェ」 典膳の亡霊曰く−である。 |
||