
妖僧

1963年10月5日(土)公開/1時間38分大映京都/白黒シネマスコープ
併映:「越前竹人形」(吉村公三郎/若尾文子・山下洵一郎)
| 製作 | 永田雅一 |
| 監督 | 衣笠貞之助 |
| 原案 | 八尋不二 |
| 脚本 | 衣笠貞之助・相良準 |
| 撮影 | 今井ひろし |
| 美術 | 柴田篤二 |
| 照明 | 加藤博也 |
| 録音 | 大谷巌 |
| 音楽 | 伊福部昭 |
| 助監督 | 黒田義之 |
| スチール | 小牧照 |
| 出演 | 藤由紀子(女帝)、万里昌代(千保)、片岡秀三郎(阿部君麻呂)、近藤美恵子(広海)、小沢栄太郎(藤原清川)、城健三郎=若山富三郎(藤原良勝)、小林勝彦(少尉名地)、成田純一郎(市原皇子)、丹羽又三郎(少尉松井)、島田竜三(大蔵卿犬養)、稲葉義男(藤原光成)、石黒達也(竹内真人) |
| 惹句 | 『その眼力は、すべてを白骨に変え、その念力は、千仭の谷を飛ぶ!女帝を守り風雲を呼ぶ不死身の怪僧!』『印を結べば大地を封じ!法力を念ずれば竜巻を起す!わが願い、ただ女帝を守るにあり!』 |
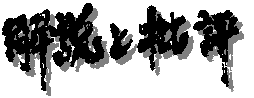

◆ かいせつ ◆
『てんやわんや次郎長道中』の八尋不二の原案より、『嘘』(1963)の衣笠貞之助と『若い樹々』の相良準が共同で執筆、衣笠貞之助が監督した異色王朝もの。撮影は『てんやわんや次郎長道中』の今井ひろし。
大映若手女優のホープ、藤由紀子と滝瑛子がそろって京都作品に出演、ドル箱スター市川雷蔵、勝新太郎とそれぞれ組んで精進している。
藤由紀子の作品『妖僧』(衣笠貞之助監督)は、弓削道鏡と女帝(孝謙天皇)の有名な恋物語を映画化したもの。雷蔵(道鏡)の相手としてだれを起用するか慎重に検討した結果、藤に白羽の矢が立ち、このほど衣笠監督、雷蔵と初めて顔を合わせた。
『妖僧』は大映が“超大作”と銘うつ作品だけに、衣笠監督もセットにはいった藤の衣装や髪に自分で手を出す意欲の見せよう。
「台本は何十回も読み直すこと。『湯島の白梅』で大スターになった山本富士子といまの君は同じ立場だ。女帝のイメージは広隆寺のみろく菩薩だよ」と藤にハッパをかける。
緊張して聞いていた藤のわきから雷蔵が「なま身に木像の気品はむずかしいな」とまぜかえし、あとはすっかりなごやかになったが、監督に山本富士子と比べられた藤は「比較にはならないけれど、精いっぱいがんばります」と張り切っていた。
一方、ハダカと度胸で名を売った滝瑛子は『悪名波止場』(森一生監督)で、勝新太郎と初顔合わせ。さきごろの広島ロケでは、田宮二郎を入れた三人で船遊びをしたあと初の共演、撮影に入った。いっしょに遊んだあとだが仕事になると、滝はまず改めて「よろしくお願いします」と勝にあいさつ、同時にすっかり緊張して、堅い顔になってしまった。そんな滝を見て、勝は冗談をいったり、滝の役柄ホステスの心理を説明したりの気のくばりよう。
おかげで撮影は順調に進んだが、「“悪名もの”の雰囲気は田宮さんから聞いてたとおりで親しめる。それにしても勝さんはおもしろい方。私の仕事でいちばんすてきな作品になりそう」とうれしそうだった。(西スポ 09/03/68)


![]()




◆ ものがたり ◆
厳しい山嶽仏教の修業に百人のうちで唯一人堪えた、行道は、恐るべき魔力を秘めた法力を獲得した。山を下りた行道はその法力を駆使して、病人を治し、やがて、その噂は宮廷に迄およんだ。類まれな美貌の女帝が幼時から不自由であった御足が、とみに悪化してきたというのだ。ひそかに招かれた行道は如意輪の秘法をもって遂に御足の痛みを取り去った。喜びの女帝は行道を重宝にし、忌憚のない言葉に耳を傾けた。
政権を欲しいままにする太政大臣・藤原良勝に反感を抱く左大臣・藤原清川、右大臣・藤原光成、大蔵卿犬養らは、行道の勢力に力を得、良勝が金銭を私している事を行道に告げた。この事実を知った良勝は、女帝の耳に達するのを恐れ、行道に刺客をさしむけた。しかし行道の恐るべき法力は、体を貫く刃に一滴の血も流さなかった。追いつめられた良勝は、かねてから不平をかこつ市原の皇子と語らい反逆の兵を挙げた。
法術で事を知った行道は、女帝を守るために永久に留まろうと決意、頭を剃り、見違えるような美僧の姿となり名を道鏡と改めた。道鏡の魔力と朝廷側の反撃が功を奏し、良勝の軍は敗走した。女帝の信任をあつくした道鏡は、権力に近づき、女人を愛し、僧の戒律を破った苦悩に悩みつづけた。新に大政大臣に藤原清川が、大政大臣禅師に道鏡が任じられた。女帝の愛寵を深くした道鏡は、天皇の位と同等の法王の位を与えられた。
嫉妬に狂った清川は秘かに道鏡を狙った。折も折、女帝は病に犯され必死に如意輪の秘法を念じる道鏡の法力もむなしく、女帝は絶命した。なきながらにとりすがる道鏡の背後から、清川の放った刺客が襲った。かつては、刃も通じなかった道鏡の胸も、今や法力はなく女帝の手を握ったまま崩れた憎の姿があるのみだった。
妖僧 押川義行
はじめの題名は「大いなる妖僧」。これをただの“妖僧”に変えたのは、内容にひきくらべてさすがに照れ臭かったからだろう。ラスプーチンの大先輩みたいな怪僧道鏡を描いているわけだが、女帝孝謙天皇の寵を得て、仏教政治時代を押立てた彼の政治的な野心や才腕についてはほとんど触れず、病気をなおした縁で女帝と結びつき、その愛情に身も心も焼きつくした“恋の男”として取上げている。つまち奈良時代のメロドラマというわけ。
日本の歴史の中からひっぱり出した女帝と一介の行者との恋のものがたり、−今までことさら避けて通った題材だから、それだけ新鮮でもあるし、着想として第一面白いが、でき上りは奇妙にもったいぶった恋愛劇に終始した。いくら面白い取り合わせでも、歴史的な背景がこうあいまいでは話が生きるはずもない。恵美押勝(映画の中では藤原良勝)がただの悪玉にすぎず、それに対する道鏡が、恋に行力を失った坊主というだけでは、第一話の構成がお粗末すぎるではないか。藤原百川や和気清麿なども何となく出て入ったりするばかりで、話はもっぱら道鏡の恋にしぼられる。その恋にも火のような激しさや、救いようのない暗さが描き込まれるわけではない。不治の病に冒されているらしい女帝は、道鏡への愛を唯一の喜びとしながら死に、煩悩のために長年の苦行も水泡に帰した道鏡は、みずから敵の刃にかかって恋人のあとを追う、という甘さに徹しているのだ。
舞台を宮中に限ったのは、この話の組立てようから察して、恐らく意識的なのだろうが、それなら政治の他愛なさをさえ描こうとしなかったのはなぜだろう。この恋物語にそれが欠けるくらいなら、「不如帰」でも作りなおした方がまだましというものではなかろうか?
しかし、何はともあれ致命的なのは、恋する男女に人間らしい真実感がないということだ。恋を描きたいなら描くものいい。だが、そのためにこの時代とこの人物を選んだのなら、選んだ理由を何らかの形で納得させなければならないだろう。興行価値:意匠をこらした大作だが、現代に通用する破格な面白さが不足。もう一つキレイごとでないパンチが足りず、50パーセント。(「キネマ旬報」より)
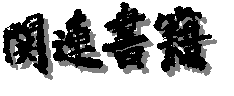

![]()


![]()