


1967年10月28日(土)公開/1時間39分大映京都/白黒シネマスコープ
併映:「なみだ川」(三隅研次/藤村志保・細川俊之)
| 製作 | 永田雅一 |
| 企画 | 辻久一 |
| 監督 | 増村保造 |
| 原作 | 有吉佐和子 |
| 脚本 | 新藤兼人 |
| 撮影 | 小林節雄 |
| 美術 | 西岡善信 |
| 照明 | 美間博 |
| 録音 | 大角正夫 |
| 音楽 | 林光 |
| 助監督 | 宮島八蔵 |
| スチール | 西地正満 |
| 出演 | 若尾文子(加恵)、高峰秀子(於継)、伊藤雄之助(華岡直道)、渡辺美佐子(小陸)、丹阿弥谷津子(佐平次の妻)、浪花千栄子(加恵の乳母)、内藤武敏(妹背佐平次)、原知佐子(於勝)、伊達三郎(下村良庵)、木村玄(妹背米次郎)、語り手(杉村春子) |
| 惹句 | 『美しくもすさまじい、妻と姑の愛と葛藤を描いた話題の名作を最高のスタッフで映画化!』 |
昭和42年/1967年キネマ旬報ベスト・テン第5位(ベスト・ワン『上意討ち』)
男優賞 市川雷蔵 (『華岡青洲の妻』 『ある殺し屋』)
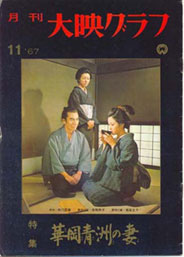
華岡青洲は江戸時代の紀州の医者である。研究熱心な名医で、世界で最初の全身麻酔による乳癌手術に成功したと伝えられる。この名医の生涯を、おなじ紀州=和歌山県出身の作家有吉佐和子が、女流らしいユニークな視点から描き出したのが小説「華岡青洲の妻」である。これはベストセラーとなり、舞台化され、テレビドラマ化され、またこの映画になった。
有吉佐和子は、華岡青洲自身よりもむしろ、彼をめぐる家族の女性たちに注目した。すなわち、母親の於継、妻の加恵、妹の小陸と於勝である。青洲の偉業はこれら家族が献身的に青洲を助けたことのうえに成り立った・・・と言ってしまえば家族主義を讃える単純な美談になってしまうが、ことはそう、単純ではない。じつはそこに、本人同士以外は誰も知らない姑と嫁との猛烈な嫉視反目があった、というのが卓抜なストリーテラーとしての作者の目のつけどころの面白さである。しかも、ただ姑と嫁の反目があったというだけならありふれた観察にすぎないが、反目しあう姑と嫁は、互いにそのことを表には現わさず、ただ息子であり夫である青洲のためにはすすんで自分の体で人体実験をしてもらう危険をおかし、そのことで競い合い、心の中だけで互いに相手にうち勝とうとしていたのだという。その結果は青洲の偉大な業績につながり、家名をとどろかし、二人はともに、賢母、良妻としてあがめられた。
いったい、母も妻も、偉らかった言うべきなのか、愚かだったと言うべきなのか、これもまた女の見事な生き方と見るべきなのか、これでは女はたまらないと見るべきなのか、どっちにしろそう簡単に割り切った判断をするわけにはゆかない立場に読者をさそい込むところがこの物語の面白さであった。
監督の増村保造は、一高。東大法学部の秀才コースををへて、大映の助監督となり、1952年から2年間、ローマの映画実験センターに留学、帰国後1957年に『くちづけ』で監督としてデビューした。ストーリー的には単純な青春映画であるが、感傷を排し、きびきびした行動性を積極的にうち出して、日本のヌーベルバーグの先駆とも言うべき問題作となった。イタリアでの生活が彼に、西洋的な自我の強さというものを教え、日本的な感傷的な映画作法を反省させたのである。
以来、クレージーなまでに愛の情熱のボルテージを高めた『暖流』、高度成長時代の日本の猛烈サラリーマンたちのその猛烈さの記念碑とも言うべき『巨人と玩具』、60年代安保闘争の時点で学生運動の内部崩壊的な傾向を鋭く予見していた『偽大学生』、女のエゴイズムを凄艶な美しさに高めてみせてくれた『妻は告白する』や『卍』、さらには感傷的な反戦を超えてもっと力強い反戦・反軍の行動を模索した『兵隊やくざ』や『清作の妻』、などなどの力作が相次いだ。
自己主張のエネルギーに乏しく、自己抑制を美徳と考えるのが日本映画の伝統的な欠点であると信じ、これを打倒するために、不自然であってもいいから登場人物たちを情熱的に行動させるというのが彼の信条だった。彼は見事にその主張を一貫させ、とくに1960年前後には日本映画の活性化の牽引車のような存在になった。1987年の暮れに惜しくも亡くなったが、日本映画の進路に大きな影響を残したその存在は大きい。
華岡青洲を演じた市川雷蔵は、この時期に大映映画時代劇を勝新太郎と並んで背負っていたスターである。凛として気品があり、チャンバラ映画の颯爽たる美男剣士役で人気があったが、抜群の演技力で現代劇でも劣等感に悩む『炎上』(’58)の主人公など、名演が多い。
姑の於継を演じた高峰秀子は、昭和初期に子役として人気があり、戦時中には少女スターとしてアイドルになり、戦後は本格的な演技派スターに成長したキャリアの長い大ベテラン女優である。
加恵を演じた若尾文子はこの時期の大映のトップだったスター女優である。演技力も充実していて、とくに増村保造と組んだ一連の作品で、表面はやさしいがシンは強靭きわまりないいくつかの女性像は忘れ難いものがある。前述の『妻は告白する』『清作の妻』の他、『夫が見た』(’64)『刺青』(’66)『赤い天使』(’66)『濡れた二人』(’68)などがこの名コンビによる力作である。
『華岡青洲の妻』はこの演技力十分の三人の大スターの組み合わせでファンを大いに満足させてくれた作品であり、とくに嫁と姑、女二人の内にこもった丁々発止のやりとりのうまさが唸らせる。( 佐藤忠男、大映版レザーディスク解説より )


華岡青洲の妻 白井佳夫
ベストセラー長編小説の映画化について
意地のドラマ − つらぬき通す美学
美談の裏のエゴの葛藤
1967年の「華岡青洲の妻」は、有吉佐和子の小説を新藤兼人が脚色し、増村保造が監督した力作である。江戸時代に、世界で最初の全身麻酔による外科手術をやって成功した紀州の医者華岡青洲(市川雷蔵)の麻酔薬調合の苦心の物語であるが、ドラマの核心は、その麻酔薬の人体実験に、彼の母(高峰秀子)と妻(若尾文子)が競って実験台になりあった、というところにある。表面的にはそれは美談であり、当時、人々もそうほめそやした。しかしほんとうは、姑と嫁との表には現れない激しい対立が、どちらがよりいっそう献身的に彼につくしているかを誇示しあう意地の張り合いとして表れたものだったのだ、というのが原作者の皮肉な解釈である。
美談と見えるものが一皮むくとエゴイズムの葛藤でしかない、というのは、むかし菊池寛の短篇などにもよくあった小説的な発想の一種であるが、たいてい、気がきいた見方だと思って面白がりはしても、感動はしないものである。ところが「華岡青洲の妻」は、適度の通俗性を持った良くできた作品であると思うと同時に、心を動かすものを持っている珍しい作品でもあった。
姑は申しぶんなく立派な大奥様と呼ばれている女性であり、嫁もまた、模範的に貞淑で孝行な女性と見える。ところが二人は、息子であり夫である青洲の愛情を自分一身にひきつけようと争っている。そこで、青洲がようやく完成した麻酔薬を人体実験できなくて悩んでいることを察すると、争って自分が実験台になろうとする。青洲は、二人の申し出に感謝し老いた母にはごく軽く麻酔薬を試みるが、母は軽い実験だったとは知らずに自分が役に立ったとおおいに満足する。妻には本格的な実験を試み、そのために彼女は盲目になってしまうが、彼女は自分こそが本当に役に立ったのだと満足する。青洲は母と妻の二人をともに大切にして丁重に感謝する。
しかし、青洲の妹は、兄たちの心の裏をちゃんと見抜いている。兄は母と妻の心の争いを知っていながら、知らぬふりでそれを利用した、というのである。この妹は、それで、男というものは恐ろしいものだ、と思うようになり、せっかくの兄の門弟の良い求婚者がいながら、独身のまますごして病気で死んでゆく。この妹は、いわば青洲の心理をさいごに解説する役割であり、彼女が青洲の妻に、自分はみんな知っていた、母と妻の争いを冷静に利用できるのだから男は恐ろしい、とうのが、全体のドラマの鮮やかなしめくくりになっていた。
ただし、兄をエゴイストだと思うからといって、すべての男がそうだと思うのはおかしいし、だから独身で通すというのは不自然である。そこでこの人物は、いかにも青洲の心理を解説するためにだけ登場しているようなわざとらしさが生じる。この人物が青洲の正体を見抜いたようなことをいうことによって、この作品はたいへん分かりやすくなっている。と同時に、いささか安直に解説されてしまったような味気なさも感じ、それがせっかくのこの力作をいささか通俗的に感じさせることにもなる。
青洲は母と妻の争いを知ってて利用したのだろうか。だとしたら相当に利己的な、目的のためには手段を選ばない男である。小説では母と妻の心理は克明に描かれているが、青洲の内面はまったく描かれていないので、その心理はわからない。妹のいうとおりかな、とも思う。これを映画では、市川雷蔵がじつに堂々と演じた。どこから見ても誠実な男、人々のために献身的に努力し、医は仁術という立場をなんの迷いもなくとりつづけている男として演じた。
立居ふるまいに凛然とした威厳があるという点で日本の映画スターのなかでもきわだっている雷蔵であるだけに、彼はそんな利己的な人間には見えないのである。むしろすがすがしい。もちろん、そんな利己的には見えない人間がじつは利己的であった、と考えると皮肉な面白さになるし、誠実で立派な男が、別に後ろめたい気持ちもなしに母と妻の争いを利用することができた、と考えると、なるほど男というものは恐ろしいものだ、ということになる。
しかし、すがすがしいほどに凛然とした雷蔵を見ていると、また別の考え方もうかんでくる。「華岡青洲の妻」は、せっかく、美談と見えるでき事の裏の卑小な心理を暴露して見せてくれるのであるが、そういわれると逆に、いや、あれはやっぱり美談ではなかったか、と天邪鬼な気もしてくる。
『華岡青洲の妻』に見る封建制と近代 佐藤忠男
封建時代には、職業は個人のものでははなく、家のものだったのである。夫が一人仕事をしているにしても、その仕事は家族によって支えられ、家族によって伝承されたものなのである。青洲が偉業をなしとげるということは、そのまま、華岡家が偉業をなしとげたことになるので、彼女たちはあながち、息子や夫の犠牲になるつもりで麻酔薬を試みたわけではなく、家の名誉を輝かせるとう誇らしい気持ちのほうが強かったかもしれない。
封建社会とはまさにそういうものだったはずである。とはいえ、封建社会の人間には家が大事という意識だけがあって個人の意識がなかったというわけではないから、そこには姑と嫁の意地の張り合いという要素もあっただろう。この作品ではそういう個人的な心理だけが正面におし出されて、封建社会の女たちの毅然とした誇りのほうは、いくらかお留守になり、そのためこざかしい作品になったといううらみが残る。ただ、市川雷蔵はさすが時代劇スターだけあって、封建的人間の誇りというものを、その立居ふるまいにはっきりと見せていた。
封建的ということは、今日では全面的に悪いこととなっている。しかし、封建的であることの良さ、というものも、ないわけではないのである。心の中のいっぽうの極にエゴイズムがあっても、もういっぽうの極には、つくす、とう精神があり、そのバランスの中に人間が形成されることである。そのつくす相手が貪欲なだけの支配者でしかなかったらどうしようもないが、必ずしもそれだけではないであろう。現に華岡青洲とその一家は医学のために献身したのである。つくす、という精神は、理想的なかたちにおいては責任という精神と組み合わせていなければならない。
華岡青洲は、母と、妻と、そして嫁にもいかず家の雑用をやりぬく妹たちによってつくしぬかれる。封建的人間の堕落した連中は、つくされてただいい気になって横柄にふるまっていただけであろうが、封建的人間のすぐれた者というのは、つくされればつくされるほど、その責任というものをひしひしと感じて精進したと思うのである。つくされるにふさわしい立派な人間であろうと努力したと思うのである。そういう人間がいたはずだ、と考えなければ、封建時代というのはぜんぜん闇ではないか。
封建時代は闇だから、それを否定して近代性がうちたてられたのだ、近代に生きている俺たちのほうが封建時代の人間よりマシなのだ、と考えていい気分になるのは用心したほうがいい。人間というものは、封建時代にも封建時代なりに立派な生き方を模索してゆくものであるから、近代という別の時代になっても、それなりに良い生き方の模索ができるのだ、と考えたほうがいい。
時代劇のスターというのは、封建時代における人間の立派さというものを、近代の今日からふり返ってみるためにわれわれがつくり出したものだ、ともいえるかもしれない。市川雷蔵は、封建的人間の毅然とした態度を演じると比類のない俳優であった。だから、原作ではあまり具体的に描かれていない青洲も、映画ではすぐれた封建的人間に見えた。それは、やや、個人的な感情に偏っている姑と嫁のドラマから超然とした存在にも見え、作品全体のバランスを崩していたかもしれない。しかし、私はむしろ、そこに封建的人間というものをどう考えるかということについてのわれわれの価値観の未整理の部分があらわに見えて興味ぶかく思えたのである。
個人の果たすべき役割を明快に
われわれが時代劇を見ることを好む理由のひとつは、時代劇においては、個人の役割というものが現代劇よりもよほどくっきりと見える、ということであると思う。封建時代は身分本位の社会ある。身分本位の社会では、ある状況で個人がどう行動すべきかとうことは、身分に応じてくっきりときまっている。身分の高い侍は、平和なときはのうのうといばっていてもいいが、戦争に負けたときなどは、いさぎよく腹をきらなければならない。このとき、みっともないふるまいをすることは許されない。
近代社会ではそれがあいまいになってくる。職場では身分が高くて部下に命令できても、職場以外では他人に命令することはできない。では職場以外の場で部下とつきあうときはどうしたらいいのか、目上らしく、仕事以外のことにも威厳をもって指導したほうがいいのか、それとも全く対等になってしまったほうがいいのか。むしろ部下の機嫌をとるようにするほうが好まれるのか。そのへんは微妙なところで、みんな気を使っているのである。気を使って、上役だからといっていばることもしなくなるとともに、いざというときにはみごとに責任をとるという道徳的な美意識も失われがちで、頼りない。
田中角栄のように、元首相という身分でありながら逮捕されてもぜんぜん恥ずかしいと思っていないみたいなみっともない人物が選挙の結果では許されている。その複雑さを調整して合理的にやってゆくところに近代社会が成り立つわけであるが、ときどき、もっと単純ににすっぱりと割り切れた人間関係というものを見たくもなる。
時代劇では、誰が誰につくすべきであるか、とか、誰は誰に対して責任をとるべきであるか、とか、誰は誰に対してはぜったいにみっともないマネはできない、というこは、その人物たちが登場したときから、もう、すっきりと分かるようになっており、しかも、職場や城中などの公的な場と、町や家での私的な場とでそれが区別されるということもない。つまり、個人の果たすべき役割というものが明快なのである。明快だから単純で面白くない、ということもいえる。
「水戸黄門」みたいに、「天下の副将軍であるぞ!」と名乗りさえすればどんな難問も解決するというのでは近代的な人間は単純すぎて面白くない。そこで「華岡青洲の妻」のように、一見、封建的な思想に殉じたような女たちが、じつは個人的なエゴイズムの葛藤で行動していたのだ、と暴露してみせる近代的な時代劇もつくられる。しかも、その近代的な解釈の面白さもさることながら、それだけではやはり、わざわざ時代劇をつくる意義は薄いので、そのいっぽうにおいて、女たちの内心の葛藤を知ってか知らずか、鮮やかに家父長らしい毅然たる役割を生き抜いた青洲の風格というものが静かにひとつの魅力になっているのである。また、動機は姑と嫁の自我の張り合いであっても、結果としてはみごとに、家業に殉じたことになる女たちの生き方の壮烈さが、皮肉を含みつつ、やはり感動的なのである。( 「君は時代劇を見たか」じゃこめてぃ出版1977年刊 )
ベストセラー小説の映画化 佐藤忠男
ベストセラー小説の映画化である。ベストセラーになる小説というものは、内容の深さはともかく、ストーリーとして面白くできていることはほぼ確実であるし、一般にアピールする要素が含まれていることも間違いがない。したがって、原作をほぼ忠実に映画に移しかえるだけでも、商業映画としてある程度の成功をおさめる見込みはたてられる。しかし、ストーリーとして面白いということは、必ずしも映画としての表現の面白さを約束するものではなく、むしろ、しばしば、原作のストーリー的な要素を過不足なくつめこまねばならなくなる結果、映画的表現のポイントを見失うことのほうが多いようである。
ことに最近のように、ベストセラー小説というと片っ端から連続テレビドラマになる時代になってくると、時間的にどうしても原作をダイジェストしなければならない劇場用映画は、ストーリーを巧みに物語るという点では、原作どおりにやることの可能なテレビに比べて、根本的にハンディキャップを背負っていることが明らかになってきている。このハンディキャップをのりこえるためには、テレビでは効果のうすい映画的な表現力を可能なかぎり生かさなければならない。ところが、なまじ原作がストーリー的に面白くできているだけに、それを要領よくきちんと展開するだけで、映画になったと安心してしまう傾向もおおいにある。
有吉佐和子の小説を、新藤兼人は要領よくまとめている。それをさらに、増村保造の演出はあぶなげなく映画にうつしかえている。演劇でいうウエル・メイド・プレーという言葉に相当する映画であろう。決して出来は悪くないし、観客にも安心してすすめられる。しかし本当になにか、充実した映画を見た、という感銘には欠けるものがある。というより、これならば原作の小説を読めば分る、と思うのである。
ダイジェストすることによって、原作のある一面がとくにくっきりと出てくる、という効果はある。この映画の場合、やたらと人間の死というものが連続するということがそれである。ヒロイン加恵の祖父の死からはじまって、青洲の父直道の死、青洲の妹小勝の死、長女小弁の死、青洲のもう一人の妹小陸の死、そしてもう一人のヒロインともいうべき青洲の母於継の死、と、チャンバラ映画でもないのに、一篇の映画のなかで実にたくさんの死の場面があり、その多くが、白布を顔にかけられた遺体や、祭壇や、葬式の行列で描かれる。
一人の人間の生涯は、たしかに多くの近親者の葬式に立ち会わねばならないし、原作でもたしかにそれだけの人間が死んでいっているのだが、それらの人々の生きている間の生々したイメージが相当省略されているのに、死ぬ場面だけはストーリーのきまりをつける必要上映像としてちゃんと残ると、結果として、生のイメージは減少し、相対的に死のイメージがふえることになる。おなじ人数の死しか扱っていないのに、映画のほうが原作よりだいぶ縁起が悪い感じになっているのはそのためであろう。
もっとも、このたくさんの死は、一人の天才、華岡青洲という人物を大きく見せる効果もないではない。父の直道はすべての希望を託して死んでゆく。二人の妹は、彼の医学的な使命感をかきたてずにはおかないような死にかたをする。そして母と妻は、彼の業績のために命を賭けて実験台になるという。つまり、多くの死が、あたかも、青洲という一人の人物の業績をきわだたせるためであるかのようにそこに置かれている。おしまいのほうで小陸が、男は母と妻との争いすら利用するものだ、と、死を目前にひかえて語るが、そこにそれらすべての死のイメージが集約され、意味づけられている感がある。
しかしこれは、一面の真実を語るものではあるかもしれないが、いかにもネガティブな真実であって、見る者の心をふるえあがらせもしなければ鼓舞し昂揚させることもない種類のものでしかない。青洲という人物をきわだたせるためなら、彼の人物や仕事そのものを、もっと、力をこめて表現すればいいわけである。
もちろん、この題材は、題名が示しているとおり、妻が中心人物であり、嫁と姑の争いという、古くて根強い問題が芯になっている。姑が息子を独占しようとして嫁を疎外する。これに対し、嫁は断固攻撃に出、夫に対する自分の権利を主張する。しかもそれが、たがいに立派な家柄の出の女性だけに、口穢いののしり合いや、露骨な陰口のかたちではなく、表面きわめてきれいごとな献身くらべとして行われ、結果は世にも稀な美談になるというのが、意表をついたストーリーのミソである。つまり、女たちの強烈なエゴを描くことが眼目だと見られるし、於継、加恵に青洲を加えて、三人の男女の強烈なエゴを描くのが眼目だったと考えてもいいだろう。
そして、いうなれば、そのエゴの強烈な者ほど堂々と生き、エゴの弱い者、たとえば青洲の二人の妹などは、エゴの強い者たちの堂々たる生き方のまえには、いわば肥料のような役割をはたすに甘んじなければならなくなるといった人間社会の様相が展開されていると見ることもできる。
しかし、その意味からするとこの女二人の争いが、たんに、母親の息子に対する溺愛から生じた性格的なものというのではつまらない。それなら要するにどんな立派そうに見える家も内情はこうだ、というだけの興味を満足させるものになってしまうからである。母親のこの態度を、たんに嫁に対する嫉妬という以上に、もっと根深く、もっと強烈なものとして描き出すことが、加恵や青洲のエゴをも、より強烈なものとしてきわだたせるために必要だったと思う。
映画のなかのセリフで、しきりと「美しいお母さん」という言葉が繰り返される。加恵は於継があまりに美しい女性であったために、彼女に憧れて見知らぬ青洲の妻になったという設定である。この於継という母親が、文字どおり惚れ惚れと仰ぎ見るような美しい女性であることが重要なのである。それはたんに、美人であるという以上に、封建的な時代においても、女性は、美貌と、才気と、気位の高さと、実家の家柄などによって、堂々と家庭に君臨し、近郷近在にその名をとどろかせることができた、ということの象徴的な表現であると見たい。
そして、加恵はその意味において於継に憧れたのであると見たい。そう見ることによって、青洲、於継、加恵の三人のエゴのからみ合いは、はじめて、バランスのとれた壮烈なものとなるはずだからである。
しかし、小説では、於継は美しい女性だった、と書けば読者はそれを信じるよりないが、映画では、その美しさを本当に見せなければならないのだから難しい。しかし、たとえば、於継が加恵の両親に縁談を申し込みにきて堂々の熱弁をふるう場面などは、もっと於継の態度に大きな比重をかけて描いてほしかったと思う。
もちろん、あの場面をもっとたんねんに、とか、この場面をもっとていねいに、などと言っていたら、時間に制限のある映画ではないものねだりになるが、少くとも、たくさんの葬式の場面などもっとなんとか省略して、死よりも、生のイメージのほうにもっと力を入れてほしかったと思う。
かつて増村保造は生の歓びを謳歌する映画作家として第一人者だったと考えるだけに、生よりも死のイメージのほうが、あまり意味なく前面にのさばりすぎる感のあるつくりかたには、やや意外な感じもしたのである。
この映画は佳作と呼ぶことはできる。しかし、増村保造には傑作をつくってもらいたい。(「キネマ旬報」67年11月下旬号より)
華岡青洲の妻 白井 佳夫
ベストセラーの長編小説の映画化について、まず考えさせられる作品である。この点では、もはや映画は、テレビの敵ではない。ワン・クールもツー・クールも使って原作のエピソードを重層的に追えるテレビにくらべては、1時間3〜40分の映画は、しょせんくらべものにならぬくらい、不利である。
また、小さなブラウン管にくらべて、横に広い精妙な視覚を持つ映画の画面は、独りの俳優が娘時代から中年までの役を、人工的なメークアップによって演じることの不自然さを、なさけ容赦もなく暴露してしまう。これは実は、映画のリアリズムの進歩であるわけなのだが、この場合、それが逆の作用に働いてしまっていることになる。
要するに、長い年代記的物語を、編年体で展開するドラマは、もう映画にとって、時代遅れになってしまっているということだ。原作の物語を、眼で読みたい、といったファンの素朴な要求への応対は、そろそろテレビに一任してしまった方がよろしい。
それでは、もう映画は『華岡青洲の妻』のような原作は映画化出来ないのか。実はそうではない。ひとケタ次元をズリあげたところで、それはテレビよりもステージよりも面白く、立派に可能なはずである、若尾文子のヨメと、高峰秀子のシュウトメの、日本的な精神と整理の葛藤を、映画的リアリズムのスペクタクルとして、ぐんとクローズ・アップする方法である。
そのためには、映画はもう、チマチマと長大な物語の筋を追っかけるダイジェスト精神を放棄し、因果話的エピソードの積みあげと、抒情的な郷愁のドラマを組み合せ、人の一生をしみじみ描く、といった絵草紙趣味を放擲してしまわなければダメだ。
オール・セットに近い板ツキのお芝居で、手廻しよくストーリーをまんべんなくナゾるのは、もはや愚かなことなのだ。なまじ巧くツジツマがあっていればいるほど、それは薄っぺらな、ウソごとのお芝居ごっこに見えてきてしまう。
華岡青洲・市川雷蔵を中心にすえた、ヨメ・若尾文子とシュウトメ・高峰秀子の、厳然たる家父長制家族主義と封建的人間関係の中の、屈折したエゴイズムの確執は、もっと広いパースペクティヴを持って、壮絶に、その部分だけスポット・ライトを当てられてしかるべきだった。そのためには、現在、増村保造監督が自分のプライベートな生活の中で、あるいは実感しているかもしれない、そして僕自身が私生活の中で実感しているかもしれない、日本的な生活環境と、人間関係と、精神と生理の重みが、もっと画面の内側に、ジワジワとにじみ出てこなければならない。
せまい土地の中で、木と紙の家に囲まれ、小さい部屋に何人もの人間が鼻をつき合せている生活の中から、何の壮絶なエゴイズムが、何の重量感を持った精神が、生れてくるものか、という反論もありそうである。しかし、石の家と荒々しい自然の中から生れた強靭なエゴイズムと違った、もっとシブトく、もっとトリビアルであるだけになお始末の悪い、図太いエゴイズムや精神が、この風土、われわれ日本人の生活環境の中にはあることも、知らねばならない。
これに喰いさがるのは、なみていていのことではない。キメ手のように出すつもりはないが、溝口健二は、それをやった。日本の土と、日本の風土が醸成した、特殊な精神と生理の生んだ壮絶なドラマとして、映画的自然主義リアリズムで、それをみごとに表現してみせたのである。ワイド画面の新しいリアリズムによって、市川雷蔵をまん中に、若尾文子と高峰秀子がプライベートな精神や生理の中にも、生来持っているに違いない日本的なものを、ぐんと増幅しクローズアップすることから、この原作を足がかりに、増村さん、あなたはもう一歩も二歩も三歩も、自分の『華岡青洲の妻』を映画的に創造することに挑戦すべきではなかったのだろうか。 (興行価値:原作もよく知られ、作品も一応の水準には達して、俳優も揃っており、本来なら興行価値80%は十分にあるのだが、宣伝のポイントにあやまりがあったようだ。「キネマ旬報」67年11月下旬号より)
偏見・ビデオ館・・・柴田理恵がすすめる
『華岡青洲の妻』
この映画がきっかけで6キロ太った。
三年前にケーブルテレビでこの作品を観たのがきっかけで、一気に雷蔵さんにハマッたんです。もちろん子供の頃から「眠狂四郎」などは知っていましたけど、あのシリーズって結構エッチな場面ありますよねぇ。女の敵役を狂四郎がサッと斬ると、着物の前が真っ二つなって白い柔肌が見えたりとか。だから、子供心に「あ、これは子供が観ちゃいけない映画なんだ」と思って、雷蔵映画に浸る機会がないまま時間が経ってたんです。
それだけに、この『華岡青洲の妻』にはすごく驚きました。時代劇だから、例の如く二枚目かと思ったら、わざと不細工にしてるんじゃないかと思うくらいのメイクだし、シリアスな物語の中できっちりと日本初の麻酔医の役を演じてますしね。
もう翌日からは雷蔵さんのビデオを借りまくり、買いまくり、入手可能な限り観ました。その上でなお、この作品に新鮮さを感じました。というのは、現代劇ではまるで公務員みたいな地味な顔をよく見せますが、時代劇で白塗りをしないで、しかもこういう名作に出てくるのはあまり数が多くないからなんです。
そして雷蔵さんに関する本も読み漁りました。それによって、彼の役に対する真摯研究熱心ぶりを知って、ますます虜になったんです。どんな二枚目として人気があっても、そこに安閑としないで、社会問題を扱った作品から『初春狸御殿』のような超娯楽作品まであらゆるジャンルに挑んでます。そしてその度に変幻自在で、どれにも偏ることなくどれもが魅力的。
私、こういう人、好きなんですよ。例えば伊東四朗さん。何年か前の年末、松本清張さん原作の「けものみち」で執念深い刑事を陰惨なまでに演じてるかと思えば、紅白歌合戦では電線マンを乱舞している。何て素晴らしい人なんだろうと思いました。シリアス路線で売れても決して昔の自分のギャクを拒否しない。その幅の広さは雷蔵さんに通じるものがあります。改めて市川雷蔵さんの演技者としての貪欲さに敬服しています。
でもこの映画がきっかけで雷蔵ビデオに耽溺したあの夏は、典型的なカウチポテト族になって六キロも太ってしまいました。
有吉佐和子は「紀ノ川」(1959)で文壇的地位を確立し、この「華岡青洲の妻」で1966年の女流文学賞を受賞した。芥川賞の候補にもなった56年の処女作「地唄」から急逝の84年までの30年に近い作家生活を展望すれば「華岡青洲の妻」を発表した頃が、有吉佐和子の頂点だったのではないだろうか。その有吉佐和子は、「古い世界にある意地、かたくなさ、しぶとさ、うぬぼれといったものを、現代に生きる人間の目で見直そうとする」という思いを抱いて出発した作家である事を考え合わせると、「華岡青洲の妻」の存在が光って来るように思う。尚、「華岡青洲の妻」は新潮文庫で読める。



小説「華岡青洲の妻」は、1966年に新潮社から出版されベストセラーとなる。この小説により医学関係者の中で知られるだけであった華岡青洲の名前が一般に認知される事となる。小説では華岡青洲の功績を、実母と妻との「嫁姑対立」と云う現代にも通じる問題に絡めながら、実母や姉・妻の献身的な協力無くしては成されなかった物として描かれている。
しかしながら実際には親族が自ら次々と実験体に名乗り出ており、実母や妻に限った話ではない。あくまで本作は小説であり、映画版を含めて、実母と妻の役割と美談を強調した創作である。
ただし、青洲の妻・加恵は、中世以来の紀伊の名家である妹背家(その屋敷は紀伊藩主が参勤交代の際の第一番の宿所に指定されている)の出であり、青洲としてはむしろ妻の実家に遠慮しないといけない立場であった。当時の社会制度上は妻が夫に反しては生きていけなかったため、加恵は協力を断れない状況に追い込まれたというのは、有り得ない話である。(Wikipediaより)

![]()
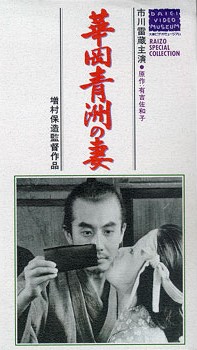



![]()