|
発言 ■ 残酷作戦 -63 ■ ある助監督から
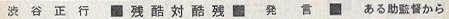
同様に、『宮本武蔵』の、首がぶっとび血がぶっとび血がふき出る<残酷な>ショットも、この作品にとって重要なショットである。般若坂の殺し合いの光景は誠に凄惨であるが、武蔵はこの時、殺人という血なまぐさいスリルに、完全に動物に還元し得た精神状態を露骨にその表情にあらわして、大刀を抜くや剣林の真只中へ飛びこんでゆく。人間武蔵などという甘ったるい粉飾をかなぐり捨てて、眼の前の殺人者共を自らの手で叩き斬ることだけに全精神を凝集し、斗争の権化と化しさった武蔵は、この一瞬によって始めて現代と接点を持った英雄として定着される。斬らねばならぬものがある、だとしたら先ずこれを叩ッ斬れ、全てはそれからだ、かくて武蔵は斬りまくる、首が飛んで血がふき出る。残酷だ、だが、そんなものに構っていたら、こちらが敗北する。残酷であろうとなかろうと必要なのは敵を粉砕することだ。粉砕の手段に良いも悪いもあるものか!だから、武蔵はお構いなしに斬りつづけてゆく。こうして首が飛び血がふき出るショットは、是非とも必要なショットだった訳である。
これらの作品にあっては、所謂<残酷描写>なるものが不可欠且つ重要な描写として認められるのだが、多くの作品が<残酷描写>の価値を厳密に考察しようとしていないのは誠に残念至極なことである。肉体を思いもかけなかった方法で破壊するという事自体、何もサドを引用する迄もなく非常にオモシロイ事だと思うのだが。
しかしながら、時代劇という特殊なジャンルに於て、最も戦慄すべき残酷さとしてわれわれが意識しなければならぬのは、決してこのような肉体的加虐さにあるのではあるまい。封建制度という、社会機構の上からも個人が完全に自己発現の場を封じられた状況そのものこそ、最も残酷なるものとしてとらえる必要がある。そうした意味に於て加藤泰の『丹下左膳』は極めてすぐれた作品である。
ここに登場する左膳は、もはや従来の荒唐無稽なチャンバラ劇のヒーローとしてのではなく、自分を体制側の一員であると自認し、その中でよりよい地位を得んがために片目を失い、更に片腕を失い、しかも結局体制の外へはじき出される誠に残酷なウンメイに弄ばれる哀れな敗残者として描かれる。又、櫛巻お藤さんも、惚れた男には只ベタベタと肉体的接触を果敢に行うことによって、その愛情を獲得出来ると盲目的に信じ、正に長屋のオカミさん的バイタリティを唯一の行動推進力として、エネルギッシュに行動するが、その結果獲得出来るものは、哀れな敗残者の肉体的形骸のみでしかないというのも、これ又、可哀想さを通りこして残酷な一つである。
だが、時代の持つ残酷さを最も苛烈な形で浴びせられ、その中で精一杯の主体的抵抗を試みながら、尚かつ、敗北せねばならなかった人間として登場するのは、桜町弘子扮する道場主の娘弥生である。彼女が乾雲坤龍なる名刀を捜し求める時、左膳のようなフェティシズムは露ほどもないが尚、その執念の凄まじさに於て左膳を遥かに上まわるものをもつのは、彼女にとって名刀奪回に執念を賭けること自体の中に、自己を取りまく閉鎖されきった非人間的状況をつき破るための脱出穴を見い出そうとする、鮮烈な志向が存在しているからである。
男姿に身を落して迄、自我を貫き通そうとするこの弥生は、もはや従来のタイプ化された時代劇の中の女の如く、しおらしく忍び泣きし、情緒に訴えて他から救済を待つ、というような甘っちょろさとは完全に無縁な存在として現われるが、にも拘らず、最後に名刀をとり戻すことによって彼女の得るものは、再び閉鎖された状況への復帰でしかない。彼女はインサイドにいながら、永遠のアウトサイダーとして生きつづけねばならないのだ。如何なる人間の意志も願望も、閉鎖された状況の中でのカラマワリに終らしめてしまうこの非人間性こそ、残酷の極致である。そして、これこそ、現代のわれわれの置かれている状況と余りに酷似しているのではあるまいか - 。
この『丹下左膳』は、だから、残酷映画の筆頭にあげられねばならぬ作品である。(余計な事だが、この桜町弘子という女優はすぐれた女優である。安っぽい涙に頼らずして、自らの意志で生き抜く力を持った女を立派に表現出来る、稀有の女優の一人であるから。)最後に、この世に於ける最も残酷な事の一つは、企業という名目の下に作家の主体性を抹殺し、没個性的な次元でしか映画をつくらせまいとするある種の経営者の存在することである。かくて映画は、益々堕落し衰亡してゆく、残酷な、余りに残酷な話である。 |