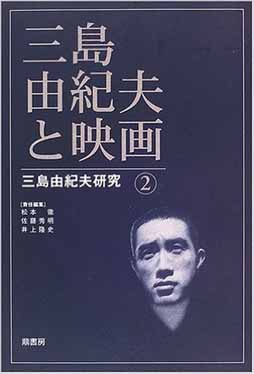
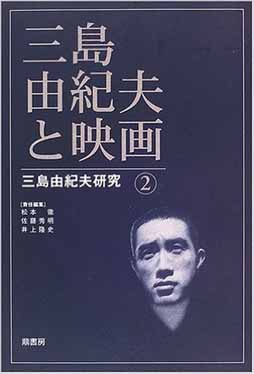
市川雷蔵の「微笑」 - 三島原作映画の市川雷蔵 -
2 『剣』
映画『剣』は昭和三十九(1964)年三月に公開された。小説は前年の十月に「新潮」に掲載されたので、小説発表から映画化までわずか五ヶ月である。雑誌に掲載された小説を雷蔵が読んで、自ら映画化したいと希望した作品である。
『炎上』以来、雷蔵が『からっ風野郎』撮影中の三島を陣中見舞いするなど交流を深めた二人だが、『剣』の映画化に際し、こんなエピソードもある。
昭和三十九年一月四日。午前四時四十五分。厳寒の早朝、目白にある学習院大学剣道道場に、三島由紀夫、市川雷蔵、舟橋和郎、藤井たちは集合した。かつて学習院長乃木将軍時代の面影が残る道場で、学生たちの寒稽古を見学したいという雷蔵のたっての希望と、この映画に賭ける雷蔵の熱き思いを汲んだ三島さんが、その機会を作って下さったのである。([藤井浩明寄稿文]「雷蔵の挑戦」DVD『剣』角川映画、2004年9月24日)
年明けてすぐ、午前四時の寒稽古見学、多忙を極める二人がここまでするのは、作品への情熱、そして、三島が雷蔵を本物の俳優だと認め、期待していたからだろう。
『剣』はTVドラマとしても映像化されているが、三島はそのドラマと映画を比較した感想も日記に書いている。
加藤剛の主役は、みごとな端然たるヒーローだが、映画の主役の雷蔵に比べると、或るはかなさが欠けている。これはこの役の大事な要素だ。(「TV 「剣」金曜日」「週刊新潮」昭和三十九年五月二十五日号 <週間日記>抜粋)
雷蔵は、次郎の正しさ強さ、「はかなさ」を見事に表現した。映画『剣』に関して「ここでは雷蔵が三島の分身ではないかと思わせられるほどだった」という感想もあるほど、雷蔵は三島の理想を体現することに成功している。
ところで、市川雷蔵が、勝新太郎や中村(萬屋)錦之助と良きライバル関係にあったことはよく知られている。特に雷蔵と錦之助はお互い対抗心に燃えていたようだ。もちろんワイドショーネタになるような、陰湿なライバル関係ではない。同じ道を志す者同士、切磋琢磨することで、雷蔵は映画俳優としてのアイデンティティーを確立していったと言える。だからこそ雷蔵にしか演じられない溝口(『炎上』)や机龍之助(『大菩薩峠』)などが誕生したのである。
さらに言えば、雷蔵が『剣』の国分次郎を演じたのは、もう一人の同時代俳優、石原裕次郎を意識してのことだったかもしれない。時代劇で映画デビューをした雷蔵に対して、石原裕次郎は兄慎太郎の原作映画『太陽の季節』(昭和三十一年)に脇役出演し、同年の『狂った果実』で主演デビュー。「太陽族」と言われた戦後派青年の象徴的存在だった。しかし、同じ戦後派の国分次郎は、
カンニングすること、いろんな規則から一寸足を出すこと、友だちとの貸借をルーズにすること、そういうものが若さと考えられているのは本当に変なことだ。強く正しい者になるか、自殺するか、二つに一つなのだ。(その二)
という反時代的な生き方をしている青年だ。雷蔵は、この国分次郎を演じることで「市川雷蔵」という俳優をアイデンティファイするという意図もあったのではないだろうか。
雷蔵は、俳優「市川雷蔵」のアイデンティティーを反時代的な美に求めていたように思う。それは、市川崑監督が「若いくせに妙にクラッシックなところがあって、そのくせ強情なんですよ」と言ったように、雷蔵の生来の性質だったかもしれない。また、『剣』で原作にはないヒロイン役を演じた藤由紀子は「たしかに、雷蔵さんは誤解されやすい人です。人にこびるということを知らない方のようです」と語っているが、この特徴は次郎にも当てはまるものである。
雷蔵は三島作品によって自己を表現することが出来た。自分を思う存分表現出来る作品に恵まれなかった勝新太郎に比べると、雷蔵の俳優人生にとって三島の作品は、かけがえのない存在であっただろう。