
源氏物語・浮舟

1957年4月30日(火)公開/1時間58分大映京都/カラースタンダード
| 製作 | 永田雅一 |
| 企画 | 辻久一 |
| 監督 | 衣笠貞之助 |
| 原作 | 北条秀司 |
| 脚本 | 八尋不二・衣笠貞之助 |
| 撮影 | 竹村康和 |
| 美術 | 山田伸吉・太田誠一 |
| 照明 | 加藤庄之丞 |
| 録音 | 大谷巌 |
| 音楽 | 斎藤一郎 |
| 助監督 | 西沢利治 |
| スチール | 小牧照 |
| 出演 | 長谷川一夫(光源氏の嫡子・薫の君)、山本富士子(中の君の妹・浮舟)、音羽信子(匂の宮の北の方・中の君)、阿井美千子(右近の北の方・早蕨)、浦路洋子(皇女・二の宮)、中村玉緒(浮舟の侍女・侍従)、三益愛子(浮舟の母)、柳永二郎(蔵人所別当・白藤の大臣)、浪花千栄子(薫の邸の女房)、中村雁治郎(帝)、夏目俊二(右近小納言)、山路義人(匂宮の供人)、橘公子(山路) |
| 惹句 | 『その心は薫の君の面影を慕いて!野性の肌は女のよろこびを求めて・・・・』『優しく頬にささやくは薫の君、激しく官能を誘うは匂宮・・・女の本当のよろこびは、心と心ではなく、体こそあるものだろうか・・・』『心に薫の君を慕いながら、身は匂宮の快楽の手に酔う、女の体の悲しさに泣く浮舟あわれ!』 |
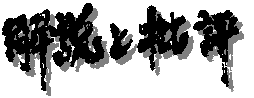

源氏物語「宇治十帖」に登場する浮舟をヒロインにした北条秀司の同名戯曲の映画化。
(←クリックすると“源氏物語千年紀 ”「浮舟」へ)
心は薫の君を慕いつつ 身は匂宮にひかれゆく 哀しきは女の性か! [解 説]
「源氏物語」はいうまでもなく平安朝時代の閨秀作家紫式部の筆になる大ロマンで、日本古典文学の最高峰といわれるもの。これが同じ大映で昭和二十六年、吉村公三郎監督の『源氏物語』(長谷川・京・乙羽主演)として映画化されるや、俄然ヒットし日本映画で最大の興行収入を挙げ、その年の社会に“源氏ブーム”を作った。
今度の『源氏物語・浮舟』は総天然色の色彩映画。世界にユニークな我が王朝文学の美しい建物・調度・衣裳・風俗が大映カラーの色彩で初めて、スクリーン一杯に描かれる。
内容も原典のうち続篇にあたる「宇治十帖」に登場する浮舟という女性をヒロインにした北条秀司の同名戯曲を原作とするだけに、前作とはまったく別な新しいもの。前作で光源氏になった長谷川一夫は、今度はその子供である薫の君になり、女主人公浮舟には山本富士子がなる。さらに皇子匂の宮には市川雷蔵、前作で紫の上になった乙羽信子は今度は匂の宮の北の方中の宮、浮舟の母中将には三益愛子、帝には中村鴈治郎その他、阿井美千子、浦路洋子、中村玉緒、夏目俊二、柳永二郎、浪花千栄子らが出演する。
故池田亀鑑氏「源氏物語大成」八巻も完成しそれが文化賞を受けた時でもあり、『地獄門』でアカデミー賞をとった名匠衣笠貞之助が情熱を傾けて作るこの芸術大作が再び“源氏ブーム”をまき起こすか大きな期待が寄せられる。
王朝映画撮影の苦心あれこれ
- ラブシインも十二単衣で身動きならぬ
眉毛を剃り落したり、牛車を揺ったり -
いわゆる“王朝もの映画”とりわけカラー作品となると、海外でも多くの讃歎者を持つほど、そのケンラン優雅の美しさで有名。この大映京都で目下撮影中の『源氏物語・浮舟』も、もちろんその例外でないどころか、衣笠貞之助監督は物語の時代からいっても、内容から云っても、この作品は今までの最も美しい色彩映画になるだろうとその抱負を語っているほどだ。
雅やかな宮殿・庭苑・調度・衣裳と、洗練された色彩を背景にくりひろげる優美な恋物語は、エレガント時代にピッタリの、王朝映画決定版として期待が寄せられる。
ところで、このエレガント映画も、特殊な題材を扱うだけにスタッフの苦労は一しお。以下そういった裏の苦心を「浮舟」のセットに拾ってみよう。
まず主演する俳優の衣裳が大変。女は何枚も着物を重ね、最後に十二単衣と呼ばれる厚ぼったいうちかけを着るのだから、完全武装?すると一寸も身動きならない有様。
おまけに背中から足下につくほどのおすべらかしの長い黒髪がぶら下がる。男も、それに順じたものものしい着付けが必要なことは同然。男はまた頭にいつも冠をつけていなければならない。このため薫の君に扮する長谷川一夫などは衣裳着付けはセットにゴザ・鏡を持込んでやっているほど。
さきに撮影された“宇治の山荘・廂の間”シインは、ヒロイン浮舟の山本富士子と薫の君の長谷川のラブシインだったが「浮舟のこの体をあなた様のものにしていただきたいのです。そして身も心もあなた様のお体にはっきり縛りつけてほしいのです」と云い放って、山本が長谷川の膝にとりすがり、抱擁を迫る甘美な雰囲気ただようクライマックス シインの本番で、山本の十二単衣の袖が傍らに置いた酒盃に触れ、ガタンと無粋な音を立てたため、このカットは撮り直し。
その他、この当時の貴族は男女を問わず、眉毛を剃り落としたいわゆる高眉で、また歯は黒く染めていたので、長谷川・山本・雷蔵・音羽信子・中村玉緒・中村鴈治郎・浦路洋子・三益愛子・夏目俊二ら衣笠組出演者の大半が眉を剃り落とし、お歯黒(もちろん本式ではない)をやっているのも陰の苦労の一つだろう。
また物語中にしばしば出てくるのだが、当時の自家用車?であった牛車の内部の場面では、のどかな牛車らしい震動感を出すため、出演の長谷川・山本・雷蔵らを乗せ、カメラ側の仕切りを外して内部をバラした檳榔毛の車を、助監督以下の裏方の面々数人が、外から手で支え、いともデリケートに慎重にゆするなどから、文献を探し歩いての時代考証まで、裏方のスタッフの苦労はつきない。(公開当時のパンフレットより)
[ 略 筋 ]
きらびやかな平安の都に東国から二人の母娘、常陸の介の妻中将と、中将がいまは亡き都の貴族八の宮との間に生んだ少女浮舟がやって来た。−浮舟にとっては異母姉にあたる八の宮の姫大君の葬いにきたのだ。丘の上の墓所で、母娘は大君を愛していた薫の君に出遭った。薫の君は浮舟の野生美もさることながら、その顔立ちがあまりにも生前の大君と瓜二つなので驚くが、いつしかそれは彼女への深い思慕に変った。
浮舟母娘は大君の妹の中の君が嫁いでいる匂の宮の館に滞在しているが、匂の宮は清純な愛を信じる薫の君とは反対に次から次へと女を愛する快楽主義者であった。ある日、薫の君の案内で洛中の名所をめぐりまわった浮舟は、朱雀門の池の端で薫の君から想いを打ち明けられたが、彼女は踵をかえして走り去った。その数刻後、彼女は清冷院の東庭で匂の宮に出会った。匂の宮は強引に彼女を抱き寄せたが、彼女は彼を突き飛ばす。
−時が流れて、浮舟は居を宇治の元の八の宮の山荘に移し、いまは薫の君の深い愛を信じ、毎日彼の訪れを心待ちに待っている。その間も匂の宮は何かと浮舟を誘惑しようとした。
ある日、匂の宮は浮舟に薫の君が帝の勅諚で皇女二の宮と結婚しなければならなくなったと囁き、彼女が動揺するのにつけ込んで、その夜無理矢理に彼女の体を抱いた。だが、浮舟の理性が崩れ去った頃、薫の君は地位も名誉もなげうって、浮舟の愛のみを信じ、勅諚に反して彼女の許へ牛車を急がせていたのだ。しかし、薫の君は全てを知って絶望に立ちすくんだ。
勝ち誇った匂の宮は浮舟を都に連れて行こうとする。と、彼女は山荘のどこにもいない。薫の君は浮舟の死を直感した。たとえ、どのようなことがあっても、二人は心の底で結びついていたのだ。山荘の女房たちの浮舟を求める声を遠くに、いつか薫の君は宇治川のほとりに出た。夜明けの霧が川面に垂れこめている。その時、白い被衣が川底に没して行くのがわかった。“浮舟ッ”薫の君は悲痛な叫びをあげ、一歩、二歩思わず川の中に身を進めていた。(キネマ旬報より)
源氏物語 浮舟 瓜生 忠夫
「源氏物語」とは申せ、原典の映画化を期待すると面食う。これは北条秀司原作戯曲の映画化。正確に申せば、もはや「源氏物語」ではござらぬ。「源氏物語」は宣伝用の謳い文句でござる。東から京へ上った田舎娘「浮舟」は、長く坐っていると足がしびれてゴンとひっくり返る女。よくもまあゴテゴテと行動の自由を奪う着物を召していると思うが、足のシビレがお得意な現代娘には安直に理解できよう。
その浮舟と、薫の君(光源氏の嫡男)が恋におちた。薫の君は、王朝男に似合わず、プラトニック・ラブの信奉者で、せっかく宇治まで彼女を訪れても肉体関係をつけない。浮舟は「あなたのものにして」とか何とかアタフタする。時々ふッと、薫は不能者で、浮舟は多淫女のような気がする。
二人の間に、色事師、匂宮がわりこむ、匂宮は術策を弄し、浮舟と彼女の母をだまして、ある夜、ほとんど暴力で彼女をものにする。犯されながら、彼女は肉欲の悦びに夢中になった、それが女の本性だと宮は語るのだが、これはこれは春本好みの言い草だ。わたしは、心理的にも肉体的にも、浮舟はよほど特殊な女であるとの印象しか受けなかった。だから、後朝、薫の君が現われて一切を知り、浮舟は薫に、わたしのほんとうに愛する人はあなただ、なんていうのがチグハグで、むしろ不潔である。男の肉体におぼれる浮舟の入水自殺も必然性がない。いっそのこと、大いに肉の悦びを謳歌して、男から男へ渡り歩く太陽族娘にすればよかった。そうすれば薫が阿呆に見えて喜劇になる。
この作品は、風俗は王朝だが、権威権力を併せもつ匂宮というヤクザの親分が、純情な子分大納言の女を横取りした、というヤクザ映画である。ふつうならば、掟に従順な子分が、親分に反抗して起ち上り、親分をやっつけることで終るのだが、この作品では、子分薫の君はやられ放しというのだから後味が悪くなる。観ている方の義憤は水をかけられたまま、というわけだ。いかに王朝が舞台でも、これでは大衆性がない。
ものものしくぜいたくな風俗を色彩で描く−それがこの映画の狙いであろうが、衣裳が行動の自由を失わせるというだけでなく、画面のテンポそのものがのろいので、色彩もくどくなり一向に効果を発揮しない。衣笠監督らしい巧みさは、匂宮が浮舟のもとへ急ぐとき、路傍の草を牛車がふみしだいて彼女の運命を暗示するところに現われるが、まアその程度。総体にたいくつである。
長谷川一夫の薫の君に、政務に練達な大納言の風格がなく気味の悪い男女にみえるのは、この映画を特につまらなくした。たとえ情痴映画であるにしても、権力機構の中の重い人物は、その重さをしっかり掴んで演じるべきである。
なお、王朝時代の情事生活を描こうと思うならば、当時の権力争い、政略結婚、結婚についての観念と習慣をどこかで明らかにしておかないと、今の人にはチンプンカンプンだとつけ加えておく。
興行価値: 豪華キャストによる天然色映画ではあるが、王朝時代の風俗習慣、そしてニュアンスは果たして今の若い人の体質に合うかどうかは疑問である。しかも恋愛を描いただけにその売り方も大分苦労はする。キャストの豪華さを表面にしたほうが無難。(キネマ旬報より)
日スポ東京04/27/57より
デイリースポーツ04/22/57より
サンケイスポーツ04/23/57より
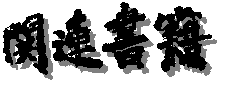

![]()



![]()