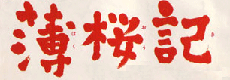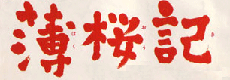五味康祐の原作を、伊藤大輔がシナリオに仕上げて、森一生監督がメガホンをにぎる大映京都『薄桜記』は勝新太郎、市川雷蔵両看板スターにSKD出身の新人真城千都世をからませて、このほどクランク・インした。勝新太郎扮する中山安兵衛の回想にはじまるこの映画は、赤穂浪士のアダ討ちを背景に、相異なる二つの道をゆく二人の武士、丹下典膳(雷蔵)と中山安兵衛の友情と運命を、千春(真城)という絶世の美人にまつわる因縁話の中に感動的に描く、格調ある時代劇である。
森一生監督は「私の恩師である伊藤大輔監督のシナリオは、深みと格調のある立派な本になっているので、大いに張り切っている。大映が一本立になって、監督にとっても、これからは、一本々々が待ったなしの勝負なので、いい本が当たったことを喜んでいる。伊藤先生とも、いろいろ相談したがこんどは、一つ思い切り変わった手法を試みてみた。例えば、脚本を見て、まず常識的なコンテを書いてみて、これをもとに、アップのところをロングに、ロングのところをアップにと逆にもっていってみようかと考えたりしている。 立回りにも従来のチャンバラ臭をやめ、本物の真剣を使って、重味のある立回りにしてみたい。本物を持てば、竹光のときとちがって、俳優さんの動きもおのずから変わってくるだろうし、真剣勝負のリアルな迫力も出るだろう・・・」とファイトをもやしていた。
ところで、このほど行われた宣伝スチール撮影に、安兵衛、典膳の、それぞれ浪人時代の扮装で現われた勝、雷蔵の二人は、勝が、ムシリのカツラに黒紋付きの着流し、赤ザヤの大小という豪放なスタイル。一方の雷蔵も、同じムシリのカツラ、横じまの落ち着いたキモノのソデに失った片腕をかくした作中後半の“秋の大気が草木を枯らす”というシナリオに書かれたすご味のある、それでいて静かに沈殿していくようなふんいきのスタイル。
二人の本格的共演は『花頭巾』以来で、まる三年目になるが、こんどの本では、勝、雷蔵の比重を全くの五分五分に書き分けてあるので顔合せのシーンは割に少ないが、二人の腕試しという意味でも興味が持たれる映画である。 勝は「トップ・シーンから討入り姿の僕のナレーションで始まるが、このナレーション入りの回想シーンが随分多いので、いろいろ調子を変えて、単なるナレーションで終らせたくない。従来の安兵衛といえば、ノンベ安だったが、こんどはノンベ安とは違うので、その点工夫の余地がある。監督さんは僕と雷ちゃんを明暗に分けて明を僕の安兵衛にあてはめているので、むずかしいが型破りの安兵衛にしてみたい・・・」と、よきライバルとの共演作を得て、元気いっぱいだった。
また丹下典膳という暗の人物を演じる雷ちゃん、「前半を甘い二枚目の若さまの感じで、後半、妻の千春がおかされ、それがもとで自分の片腕を失ってからの典膳をニヒルで冷徹な男として出したい。扮装には、あまりたよらず、これを思い切り心理的に演じてみるつもりだ・・・」と、抱負を語り、監督をはさんだ二人は、お互いに“演技では雷ちゃんだ” “イヤ、勝ちゃんには負けるよ”とファイトを秘めて譲り合っていた・・・。
デイリースポーツ大阪版 10/12/59m |