
剣

1964年3月14日(土)公開/1時間35分大映京都/白黒シネマスコープ
併映:「座頭市千両首」(池広一夫/勝新太郎・坪内ミキ子)
| 企画 | 藤井浩明・財前定生 |
| 監督 | 三隅研次 |
| 原作 | 三島由紀夫 |
| 脚本 | 舟橋和郎 |
| 撮影 | 牧浦地志 |
| 美術 | 内藤昭 |
| 照明 | 山下礼二郎 |
| 録音 | 奥村雅弘 |
| 音楽 | 池野成 |
| 助監督 | 友枝稔議 |
| スチール | 藤岡輝夫 |
| 出演 | 藤由紀子(伊丹恵理)、川津祐介(賀川)、長谷川明男(壬生)、河野秋武(木内)、紺野ユカ(藤代滋子)、小桜純子(壬生早苗)、角梨枝子(国分ひろ子)、稲葉義男(国分誠一郎)、高見国一(多田) |
| 惹句 | 『彼はアンチ現代だ!とぎすまされた世界に命をかけた異様な現代青年!』『この汗の中に生きがいがある!現代の誘惑を叩きつぶしてひたぶるに命を燃やす異常な青年!』『誘惑の風を斬って剣の心に生命を賭けた一学徒の異常な生涯を描く!』 |
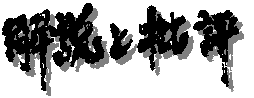

(画:高橋豊子/字:三輪雷童)
『強く正しくあれ、さもなくば死・・・。軽薄な現代に、純粋に生きようとした一人の青年の物語。』
市川雷蔵の現代劇
三島由紀夫の「剣」を映画化
64年の正月映画『新・忍びの者』『眠狂四郎勝負』と好調な主演ぶりを見せている市川雷蔵は、ファンも知っての通り、お正月は東京の日生劇場へひさびさの舞台出演で、これも好評活躍中であるが、この舞台を二十七日で打ち上げにしたあと、新春第一回の映画出演は、三隅研次監督、舟橋和郎脚本、三島由紀夫原作の『剣』と決定している。
これはある大学の剣道部の主将が剣道ひと筋に生きる、孤高な青年の姿を描くもので、主人公国分に心酔する下級生や、反対の立場をとる学生との反目とか、青春のなやみなどが、剣道部の合宿生活のなかにとりあげられ、雷蔵にとっては『炎上』以来の現代ものとなる。なにしろ二月の撮影に真夏のシーンを撮影したり、本も読まずに剣道ばかりやっている、風変りな人物をどうこなすか、ヒーローに扮する当人はもとより、大映でもいまから力こぶを入れている。

写真は打合せ中の、三隅監督(左)と、舟橋シナリオライター(右)(近代映画64年3月号より)
 撮影スナップ
撮影スナップ



あらすじ 国分次郎(市川雷蔵)は、東和大学の剣道部主将になった。純粋一途に剣の世界に打ちこむ国分は、部員にきびしくのぞんだ。新部員の壬生(長谷川明男)の目には神のようにうつり、心酔した。 国分は女をからかう学生をこらしめ、自殺者にも冷たい批判をくだした。副将格の賀川(川津祐介)は、適当に遊び適当に学ぶタイプ。息苦しい国分のやり方についてゆけない。部費かせぎのアルバイトで賀川はタバコを吸い、デパートで叱責を食う。国分は賀川に四十分正座の制裁を加えた。 賀川は学友の恵理(藤由紀子)に国分の誘惑をそそのかす。恵理は国分に近づき、その結果国分もやっぱり人間だったと賀川に報告した。賀川は勝ったと思う。 夏の強化合宿が始まった。国分は鬼のような指導を強行した。しかし賀川はスキを見て部員をあおり、皆で禁制の水泳をやった。崇拝者の壬生までも・・・。 短評 この全員の規則破りは、国分の信条を根本から崩壊させた。合宿納会の晩、彼は自殺する。それは死なねばならぬほどの傷手だろうか、と問い返す人も多かろう。とくに若い現代の人間には疑念がわくことだろう。だが人間の行動、ことに自殺行為には、第三者的には解しがたい例は多い。ほとんど死に値する理由は見つけられないのに、自殺はたえない。それに国分次郎の、「責任を重んじ、みずからにも他にもきびしい純粋さ」という日本的美徳を代表する、いわば古武士的人間像なのだ。それが主体性をもつ現代人には通用せず、もろくも敗れるという、一種の図式を形成したのだった。国分次郎を心理的に探ることより、日本的典型として見るほうに意味がある。その死もうなずけるというものだ。 国分次郎の敗北というヒューマン・ドキュメント(原作:三島由紀夫)を、三隅研次演出はいささか同情的に見ている。国分の死後、江利に「かれは自分にふれなかった」と真実を語らせ、賀川に、ついに国分に勝てなかったと嘆じさせ、かれの死をパセティックにしたあたり、ヒューマンに傾きすぎたきらいもある。国分の青春は厳粛だったと見えさえする。しかしどう見ようと、敗北の事実と記録に変わりはない。感傷のあまさを加味してもなお、主題を貫き通した演出は相当に評価されるべきだ。雷蔵も過不足のない好技、川津は最近の卓技。二人の青年によって、現代の青春に方向を求めた意欲も重視したい。力作。(映画評論家:君島逸平
西スポ 03/23/64より) |
■解説■
この『剣』は、鬼才、三島由紀夫が、書き下ろした傑作小説に、市川雷蔵が三隅研次監督の演出を得て野心満々に取組む異色文芸大作です。
大学生でありながらあまり本も読まず。遊び事には目もくれず、ただ、ひたすら、剣の道に全身全霊を打ち込む主人公、国分次郎。未来の幸福を思い悩むことなく、ただ、純粋な剣の世界のみを信じるこの青年は、打算的で適当にお洒落で、美人の細君をもらって郊外に住み、退職金の計算を間違いなくやるといった周囲の学生たちとは、あまりに異なった存在です。
苦しい事には微笑を浮かべてじっと堪え忍び、強く正しく生きる事だけを望み東和大学剣道部の主将として、鬼神のように君臨するこの主人公は、当然周囲の人間と様々の波乱をひき起こします。精神と肉体の練磨を同時に要求する剣に托して、鬼才三島が、幸福を求めるあまり理想を見失うといった落し穴に陥っている現代の若い世代に鋭く挑んだこの作品は、賛否両論の轟々たる嵐を現在、マスコミ界にまき起こしています。
キャストは、主人公国分次郎の市川雷蔵の他、剣を愛しながらも、適当に遊び、適当に学ぶタイプで、国分を認めながらもその堅苦しい考えについていけず批判的な立場をとる三段の部員、賀川に川津祐介、国分に青年の理想像を見出し、彼を神の如く尊敬する新人部員壬生に長谷川明男、会社の経営者でありながら、世俗のわずらわしさよりも、剣の純粋さをより愛する剣道部の監督、木内に河野秋武、それに、原作にない登場人物として、学内ナンバーワンの美人学生に藤由紀子という絶好の適役を得た四人の重要な副人物が登場。また他に、稲葉義男、角梨枝子、紺野ユカ、小桜純子、堀川真智子、風間圭次郎、矢島陽太郎、高見国一といった多彩なメンバーが顔をそろえています。
いよいよ今年は、本格的な活躍が期待される三隅研次監督は、この意欲作に大いに作家精神を燃やしていますが華麗な文体を特徴の三島文学だけに、その映画化には細心の注意を払い、新鋭牧浦地志カメラマンとのコンビで、慎重に撮影をすすめています。( 公開当時のプレスシートNo. 1152より )
■物語■
国分次郎は、少年の頃、太陽とにらめっこをしてその本質を見たと思った。その時以来、彼は強く正しく生きる事を自らの課題にした。そうした彼には雑念を払って純粋な力が純粋に作用する剣の世界は、この上ないものだった。
東和大学の剣道部にとって、主将である国分の存在は、はかり知れぬ程大きなものだった。勉強にも、遊び事にも一切目もくれず、ひたすら、純粋に剣の世界に己を打ち込む国分は、部員一同にも、自分の行き方で、厳しく臨んだ。打算的で、お洒落で、結婚すれば家庭第一主義で退職金の計算をするといったタイプがほとんどの他の学生とくらべ、未来を思い悩むことなく、剣に全存在を賭ける国分の姿は、新人部員の壬生の目に、神の如くうつった。壬生は、偶像のように国分を尊敬し、すべて、彼の生き方に学ぼうとした。
“みんな未来の幸福を考えすぎる。その為に生きる目的を失うんだ”と国分は壬生に語るのだった。ある日の稽古の帰り、国分に連れられて下級生の部員と共に近所の喫茶店に入った壬生は、便所の入口に陣取り、出て来る女性に下卑な野次を飛ばす学生達に憤慨したが、手を出すことが出来なかった。国分は立上がり、彼らを便所の中に押し込めた。屈辱に顔をこわばらせて出て来る彼らに国分にならい壬生達は嘲笑を浴びせた。壬生の国分に対する気持ちは、崇拝にまで高まった。
だが、国分の同級生で三段の賀川は、剣を愛することは同じでも、適当に遊び、適当に学ぶというタイプで、あまりにも息苦しい国分の考え方について行けないものを感じていた。剣道部の監督、木内は、ある会社の経営者だが、矛盾の多い実社会よりも、誰の目にも明らかな勝負だけで片がつく剣の世界をより愛する男だった。彼は、部員達を深く愛し、賀川も彼にだけは、国分の生き方に対する批評を誤解を恐れずに訴えることが出来た。
例年のように、強化合宿の費用を稼ぎ出す為、木内監督の紹介で、剣道部員全員は、あるデパートにアルバイトに出向いた。ところが、ある日、可燃性の商品を置いた部屋で、賀川が煙草を喫ったことから、デパート側の叱責を食った。国分は、全員を道場に集め、賀川を四十分間正座の制裁に処した。賀川は、身じろぎもせず、歯を食いしばって、この処分に甘んじた。
苦しい時、無意味なことに堪える時国分は、きまって、微笑を浮かべるだけだったが、賀川には、そんな国分の男らしさがたまらなかった。あるダンスパーティで、賀川は、学内ナンバーワンの美人の文学部の伊丹恵理に会い彼女の自尊心に訴え、国分を誘惑するよう、そそのかした。ある日、裏山で太陽に向かい合っていた国分は、構内に入り込んで、鳩を空気銃で射った無頼の若者に対決し竹刀の一撃で、傷ついた鳩を取戻した。これを見ていた恵理は国分に強い関心を抱いた。
賀川は、自分のアパートに恵理を待たせ、自分が会いたいと偽って、国分を呼び出した。後刻、恵理に会った賀川は、彼女の口から国分が肉体を求めたことを知った。初めて国分の人間的な弱みを知った賀川は、これで、国分に勝てると自信を持った。
しかし、その後も、剣に取組む国分の態度は変らなかった。全国大会の優勝を目指し、夏の強化合宿が始った。ある港町の山寺に陣取り、連日、早朝から猛烈なトレーニングが続けられた。ランニング、腕立て伏せ、素振り、早素振り、へとへとに疲れ果てぶっ倒れる下級生が続出しても、国分は手をゆるめなかった。彼は、率先して鬼神のような指導を続けた。
後二日で納会という日に、木内監督が、来るという知らせがあり、国分は、副将の村田と共に、港まで迎えに出た。本堂で、のんびり昼休み中の部員達にまじり、賀川は、厳しい訓練をやり通した自負と共に、よく皆をここまで引っ張ってきた国分の統率力に感嘆したが、それと同時に、あくまでも強い彼の存在に、故知れぬ反撥を感じた。
賀川は部員達を剣道部に厳禁されている水泳に誘った。賀川は、禁を破る事をためらう部員に、国分が恵理の肉体を求めた事を明らかにした。意外な事実を知って、部員達は実行に踏み切った。帰ってきた国分と木内監督は、頭からびしょぬれの部員達と出くわした。唯一人残って海に入らなかった壬生も、パンツ一枚になって、仲間達の間にまぎれ込んでいた。提案者の賀川は、木内の命令で、即日帰京を命じられた。うなだれた国分の姿は、これまでにない敗北的なものに壬生には思えた。二人きりになった時、国分はお前も本当に行ったのかと壬生にたずねた。「はい」と嘘をついた壬生は、これで始めて国分と対等に話している自分を感じた。
ようやく、納会の日が来た。“みんな、よくやった”と国分は、初めてねぎらいの言葉を述べた。酒宴たけなわの席から、いつの間にか、国分の姿が見えなくなった。全員、八方をさがしまわった結果、林の中に、胴を着け、竹刀を抱えたまま、絶命している国分の姿が発見された・・・。
通夜の日、恵理は以前賀川に語った事実は嘘だったと告白した。( 公開当時のプレスシートNo. 1152より )


■新聞評■
純粋な若者を熱演する雷蔵『剣』、大映、1時間35分。三島由紀夫原作、舟橋和郎脚色。剣一筋に生きた大学剣道部の主将が、あまりにも純粋なるがために若い命を自らの手で断つまでの物語。
主人公のあり方にはいろいろと問題があろうが、全国大会の優勝を目標に。計画的な誘惑にも乗らず一途にトレーニングに励む姿を市川雷蔵が熱演している。時代劇と違ってがらりと線が細くみえるがそれがまたこの主人公にはうってつけだし、いい効果をあげている。たとえば、彼にまず反抗する高見国一や、たえず敵意を燃やす副将格の川津祐介などが、主人公より生き生き見えるのもそうした彼の性格のためで、一見主人公の彼が陰に回っているようだが、地味ながら着々とその人となりをなっとくさせていく。原作にはない藤由紀子の役どころも、まず無難に作中にとけこんではいるが、もうすこし学生らしく見せることはできなかったろうか。
雷蔵と川津の対照的な性格のからみ合いがおもしろいのだが、川津の一人相撲的なところが多いのはものたりない。他の出演者では、若い剣道部員の長谷川明男、監督の河野秋武が好演。三隅研次監督としては中級のでき。−朝日新聞から−
数十年前に見たときには、横長の画面を最大限に活用した三隅研次の構図が印象的だった。が、いま見直すとかなり奇怪な映画だ。原作は三島由紀夫の短篇小説。描かれる世界は、東和大学の剣道部にほぼ限定される。主人公の国分次郎は、そこで主将を務めている。 国分は原理主義者だ。純粋とか一本気とか呼ぶこともできるだろうが、自ら定めた掟に従うことに快楽を覚える体質の持ち主というほうが適切ではないか。 国分には壬生という崇拝者がいる。賀川という偽悪魔も身辺に出没する。壬生は国分に憧れ、国分になりたがる。賀川は国分を現実世界に引きずりおろしたがる。しかも彼らは、一種の小宇宙に属している。悲劇まではほんの一息だ。 というわけで、話の筋を追えば白ける。三島由紀夫の明晰さと幼さが、どちらも透けて見える。託された寓喩もやや強引で単純すぎる。 が、雷蔵の肉体が映画を脈打たせる。とくに静止したときの姿勢が素晴しい。一枚の硬い板になって眉ひとつ動かさない。背中の線も眼を惹く。スクリーンという平面のなかで、自身も平面に近づいてくる。 これは難事業だ。他の俳優の容易になせるところではない。だからこそ、三隅研次の築き上げる構図も生きてくる。平面と平面が交わると、映画は不思議な歪み方を見せる。奇怪な映画と呼んだのはそのためだ。 |
シネマ・スコープサイズの画面が、スタンダード・サイズ映画の画面の上半分をカットしたように、妙に寸足らずに見える映画である。かってある監督が、シネマスコープ・サイズの画面のことをスタンダードにくらべて「タテがセマクなった」と形容したことがある。ああこの人には、シネスコ映画は撮れないな、と思った。それを聞いた時と共通するもの足りなさを感じさせられる作品である。 自由奔放が生活のルールになっている現代にあって、厳格な規律と精神主義を強いられる唯一の場所であるかもしれない大学の剣道部という存在。この「現代の異風景」にくいさがろうというテーマは大いに面白い。ここには、「現代を舞台にした時代劇」を作り得る可能性がある。 しかし、三島由紀夫の原作のテーマを忠実にふまえて「人間の純粋性」などを持ってまわったドラマは、文学の舌たらずな引きうつしであるいわゆる文芸映画に、この作品をしてしまっている。映画に撮ることによって、新しく掘りおこされたものがないのである。 くわえて、この映画には「現代」がない。開巻当初の何分間か、これはいったい、いつの時代の大学生活をえがいたものなのかと観客を迷わせる「フィルムによってとらえた時代感覚」の喪失。 この二つが、映画『剣』を妙に寸たらずなものに見せている原因である。同じ銀座大映のスクリーンで同時に見た『座頭市千両首』が、シネマスコープ・サイズの広がりをフルに使って、痛快な「大衆的」シネマツルギーをみごとに見せていたのが、はなはだ対照的であった。興行価値:『剣』という因くありげな題名と、三島文学 - 雷蔵というコンビの妙がうけて興行価値70%台。(キネマ旬報より) |
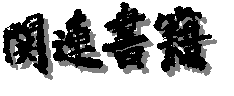
(画:中田雅喜)

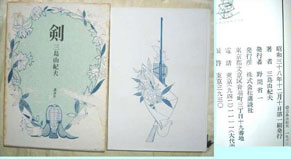
短編集『剣』は、昭和三十八年十二月(1963)に出版された。三島由紀夫三十八歳の年で、ここには九編の異色作(題名の「剣」は大学の剣道部を題材に、強く純粹に生きようとする若者の挫折を描くことで著者の美学を感じることのできる作品。その他「月」「葡萄パン」「雨の中の噴水」「苺」「帽子の花」「魔法瓶」「真珠」「切符」)が収められている。なかでもタイトル・ストリーの『剣』は、かくべつ充実した作品で、三島らしく又しても、主人公の自殺がクライマックスをなし、結末をなしているが、一種澄妙な透徹感が全体をつらぬいていて、爽やかな後味さえのこす。− 佐伯彰( 文庫判解説より )−初出、昭和三十八年十月(1963)「新潮」。講談社文庫等で読める。
詳細は、シリーズ映画、その他のシリーズ「剣三部作」参照。

![]()



![]()