|
発言 ■ 残酷作戦 -63 ■ ある助監督から
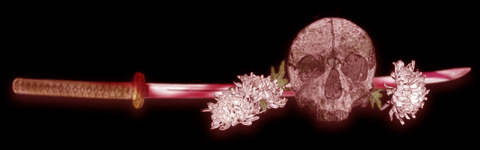
●潜行 B |
いわゆる残酷リアリズム時代劇なるものは『切腹』『椿三十郎』あたりから、ジャーナリズムにのぼって来たのであるが(製作会社の宣伝もふくめて)、その系譜は意外に古い。
映画の『斬人斬馬剣』などは題名だけでもいかにもそれらしいが、主として戦後の映画しか観ていない私にはストーリーや映画史を読む以外に知る手掛りはない。しかし - 先輩たちの話をきくと、それに類する作品はかなり多かったと推定される。この場合、残酷の意味としては映像にはっきり現れる具象的なもの(たとえば頭へオノを叩きこむ=無宿人別帖)と、内容からくるもの(たとえば人間を歪め押し潰して行く封建社会=武士道無残)とがあるが、此の両者ははからずも一つの作品の中で合致している場合が多い、それはつまり残酷だけを押し出して徹底的に具象化した作品もなく、明朗健全娯楽には残酷場面はタブーであるからだ。
中川信夫『東海道四谷怪談』をはじめとする石川義寛、加手野五郎たちの新東宝オバケ映画、今井正『夜の鼓』、溝口健二『西鶴一代女』、内田吐夢『血槍富士』、森川英太郎『武士道無残』、加藤泰『怪談お岩の亡霊』、大島渚『天草四郎時貞』、三隅研次『斬る』、小林正樹『切腹』、山本薩夫『忍びの者』と記憶をたどって行くと、それらの作品の生れる背景の共通点が意外に多いのに気が付く、中川信夫たちは量産競争脱落寸前の新東宝であり、他の作家たちも企業の枠をはみ出るか、もしくは企業でもユニークな存在の人々である(アウトサイダー的性格) - それらは企業の中において所詮異色作であり、その社の主流路線にはなりえないが、時代劇を歴史的にとらえる時、見逃すことの出来ない一つの山脈であろう(最近の大映劇を観ていると異色作が次々と現れて、残酷リアリズムの主流に近くまでのし上っている)。
●時代劇の残酷作戦 - ゲリラ隊
「時代劇は低調である」と言われている。質的にも興行的にも現代劇オンリーの東宝、日活に名をなさしめているが - 時代劇関係者の中には、この二、三年来低調であるという言葉の呪縛から負け犬根性に落ち入り、ますます自信を失い、一昔前の安全度にしがみついている現象がなきにしもあらずであろう。松竹京都は閉鎖に近いのが現状であるし、時代劇王国を誇った東映京都も、今は東京作品のギャング路線にともすれば話題をさらわれ勝ちである。
「残酷ブーム」も儚い数本の花火にすぎないかもしれない、といって、むざむざ突破口を塞ぐ必要はないだろう - 何故ならそこには虚飾をはぎとった、斬れば血の出る人間があり、人間と人間の、加害者と被害者の、あるいは被害者同志の様々な斗いのドラマが生々しく描き出せるからである。錯綜する現代社会をバックにした現代劇ではとても非現実的でみられないストーリーも、時代劇(過去)にうつし変えることによってより強烈にテーマを打ち出し、同時に観客の支持をうることは可能である。しかし生々しい人間葛藤を鮮烈に描く - といっていたずらに残酷過剰に落ち入るのはよくないと思う。たとえば、エロ写真やエロ本はいくつ見ても所詮同じことであり、吾々に新鮮な衝動をあたえることは出来ない。映倫の眼をくぐっていくら残酷場面のみを考えたところで、タカが知れているのである。(残酷を瞶める作家の眼が問題である)中川信夫『東海道四谷怪談』や三隅研次『斬る』には独得の残酷の美学と思われるショットがいくつかあった。この方向はまだまだ未踏の荒野であり、開拓し、発見する必要があるのではなかろうか。(映像における残酷の耽美主義は目下私の関心事である)
63年においても残酷リアリズム(美学派もふくめて)が時代劇の主流になることは考えられない。しかし規格品にあきて、座席に眠りかける観客へのストレートパンチとしての有効打的役割を果たす可能性は十分ありうると思う。ただし主流はあくまでも健康で人間の善意を信じ、明るく楽しくデラックスな作品であるということは申すまでもないでしょう!!
鈴木則文(1933年11月26日 - 2014年5月15日):日本の映画監督、脚本家。静岡県浜松市出身。愛称はコーブン、コーブンさん。代表作は「緋牡丹博徒シリーズ」(脚本)、「女必殺拳シリーズ」(企画・脚本)、「トラック野郎シリーズ」(監督)など。(Wekipediaより) |