
斬る

1962年7月1日(日)公開/1時間11分大映京都/カラーシネマスコープ
併映:「黒の試走車」(増村保造/田宮二郎・叶順子)
| 企画 | 宮田豊 |
| 監督 | 三隅研次 |
| 原作 | 柴田錬三郎 |
| 脚本 | 新藤兼人 |
| 撮影 | 本田省三 |
| 美術 | 内藤昭 |
| 照明 | 加藤博也 |
| 録音 | 大角正夫 |
| 音楽 | 斎藤一郎 |
| 助監督 | 辻光明 |
| 出演 | 藤村志保(山口藤子)、渚まゆみ(高倉芳尾)、万里昌代(田所佐代)、柳永二郎(松平大炊頭)、成田純一郎(田所主水)、天知茂(多田草司)、浅野進治郎(高倉信右衛門)、丹羽又三郎(千葉栄次郎)、友田輝(庄司嘉兵衛)、稲葉義男(池辺義一郎)、浜田雄史(池辺義十郎)、毛利郁子(若山) |
| 惹句 | 『梅一輪を右手にかざし、斬るでなく舞うでなく、のどをかき切る非凡の剣士』『音もなく死を呼ぶ三絃の構え!梅の小枝はのどを貫き!紅にそまって無心にゆれる!』『白刃の中を風のように走る三弦の構え!・・・うめきもたてず地上に伏す刺客の群!』 |

画:中田雅喜氏作

■解説
柴田錬三郎の問題小説をベテラン新藤兼人が脚色、市川雷蔵主演で映画化するカラー作品『斬る』は、数奇な運命をたどる多感な天才刺客の若き生涯と、六つの決斗を通じてみせる剣の醍醐味を、鬼才、三隅研次監督が鮮烈なタッチで描破する格調高い異色の文芸時代巨篇であります。
内容は出生の秘密を持つ主人公信吾が、養父と義妹の不慮の死により平和な生活を壊されるが、初めてその出生の真実を知る。以来波乱に満ちた孤独な剣客の半生が始まるが、邪剣と知りつつも、相手のノドを狙う異様な三絃の構えをあやつる彼の剣はまさに天下無敵。雷蔵得意の迫力にみちた殺陣が随所に展開され、時代劇の全魅力を画面一杯にぶつけようというもの。(公開当時のプレスシートより)


高倉信吾が、育ての親を斬って立ち退こうとする池辺親子を追いつめ、瞬時にして斬り捨てる。ふたつの死がいの前に立ちすくむ信吾の顔に勝利の喜びはなかった。暗い出生の秘密と、斬ることの宿命を背負って剣に生きる孤独な剣豪の姿を浮き彫りにした異色作品。
柴田錬三郎の原作と雷蔵の演技を、三隅研次がうまく結びつけている。伝奇的な要素を取り入れて見る人の意表をつくのも、この作品の魅力のひとつ。
斬る−そのものズバリの題名をもつこの作品は時代小説に独特の作風をもって話題を提供している柴田錬三郎の原作を、ベテラン・シナリオライターの新藤兼人が脚色、『釈迦』ですっかり演出に巾の出て来た三隅研次監督がメガホンをにぎり、水もしたたるような美剣士ぶりを見せる市川雷蔵が主演するという、大映時代劇最高のスタッフ・キャストである。
ストーリーは出生の秘密を持つ主人公信吾が養父と義妹の不慮の死により平和な生活を壊されるが、それによりはじめてその出生の真実を知る。そしてそれ以来、信吾の波乱に満ちた孤独な剣客の半生がはじまるが、邪剣と知りつつも相手のノドを狙う異様な三絃の構えをあやつる彼の剣はまさに天下無敵。
− 数奇な運命をたどる多感な天才剣客の若き生涯と六つの決闘が、雷蔵の迫力にみちた殺陣を中心につづられていく。出演者は雷蔵のほか「破戒」で好評を博した新人の藤村志保、万里昌代、時代劇初出演の渚まゆみに成田純一郎、丹羽又三郎、友田輝、天知茂、柳永二郎など。( キネマ旬報より )
市川雷蔵が『椿三十郎』の向こうをはって、十五秒で十人を切り倒す“三絃の構え”を、目下撮影中の『斬る』でたっぷりみせている。
小諸藩主の側室を切った、侍女の藤村志保のこどもとして、暗い宿命を背負って生まれた“信吾”の雷蔵が、さまざまな陰謀と戦いながら、最後は切腹しなければならない、悲劇の主人公を演じているが、これがすばらしい剣の使い手。若くて美男ときているから、雷蔵にはうってつけの役柄。
この映画の撮影に入るまえ、メガホンを握る三隅研次監督と“殺陣”についてじゅうぶんの打ち合わせを行ない。新しい立ち回りをみせようと考案したのが“三絃の構え”だ。
右肩ななめ、左肩を敵の正面にだし、右手に握った剣を腕に近よせて、ややななめ上に横たえ、きっ先近くのミネに左手をあてる。敵の目は左方からわずかなきっ先をのぞかせておいて、刀身の大半をかくす。これが“三絃の構え”で、つまりそれはちょうど三味線をかかえたときの“形”と似ているところから、名づけた構えである。
見せ場は、ラストの水戸過激派との立ち回りで、この剣法をたっぷり見せるわけだが、その“殺陣”の迫力は、ケガ人が出るほどで、テストのときから、雷蔵の気合はするどい。なにしろ、剣を一閃すると二、三人がバタバタと倒れ、十五秒で十人が虚空をつかむ、というのだからすごい。
「三船さんの『用心棒』 『椿三十郎』はみましたが、あのときのタテはまったくすごいと思った。ボクもボクなりの新しいタテをと心がけて、こんどやったわけです」と雷蔵は言っていたが、精根こめた“殺陣”とあって、本番が終わったときには汗みどろだった。(デイリースポーツ大阪版 06/15/62)
観客を斬り伏せる新鮮さ 谷昌親
『斬る』の冒頭はまさに息もつかせぬ迫力で私たち観客に迫ってくる。藤村志保演じる女が部屋に入り、逃げ回る自分の女主人らしき人物を刺し殺したかと思うと、場面は変わり、彼女が丘の頂きにおいて処刑される様子が映され、さらに、赤子を乗せた駕籠が山越えをして、とある武家屋敷に入るまで、たたみかけるようなテンポで進んでゆくのだ。そうしたなかで、その赤子が藤村志保の子供であり、その子供の成長した姿が市川雷蔵の扮する若侍であるということがわかってくるが、そこには、物語の内容を説明するといった役割をはるかに越えた映画そのものの力強さが、ファースト・ショットにおいて手前の襖で画面を切った構図、その後のリズミカルなカット割り、さらに今回の上映のためにニュープリントで焼かれたフィルムから浮きたってくる鮮やかな色彩によってもたらされているのである。
『斬る』をはじめ、撮られてからすでに数十年がたつ三隅研次の作品をみるとき、その刃のきらめきのごとき新鮮さによって私たち観客は文字通り斬り伏せられてしまうのだが、そのことは、彼の映画が示すある偏向性とでもいったものと結びついているような気がする。これは当時の大映の映画にある程度までは共通する傾向であろうが、三隅作品の主人公たちはあらがいがたく破滅の道へと逸れてゆくといった印象がつよく、『斬る』においても、刺客として死んだ母をもち、養父と義理の妹を殺され、さらに旅の途中で出会った女の壮絶な死に遭遇した雷蔵は、みずからもひとりの殺人鬼となり、つねに死の影をまとうことになる。
しかも、そうしたまがまがしさに加え、画面そのものが中心から逸れてゆくかのような印象を与えるのだ。たとえば、かなりの頻度で使われるクローズ・アップにしても、顔が構図の中心におかれず、しかもしばしば俯瞰ぎみであったり仰角ぎみであったりするために、不安定さをはらみ、いわば異形の相貌を呈してくる。そうした偏向性によってこそ、三隅研次の映画は私たち観客へといまなお迫ってくるのではないだろうか。
又、文字通り人間が真っ二つになる場面をはじめとして『斬る』はそのダイナミックな殺陣で知られ、それがまたこの映画の魅力でもあるわけだが、そこで雷蔵はみずからが邪剣と呼ぶ剣法を用いる。刀の切っ先をまっすぐ相手の喉元へと向けたその異様な構えのごとく、三隅研次の映画そのものが、その鋭い刃の先を、私たちへと突きつけてくるのである。( キネマ旬報91年4月下旬号より )
スター列伝・名作一本勝負/市川雷蔵『斬る』
15年の映画歴で153本出演。多くの秀作を差し置いて、夭折した市川雷蔵の生涯を象徴する名作として私は『斬る』(昭和37年7月1日公開)をあげたい。「わが剣を破る者があれば、剣と共にわたくしも滅びたい」と願う悲しい剣士、高倉信吾の、その願いも叶わず、自決する宿命的に残酷な滅びの青春像を、鮮烈な映像美(かって佐藤慶は「微細なことのみにこる人」と三隅監督を批判的に評したが、微細なことにこだわる三隅研次の執念が生きている)で描きあげた71分の小品(撮影本多省三、美術内藤昭)。
昭和40年、私はこの映画の或る美しいショットについて、若さの勢いにまかせ、この息を呑む美しい瞬間は戦後思想史を逆転させるほどのものだ、と理屈を並べたてたことがある。そのとき作家三島由紀夫氏が、「そうなんだ」と力をこめて応じられた姿が忘れられない。それは氏の最後のあり方と深く関わるものだからである。
三隅研次の映像感覚(三隅、加藤泰、鈴木清順が60年代の色彩の3名人)が描きあげる滅びの美学、市川雷蔵でなくては演じきれない研ぎすまされた禁欲的美剣士像は、三島由紀夫原作『剣』、柴田錬三郎原作『剣鬼』につながっていく。
眠狂四郎も第一作は明朗すぎて失敗し、『斬る』の三隅監督による第二作『眠狂四郎勝負』の出現によって円月一刀流の虚無の構えは完成された。三隅研次は前年傑作『座頭市物語』の三人の重要な脇役、天知茂、柳永二郎、万里昌代に『斬る』でも重要な役を振りあてながら、全く異質の人物像を刻みこんだ。シベリア抑留三年、物事を逆に捉える傾向をもつ三隅研次は、「気に入ったカットが撮れた時はキャット!(カットの代りに)と叫ぶユーモアのある監督だった」(『斬る』で悪役を演じた名優稲葉義男の感想)。雷蔵は第18作『浅太郎鴉』以来16本の映画で三隅監督と組む(森一生が30本でトップ)。17本めの撮影中に下血で倒れた時、雷蔵は、自分の腸は「兎の腸みたいに」皮が薄いのや、と監督に洩らした(三隅「未完におわった“関の弥太っぺ”」)
狂四郎、信吾、雷蔵・・・・いずれも宿命の子
三十年前、巨匠黒沢明の痛快作『椿三十郎』では、椿の花が咲き乱れる椿屋敷で、しきりに鶯が鳴いていた。それに対し、あくまでも梅に鶯という様式美の型をふんだのが『斬る』であった。
敵陣の直中、静まり返った水戸城内、静寂を破る美しい一声。幕府大目付松平大炊頭(柳永二郎)が「鶯だ。よい日だの」と護衛の高倉信吾(市川雷蔵)に声をかける。信吾は壷庭を見やる。梅の古木。そこから鶯の音。作家柴田錬三郎は、「もし、この鴬の音を聞かなければ、大炊頭も、油断をしなかったであろう」と説く。うっかり、彼らは腰の刀を渡してしまう。信吾が気づいた時は遅かった。それでも咄嗟に床の間に活けてあった梅の一枝を掴み、敵の刀で先を斬らせ、とがった先端で敵の咽喉を刺し、その刀を奪いとるが、その時すでに大炊頭は殺されていた。信吾はわが腹を切って、その上に静かに倒れ伏した。
千葉周作の後継者が「その突きを躱す工夫はない」と言った信吾の異様な剣の構え(門付けの姿から着想)、「剣の理から申せば邪剣」と信吾みずから認め、みずから滅んでいった。
原作「梅一枝」は柴錬の連作『斬る』(36年8月19日光風社)の一編(脚色新藤兼人)。狂四郎(転び伴天連に犯されて誕生)に似て信吾もまた宿命の子、母(藤村志保)は御家のために主君の愛妾を殺したが、特別の計らいで妊娠し信吾出産後に信吾の父(天知)に幸せな表情で首を刎ねられる(斬る者と斬られる者の心の極致)。この出生の秘密を瀕死の義父から知らされる場面、「お前の母は一生涯の女の愛を一年でつかいはたしたのだ」との哀切な響きは忘れ難い。柴田錬三郎が好んで描く宿命の剣士(貴種流離譚の変形)はなぜか市川雷蔵以外には演じられない。俗論と誹られるのを覚悟で、彼の出生の秘密との関連を指摘したい。
死の三年前、十月末、市川雷蔵は生母(中尾富久さん)と生涯一度の対面をはたし、「天涯孤独」の覚悟を語った(対面の仲介者の遺族によると、母は今なお「健在」)。
映画『斬る』の唯一の明るい存在、信吾の“妹”を少女時代に懸命に演じた浜口まゆみさん(渚まゆみ)は死体として雷蔵に抱えられた時、「なんとかならんか、重うてどうもならん」と言われたのを懐しく思い出す。( 本木至、ダカーポ10/21/92号より )
『斬る』『剣』『剣鬼』(大映ビデオ)漂う雷蔵の“不思議な味”
市川雷蔵ブームである。ここ二、三年、東京をはじめ全国各地で彼の旧作が連続上映され、その勢いは衰えることを知らない。
今、なぜ市川雷蔵なのだろうか。日本映画がアイドルたちに席巻されて久しい。その間、大スターは次第に輝きを失っていった。こそへ、既に没後二十二年になる雷蔵が復活した。
雷蔵は三十七歳の生涯の中で、百五十三本の出演作を残した。その中から、「眠狂四郎」「忍びの者」「陸軍中野学校」などのシリーズ物、さらに『破戒』『炎上』といった名作など、四十五本がビデオになっている。
最近では『沓掛時次郎』や『若き日の信長』など、かなりマイナーな時代劇まで登場するという人気だ。では、雷蔵の魅力はどこにあるのだろう。
雷蔵は、1954年の二十三歳のとき、歌舞伎界から映画の世界に転身した。同年、三隅研次もまた監督としてデビューを果たした。後年、このコンビは、大映の屋台骨を支えたばかりでなく、数々の傑作を世に残した。そのひとつが“剣三部作”と呼ばれるものである。
『斬る』(昭和37年)、『剣』(昭和39年)、『剣鬼』(昭和40年、いずれも大映ビデオ)の三部作は、雷蔵の魅力を知るうえで、また、映画の醍醐味を味わう点からも最良の作品といえる。
特に『斬る』は、伝統に裏打ちされた見事な美術と斬新な構図に圧倒される。さらに全編七十一分という短時間の中で、幕府内の権力争いと、それに巻き込まれた個人の悲劇を余すところなく描く。雷蔵は、愛する者を次々と失う剣客の悲しみを見事に演じた。
“剣三部作”は、雷蔵主演の数ある作品の中で、最も彼の内部を浮き彫りにした作品といえる。それに触れると観客は彼のとりことなる。そこには、雷蔵だけが持つ不思議な要素があり、彼の復活の秘密が隠されている。(木)

■梗概
出生の秘密を背負いながら、何事も知らずに成人した高倉信吾の行手には、さまざまな運命の波乱が待ち構えていた−小諸藩士である養父の高倉信右衛門の許しを得て、三年間の武者修業の旅に出たが、彼の帰りを待ちわびていたのは、実の兄妹のように育てられた芳尾とよぶ可愛い義妹だった。
やがて三年の月日が流れた。元気いっぱいに高倉家に帰ってきた信吾は、ほどなく藩の武道奨励の大会に出場、藩主牧野遠江守の求めにより、水戸の剣客庄司嘉兵衛の神道無念流と立ち会った。剣のことなど全く縁のないような様子の信吾が静に立ち上がり、やがて“三絃の構え”という異様な構えで相手のノドを刺したときには、ことの意外さに場内は一瞬どよめきがおこった。信吾は邪剣ではあるが三年間の道中で密かに会得した剣法であることを遠江守に告げた。
数日して、下城中の信吾は、信右衛門と芳尾が隣家の池辺親子に斬殺されたという知らせをうけた。池辺義一郎は、伜義十郎の嫁に芳尾を望んだが、断わられこれを根にもってのことであった。信吾は池辺親子を国境に追いつめて討った。その時、信吾は自分の出生の秘密を知った。信吾の実母は山口藤子という飯田藩江戸屋敷の侍女で、城代家老安富主計の命をうけて殿の愛妾を刺したが、処刑送りの駕籠から彼女を救った長岡藩の多田草司と、一年を送ったのち生れたのが信吾だった。それから藤子は捕えられたが、彼女を斬る役が多田草司だった。
信吾は遠江守から暇をもらって旅に出た。その旅籠で、信吾は、二十人もの武士に追われている田所主水という侍から、姉の佐代を預かってくれと頼まれた。しかし、佐代は主水が危なくなった時、自分を犠牲にして主水を逃がした。彼女の崇高な姿にうたれた信吾は、彼女を手厚く葬った。
江戸に出た信吾は、千葉道場の栄次郎と剣を交えたが、その技の非凡さを知った栄次郎は、幕府大目付松平大炊頭に彼を推挙した。大炊頭に仕えて三年、信吾はその大炊頭の中に、養父信右衛門の慈愛に満ちた面影をみるようになっていた。
文久元年、世は尊王攘夷の嵐に狂っていた。中でも水戸はその急先鋒であった。大炊頭は水戸藩取締りのため信吾を伴って水戸へ赴いた。水戸へ着いた時、大炊頭を襲う刺客の中に庄司嘉兵衛があったが、その嘉兵衛も信吾に倒された。あすは江戸へという水戸最後の日、城内に入った大炊頭と信吾は、先祖の命日焼香のためというので両刀を取り上げられ、仏間に通された。仏間には刺客が待っていて大炊頭はあっという間に騙し討ちにあった。危機を直感した信吾は、床の間の梅一枝を持って刺客を倒し、仏間にかけつけたたが、大炊頭はすでに絶命していた。今はこれまでと信吾は、静かに切腹の用意をするのだった。( キネマ旬報より )
『斬る』 山田 和夫
高倉信吾が育ての親を斬って立ちのこうとする池辺親子を追いつめ、瞬時にして斬りすてる。二人の死骸の前に立ちすくむ信吾の顔に勝利の喜びはない。ただ苦汁にみちた表情。ズーム・レンズがスッと彼の姿をロングにおしやる。荒涼とした風景をバックにして立つ孤独なヒーローの姿。
それは吉川英治の“宮本武蔵”以来、日本映画の時代劇が何度もとらえてきた“孤独な剣豪”の姿である。それはまた、戦後“芸術的”な西部劇がしばしば登場させてきた“ロンリイ・マン”−孤独な英雄を思い出させる。
大映が「斬る」を企画し、三隅監督が狙った目標は、もちろん東宝の黒沢“三十郎”時代劇であろう。しかし“三十郎”時代劇は、まさにこの“ロンリイ・マン”を登場させながら−それがひよわな知識人に“芸術的”と錯覚させたが−むしろ、“ロンリイ・マン”以前のアメリカ西部劇的なおもしろさに徹していた。だから“三十郎”時代劇にもっともらしく“人間の研究”を見、何か政治的・哲学的な解釈を試みるのは見当ちがいである。
ところが「斬る」は“三十郎”的なおもしろさに徹することは出来ない反面、柴田錬三郎原作の鬼面人をおどろかすていの伝奇性や異様なエロ・グロ趣味、もっともらしいニヒリズム的ムードにこだわって、そのものズバリ“孤独な剣豪”の姿を押し出そうとしてしまった。だから草原での“三十郎”的なインスタント大量殺人、三船・仲代の決闘を思わせる河原での対決、そして「椿三十郎」のラストにおける血潮の噴水を思い出させるが、相手の体がまっぷたつに割れて倒れる趣向−どれも二番せんじ的な味気なさを感じさせるにとどまった。
“三十郎”的な行き方も大へん疑問だが、それ以上に中途半端で空虚な時代劇である。
興行価値 柴錬の原作・雷蔵の主演が結びついた新傾向大映時代劇だが少し奇をてらいすぎて、観客をとまどわせる。「黒の試走車」との二本立で封切りは好調だったがトリにするには不安がともなう一作。(キネマ旬報より)
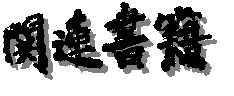
詳細は、シリーズ映画、その他のシリーズ「剣三部作」参照。

柴田錬三郎(1917-1978)による原作「梅一枝」は、1961年(昭36)に「オール読物」に発表され、日本文藝家協会の「代表作時代小説 昭和36年度」にも収録された後、連作『斬る』(光風社、昭和36年発行)の一編としても刊行された。
尚、講談社文庫 歴史ロマン傑作選第5巻「剣鬼らは何処へ」・新潮社 時代小説の楽しみ第7巻「剣に生き、剣に死す」(文庫でも刊行されている)・小学館文庫 時代小説アンソロジー第3巻「武士道」・ランダムハウス講談社 時代小説文庫「もののふ」にも収録され、読むことが出来る。

![]()



![]()