



![]()
1955年9月26日(水)公開/1時間47分大映京都/ カラースタンダード
| 制作 | 永田雅一/昭和30年度芸術祭参加作品 |
| 企画 | 川口松太郎・松山英夫 |
| 監督 | 溝口健二 |
| 原作 | 吉川英治(「週刊朝日」連載) |
| 脚本 | 依田義賢・成沢昌茂・辻久一 |
| 撮影 | 宮川一夫 |
| 美術 | 水谷浩 |
| 照明 | 岡本健一 |
| 録音 | 大谷巌 |
| 音楽 | 早坂文雄 |
| 助監督 | 弘津三男 |
| スチール | 小牧照 |
| 出演 | 久我美子(時子)、林成年(時忠)、木暮実千代(泰子)、大矢市次郎(忠盛)、千田是也(左大臣頼長)、柳永二郎(白河上皇)、中村玉緒(滋子)、進藤英太郎(伴卜)、菅井一郎(木工助家貞)、十朱久雄(関白忠通) |
| 惹句 | 『世界映画史上に燦然たる金字塔を打ち建てんとする、大映カラー、総天然色巨篇!』『反逆児青年、清盛の野心と、恋と、情熱は、今もなお、現代の若い人達の心の中に生きている!』『青年清盛の恋と闘争の絢爛豪華大絵巻!』 |
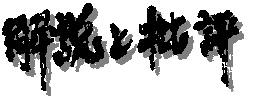
|
|


[ 解説 ]
吉川英治氏畢生の大作として、すでに五カ年半に及んで「週刊朝日」に連載されている原作の映画化です。各社争奪戦の裡に独占映画化権を獲得した大映では、国際的栄誉に輝く最高の技術を駆使して、世界最高の定評のある大映カラー総天然色映画として製作しました。
即ち社長永田雅一自ら、製作指揮をとり、溝口健二が監督の外、企画に川口松太郎、松山英夫が当り、脚本には依田義賢、成沢昌茂、辻久一のトリオが、十数次に亘る末、苦心の快定稿を完成、撮影は溝口監督のよき女房役宮川一夫が『雨月物語』『近松物語』に次いで初の総天然色映画に野心的な画調をみせ、色彩監修には『地獄門』でアカデミー衣裳賞獲得の和田三造画伯、美術監督は『源氏物語』『近松物語』の第一認者水谷浩、音楽監督は早坂文雄、衣裳考証上野芳生、録音大谷巌、照明岡本健一と、何れも数々の映画賞に輝くベテラン揃いの最高のスタッフを網羅しました。
配役には、青年清盛に、大映の誇る若手時代劇第一線スタア市川雷蔵を筆頭に、久我美子、林成年、木暮実千代、大矢市次郎、新藤英太郎、菅井一郎、千田是也、柳英二郎等、始めとする最高の適役キャストを編成しました。
内容は、青年清盛の野心と恋と、情熱を描くもので、清盛と云えば、悪逆非道の人間として印象づけられている彼を、この映画は根底から覆して、現代の私達に大きな共鳴と、共感を与える人間清盛として描き尽くし興趣溢れるものです。( 公開当時のパンフレットから )
吉川 英治
いかに良い映画は少ないものか。また映画製作とは難しい仕事であるかを、映画を見るたび私はいつも痛感する。だから自分の作品が映画化される場合になると、正直私は何か恐い気もちがする。原作者として名をつらねても、製作上においても私も唯の一観客であるにすぎない。
わけて、こんど大映の手にかかることになった『新・平家物語』は、自分にとっても終戦後の年月の大部分をそれ一作にそそいで来ただけに、云いしれない愛着がある。作家の机、掲載紙の紙面を離れ、それがスクリーンをとおして国際的観衆の前に大写しにされて出た時、果して一般の期待にそうかどうか、正直私は心配でならないのである。
けれども私は次のような信条をもっている。大映以外には、『新・平家物語』のような古典の特色と大きな規模を完全に映画化しうる社は、今のところ日本には他にないということである。
その独自のカラーの発色とか、構成や造型上の優れた経験力とか、溝口監督以下の熱意とか、それらの事は、あるいは日本の一般観衆の方が、私などよりはるかに熟知されているであろう。唯、それに、もう一つ私がつけ加えて至嘱している事は、永田社長、川口松太郎氏、松山英夫氏たちが朝日新聞社側との、幾回かの新平家映画化委員会の打合せの席でも「こんどの、一作は、大映の社運を賭している」とまで、その熱意をしめされている事だった。私として、原作者としては、その一言を伺っているだけで、もう何の杞憂があろうかである。もちろん、私も微力をつくしていかなるお力添えも否まないつもりでいる。
しかし、私はいかんせん素人である。大方の一般観衆と似たような立場で、今はただ大映のそうした抱負の開花を観うる日を、ただ愉しみに待っているに過ぎない。( 公開当時のパンフレットから )
『新・平家物語』の映画化について
吉川英治氏はこう考えている
問 :シナリオを読まれた感想からお聞きしたいのですが・・・
吉川:溝口監督の作品はいつもそうらしいが、まだ決定稿というところまでいっていないんです。これから川口松太郎君や監督とディスカッションして不満な点は改訂してもらうつもりです。ただ小説の構成では、人間主題にしていない。あくまで時代の大きな流れが主人公で、清盛はその時代に生きる、一個人に過ぎぬということです。
ところが、映画は膨大な原作をムリヤリ集約し、また一つのワクの中にすべてを表現しなければならぬ制約もあって、なかなか理想どおりにゆきません。川口君でさえも、自分の作品が映画化されたとき“これはとんでもないことになった”と苦情を持ち込むこともあるそうですからね。
まぁ今度の場合、原作をオヤと思うほど外したところがないし・・・、とにかく藤原文化の爛熟期に卵の殻を割るがごとく、宿命の子清盛が生まれ、時代の流れ、地響きがガッチリ背後に貫いていれば結構だと思います。
問 :雷蔵の清盛はどうでしょう。
吉川:大体、清盛は希望が持てないような社会状態にあって、しかも恵まれない環境に育った。しかしその不幸にもゆがめられず、芽を出そうとする強い意志と力をもっており、反面間が抜けた女好きの面もある青年なんです。それがたまたま雷蔵君と話し合っていて、実にフレッシュな印象を受けたんですね。彼が、無意識にニッと笑ってみせる表情がとてもいい・・・。これは案外、武者といった概念をこわした青年タイプが描き出せるんじゃあないかと思いました。あとの演技の難しさと、性格表現といったものは、溝口君に安心して任せられます。当人もリキミ過ぎるほど真剣ですし・・・。
問 :ほかの配役では。
吉川:そうですね。大矢市次郎君の忠盛は絵巻から抜け出たようで実に適役でしょう。また久我美子、木暮実千代、林成年の諸君もよく読んでくれて興味をもっているし、それぞれの芸風から期待できるんじゃないですか。
問 :時代考証、装置、色彩といった面で注文はありませんか。
吉川:時代考証と言えば、いまの映画会社がこれほど豊富に文献を集め、大掛かりな研究をするのかと驚きいった次第で、むしろこちらが資料を頂きたいくらいですよ。
また色彩は『楊貴妃』のとき東洋的な深みのある色をだしていましたが、こんどはもっとニュアンスに富んだカラーが向くんじゃあないかと考えています。
もともと日本人は、古くから洗練された色彩感覚をもっていて、昔の実生活を見ても女性は“袖がさね”などによって趣味を見せている。ただ時代のカラーはとくに女の服装は模様があり過ぎて、しかも背景から地面に至るまで独特の色があり、ゴチャゴチャになったり、相殺されたりする場合が起こる。やはり背景と登場人物の色の調和にもっと注意する必要があるようです。もっとも溝口君は『楊貴妃』の際、「東京の水では駄目だ。支那の水を持って来い」と千利休みたいことを言った人だから楽しみですよ。

☆昼も、夜も、忙しいのがスタジオ・マンの生活です☆
凝り方いろいろ
何ごとにも徹底しなければ承知しない溝口健二監督は、当時の女の人は、みんなズロースなんてはいていなかったんですからねと云ったものだ。ところがそう云った翌る日に恰度「遊女の宿」のセットがあって、京都撮影所の若手の女優達の中でも芸達者で知られた小柳圭子が、遊女に扮して、雷蔵にからみつき、腿もあらわに濃艶なる大熱演を展開した。
「ありゃァ小柳君、はいてないの違うか?」
「いや、まさかネ」
などと、その日のセットは、悪童連の噂とりどりだったものである。
X X X X X
同じセットで小川の岸の葦の生え方が溝口監督の気に入らなかった。お華の先生をつれて来て植えさせなさい、と言うことだが、急場のことで間にあわない。恰度、経理課の女の子が華道に堪能だと云うので、早速ひっぱって来て、葦を植えて貰った。こんなエピソードも溝口監督以外には見られないことである。
新平気物語
「遊女の宿」のセットは石コロだらけの河原の感じなので、女と遊んでいる叡山の荒法師の長刀を蹴飛ばして駈け去る雷蔵は、朝から午後一時迄、四十回近いテストの連続に、すっかり足の裏を痛め、フラフラになってしまった。途中で、足を辷らせて、小川の中へ転んでしまった程だ。
ところが、それを見ながら溝口監督は、いたわりの言葉一つかけるでもなし、平気なものだ。着物を乾かして雷蔵がまた出てくると早速また「テストいきましょう」だ。流石の雷蔵も『新・平家物語』じゃなくて、『新・平気物語』ですワ、とこぼす始末。
雷蔵俳優生命を賭ける
変っていると云えば、溝口監督は、あまりにも他の監督と変りすぎてる。雷蔵もビックリしてしまった。最初のカラー・テストの日でも、一言セリフを喋ったところ、それが気に入らなくて、「リアルじゃないあ、芝居のセリフじゃなくて、日常のセリフみたいに喋りなさい」今度は「ボリュウムがない」「簡単なセリフにも、それぞれのテーマがあるんだから、どこにテーマがあるかを、考えて喋るんだね」「言葉は感情の表現なんだから、感情が自然に言葉に現わされなきゃア」と云った調子で三時間。結局テープレコーダーで、ジックリ練習しておきなさい、と云う事になって放免となったが、その後、新聞記者のインタビューで雷蔵は、
「僕の今迄の映画に対する考え方は甘かったと思いますよ、脚本読んで、すました顔でセリフのやりとりして、きまったチャンバラをするというただそれだけでしたからネ。ルーズというのか、追われていたせいもありましたが、あまりにサラリーマン的でした」、とハッキリ語っている。
しかし、こうハッキリ云うこともなかなかムツカシイものだ。雷蔵も偉いと思う。「此の映画に、ボクの俳優としての全生命を賭けています」と雷蔵は文字通り、全身全霊の打ちこみ方だ。
牛も溝口式
この映画に出てくる東市の場面は、現代にたとえるならば、大阪新世界のジャンジャン市場のような感じ。いろんな物売り店があり、辻バクチがあり、泥棒市もあるというゴチャゴチャッとした庶民の市場の感じである。ここで清盛の雷蔵と時忠の林成年が酒を呑む。そして朱鼻の伴トの進藤英太郎と知り合いになる。これに大きな黒牛が一頭出てくる。溝口監督があまりにテストで長びくものだから、牛も待ちくたびれたか、セットの中でジャージャーオシッコを始め、そんな水たまりが二ヶ所も出来てしまった。ますますジャンジャン市場の感じが出てくるというものだ。
オシッコと云えば、溝口監督も、セットにシビンを持込んでオシッコをするという説がある。セットへ入ってしまうと仕事オンリーで、便所へ行くのも億劫になってくるのである。事実『雨月物語』や『山椒太夫』をやってるころには、そんな事があったらしい。きっと厳寒の頃の撮影だから、溝口監督も離れた便所へわざわざ出かけるのが大変だったんだろう。今度の『新・平家物語』ではそんな話は聞かない。スタッフの誰かがこんな事を云ったものだ。「牛も表へ行くのがメンドウだから溝口監督の真似をしたんでしょう」(近代映画臨時増刊「新・平家物語」より)
スターにとっては、じつに色んな苦心が要りますが『新・平家物語』となるとこれは普通の映画以上に大変な苦心が出演者を悩ませます。そのひとつがメーキャップで、なにしろ今から八百年前の頃のお話というので、まず当時の頃の扮装には、資料と首っぴきで始まるという始末です。
大映京都撮影所のメーキャップ室を訪れると『地獄門』『雨月物語』『近松物語』の名作を生んだスタジオの意気も凄く、木暮実千代さん、久我美子さん、林成年さん、市川雷蔵さんといったメイン・スタッフが、今日は『新・平家物語』の風俗に真剣に取り組んでいる風景にぶつかりました。
とくに異様なのは、清盛に扮する市川雷蔵さんで、まずびっくりするような太く濃い眉毛を描いて、逢う人々をおどろかせていますが、これは清盛の逞ましさと直情的な性格を表徴するためと聞いてはなるほど、と頷ける有さまです。メーキャップもこうして役と時代に忠実に適応する訳で、鏡に向うと一世一代の真剣な顔つきになるのも、スター商売の定めでしょう!(近代映画臨時増刊「新・平家物語」より)
かくて清盛生まる
主役の青年清盛に市川雷蔵を決定する迄には、随分みんな苦心した。『新・平家物語』は全三部作の天然色大作にするというので昨年の夏に、扇谷週刊朝日編集長らを含む朝日新聞社側と、永田社長らの大映側とで、原作者の吉川英治氏もまじえ映画製作委員会というのを作ったのだが、早くから殆どの配役は決まっていたのに、肝腎の清盛だけが決定せず、本格的な撮影の準備が出来ないままに、三月も過ぎ、四月も過ぎた。清盛役の売込みもいろいろあったらしいがどうもイメージにあわず、困っていたところたまたま五月の初めに東京後楽園球場で、東西映画人の対抗野球試合があり京都から市川雷蔵も参加していたが、この時役員になって出席していた永田社長が、雷蔵の人気を見てオドロイた。
「よーし、雷蔵で行こう!」と忽ち一決してしまった。さて京都でテストが始まったが、その扮装も、今迄若様役ばかりやっていた雷蔵が、太いゲジゲジ眉をつけ、無精髭をはやし、眼を張り、黒ぬりでやってるんだから、誰も雷蔵だなんて思わない。テストが終って雷蔵が演技部へ帰ろうと、所内をテクテク歩いていると、見学に来ている女の子達が、「誰やろ?あの人?」「私、どっかで見たような」と云っているうちに、スーッと演技部へ入ってしまう。あとでそれとわかって、地団駄をふむこと。(近代映画臨時増刊「新・平家物語」より)
近代映画 臨時増刊 新・平家物語
新・平家物語 岡本博
青年時代の平清盛の行状を中心に、武士階級が公卿にとって代った時勢の動き−これがとにかく判りよく、高級講談の面白さで物語られること、それに何より色がついている楽しみ。
色はリアリズム・カラーで殺して使い、それが一段と技術的な進歩を示したのだそうだが、なるほど特に鮮明な強さでのこらぬのはリアリズム・カラーの成功なのだろう。しかし色の楽しさというのはどういうことなのか。ぼくはむしろ『赤い靴』や『赤い風車』を忘れがたいし『地獄門』の方にいっそう色の楽しさがあったように思う。それらの作品はたしかにいまよりも色彩技術は幼かったかもしれないが、どれにも共通していることはロマネスクな色調ということである。ムーラン・ルージュの煙草の煙にかすんが画面は、ほとんどロートレックを感じさせたし『地獄門』の夜景の水底のような趣きは、これが平安かとも思った。いまのリアリズム・カラーの良さより、そういう人工的な色を好むのは季節外れの無知といわれるかもしれないが、案外それには絵画のもつ象徴性に通ずる感覚があるのではなかろうか。下品なのはいけないが、いい感覚の色の誇張は楽しい。この点吉川英治の色彩論には不満がある。
溝口がこういう平易な物語を作ったということも記憶されていい。雷蔵には好感がもてる。ただし侍が「いや、どうも」などといってはまずい。
興行価値:吉川英治の原作は週刊朝日に連載され、広汎な読者層をもっているが、この大映が誇るイーストマン・カラー大作は十分この波に乗り切れなかった。主演の市川雷蔵のなじみの薄さもさることながら、既成読者に頼らずインテリ層に、地道に売り込むべきだ。(キネマ旬報より)
昭和30年/1955年「配集トップ5」(配給収入:単位=万円)
1.新諸国物語・紅孔雀 東映 (24,182)
2.修善寺物語 松竹 (18,368)
3.ジャンケン娘 東宝 (17,600)
4.新・平家物語 大映 (17,303)
5.亡命記 松竹 (17,228)
昭和30年/1955年キネマ旬報ベスト・テン第12位(ベスト・ワンは『浮雲』)

新・平家物語/映画物語
日吉山王の御輿
保延三年の初夏。平安京。西暦でいえば、1137年。今年は1955年だから、八百十八年の昔である。平安京は今の京都である。強い日ざしを受けてうだるような暑さの中に当時のメーンストリート朱雀大路を、数百の武士の列が、行進してゆく、先頭の槍に領布をつけた首がくくりつけてあるのは、戦勝の帰途であることを示している。
「伊勢の平氏が」 「西国の海賊征伐から帰って来たぞ」
口口に言いながら、庶民は、道の左右に集まって来る。甲冑に身をかため、ゆったりと馬をうなせて来るのは、平家の中心人物、平忠盛である。長男清盛以下、家の子郎党が、それにつゞくが、どの顔も日に焼け、頬はこけ、ひげはのび、薙刀、長巻、弓矢の武具も、戦塵にまみれ放題、長途の旅と激戦の労苦をまざまざと物語っている。その時、彼らの行く手にあたって、人もなげな高笑いをあげ、破れ袈裟で顔をつゝみ法衣の下に腹巻をあて、大薙刀をかざして、高足駄を踏みならす法師の一隊が現われた。その群れの中には、金色にまばゆい、神輿が三基、白丁を着た神人にかつがれている。忠盛は、これをみると、直ちに馬を降り、部下を道の片側によせ、土下座して、恭々しく迎えた。
この法師たちは、比叡延暦寺の僧徒で、神輿は、比叡山の守り神日吉山王神社の神体である。当時、比叡山は、平安京をひらかれた桓武天皇以来、歴代の皇室の信仰をうけ、王城の鬼門の鎮護を以って自任している。日吉山王の神輿は、天皇といえども、地上に座して、これを迎えるという、最高の権威をほこった。従って、延暦寺は、朝廷に対して、要求することがあるたびに、この神輿を先頭に、御門に押しかけ、たとえ、その訴願に道理がなくとも、横車を押し通すのが、常であった。日吉山王の神輿に対しては、天皇の位といえども、はむかうことは出来なかった。
法師たちは、土下座する忠盛の一隊を小気味よげに見下しながらゆき過ぎようとしたが、その中に、西国から護送されて来た二三人の捕虜が、都のならわしに慣れぬため、土下座せず、うろうろとあたりを見廻しているのを見つけると、数名の法師が、いきなり、列中にかけ入り、その捕虜と、そばについている忠盛の家来をなぐり倒して、
「馬鹿者め、日吉の神輿のおわたりが、目に入らぬのか」
「みかどに於かせられても、ひざまづいて迎えられる神輿だぞ」
などと口汚くのゝしって、引きあげてゆく。満面に口惜しさをみなぎらせる平家面々の心中は、煮えくりかえるようだが、手を出すことは出来ない。
地の下の草
やがて、彼らは、院の御門である白河殿に赴いて、戦況を報告し、戦利品を献上した。忠盛は、軍状について鳥羽上皇に奏上することがあるから、拝謁を許されたいと頼み入った。忠盛はかねがね鳥羽上皇から一方ならぬ信任をうけている、執事別当は、武士の身分で、上皇に直き直きお言葉をかけていただこうなどとは、以ての外の僭越であると一蹴した。
忠盛の傍にいる二十才の清盛の若い血は、はげしくもえたぎった。今度の遠征は、上皇のご命令である。長い間、家の子郎党は、苦労をかさねて、ようやくはげしい戦斗に勝って来たのである、戦死者も数多く出ている。それに対して、御苦労であった、とねぎらいの一言くらい、かけて下さるのが、本当ではないか。思わず、執事別当に詰めよろうしたが、穏和な忠盛は、それを押さえた。
その夜、今出川の館にかえった忠盛は、清盛をすぐに、よびよせて、乗馬のうちの一頭を売り、酒にかえて来いと言った。戦功に対して、恩賞を下しおかれないので、貧乏な忠盛は武士にとって、命の次ぎに大切な乗馬を売って、家の子郎党をねぎらおうとするのである。清盛は、父の心中を思いやり、悲憤の涙をこらえながら、酒を買って来た。
宴はひらかれたが、郎党たちは、忠盛の心中を思いやって、一言も発しない、一せいに口にするのは、鳥羽上皇に対する不平不満である。上皇の周囲にいる公卿に対するはげしい憎悪である。清盛は、それをきくと、盃を持って彼らの間に割って入った。「泣き言をいうな。・・・お前達の不平不満はしょせん、俺達に、まだ力がないからだ。俺達は、たとえてみれば、地の草だ。まだ、芽は見えないが、春が来れば、芽をふくのだ。・・・今は冬だ。春を待つのだ。さ、うたえ うたえ」、そういう清盛の頬にも、痛憤の涙が流れている。
院政の開始
さて、ここで、当時の政治と社会の情勢を説明しておかないと、以後のストーリーが判りにくくなる。多少退屈かもしれないが、きいて頂たい。
平安京に都が定められてから、もう三百五十年もたつと、その間、宮廷に威勢を張り、政治上の要職を独占していた藤原一門のいわゆる「貴族政権」はようやく行き詰まり始めた。太平に馴れて、安逸をむさぼり、高い文化をほこりながら、日夜あそびくらすという生活からは、もう、国をおさめる大きくて強いエネルギーは、生まれて来ない。都をはなれた地方では、中央政治の弱体に乗じて、実力を持つ豪族が、しきりに土地をうばい、税金を横領し、公然と反抗して来る。延暦寺、園城寺(三井寺)といった大僧団も大地主であるから、それに対抗するために、僧兵という武力を養成する。物情騒然として来るのは当然である。
藤原一門も安閑としてはいられない。自分たちの政治上の地位と私有財産を守るために、武士を登用することになった。ここで、始めて、歴史上、武士が大きな存在として、クローズアップされて来る。それに加えて、問題が生れたのは、白河法王による「院政」の開始である。天皇が退位すると上皇とよび、仏門に入ると、法皇とよぶ。上皇、法皇の御座門を院とよぶのである。
当時、藤原一門が、延暦寺などの大寺院の持つ私有の土地があまりに大きくなり、そういう私有地からは、国税がとれないので国の財政は、非情に窮迫していた。そこで、不当な土地の私有を禁じ、国の財政を建て直そうとしたが、藤原一門の力では、従来のゆきがかり上、それが出来ない。そこで、上皇乃至法皇が、院に於いて、朝廷を指図して、政治をとることとなったのが「院政」である。そういう場合、天皇が、幼少であったなら、問題は起らずにすむが、今、鳥羽上皇の御子崇徳天皇は、二十才近い青年で、上皇との間にはげしい感情的対立が生まれ、そこにも、動乱の兆しは、現われている。
それは、さておき、院が、強力な政治を実行するに当っても、必要なものは、やはり、武力であった。一般情勢が、相当険悪になっているので、公文書では解決がつかない。どうしても武力を持つ武士の力を利用しなくてはならないことになった。ところが、血統と身分を重視する当時の慣習では、人の身分を殿上と地下に区別し、五位以上のものは、殿上それ以下のものは、地下とした。
武士は、もとより地下である。いかに実力があり、功労があっても、地下の者として、院や貴族の番犬にすぎなかった。清盛が、戦勝の宴の夜、はげしく叫んだ言葉は、実力者が、認められないことに対する不平と、何くそ今に見ておれ、というはげしい反抗であった。
見染めし処女(おとめ)
清盛の母は、泰子という。泰子は、藤原一門と血のつながっている中御門家から、忠盛にとついで来た。若く美しい泰子が、どうして、貧乏武士の忠盛にとついだのか、不思議に思う人が多い。
泰子は、その生れつきのせいか、はでで、見栄坊で、粗野な武家ぐらしをきらいながら、それでも、二十年間すごして来た。子供も、清盛をはじめ、経盛、教盛、家盛と、四人もある。しかし、交際するのは、いつも藤原一門で、蹴鞠、歌合わせ、香合わせなどと、家をあけることが多く、世間並の妻や母とは、大分ちがう。忠盛は、時にいさかいもするが大した不平も言わず、なすがままにさせている。清盛は、それが、歯がゆくてならなかった。
一日、清盛は、父の言いつけで、西七条の兵部権太輔藤原時信の邸へつかいに行った。時信は、正義派の老人で、今度の忠盛の遠征と勝利に、何の恩賞もなかったことに対して抗議したものだから、それをきらわれて、謹慎を命じられ図書寮の役人に左遷されたのである。忠盛は、それを申しわけなく思い、詫びの書状を持たせてやった。
時信の住居は、清貧という名にふさわしく、朽ち古びた建物であり、庭にひいた水で、若い娘が、糸を染めている。それがいかにも美しい。清盛は、その娘を、婢女(女中)と思って、横柄な口調で、自分のために、その糸で衣服を織ってくれ、と言った。その娘は、微笑しながら、主人の時信へ来意を取り次いだ。
ところが、もてなしを受けて、酒肴をはこんで来た美しい娘をみると、さつきの庭の婢女である。時信は、娘の時子ですと、紹介した。清盛は、さっきとは、打ってかわり、おどろき、小さくなっている。時子は、おかしそうに、その清盛をみたが、その目には、清盛の直情な正直さに対するなみなみならぬ好意が見えていた。糸を染めて、衣服を織るのは、貧乏公卿の家計をたすける一助であるときいて、清盛は、時子の女らしからぬ実行力にすっかり感心する。
母の秘密
その帰途、清盛は、時子の弟時忠と知り合い、共に東市の裏、わんわん市場に行った。二人は、盃をあげて、青年らしく時勢を慷慨する。ここは、雑草のように生活力のたくましい庶民の群が、むき出しのままの生活を、さまざまに展開している。清盛は、面白くないこと、いやなことがあると、ここへやって来る癖がある。するとそういう思いは、すべて消え失せるのである。
「ここには、強盗も人殺しもいるかも知れんが、たべていかれれば、みな笑ってくらしている。先祖や仏のおかげで、広大な領地をかかえて遊んでいる公卿や坊主たちのほうがずっと悪党だ」
時忠はその言葉にうなずいた。その時、清盛によびかけたのは、年上の友人で、やはり、鳥羽上皇に仕える遠藤光遠という武士だった。ところが、光遠の背後から鼻の赤い町人男が進み出て、もみ手せんばかりに、清盛に、一献さしあげたい、と言った。五条の伴卜という商人である。
伴卜は機を見るに敏な男で、忠盛が西海の海賊を心服させたと知ると、早速、忠盛を利用して、西国はおろか海外まで、商売の手をひろげ、大儲けしようと企らんでいる。伴卜の家の酒盛で、清盛は、光遠と伴卜から、思いがけないことをきいた。
それは、母の泰子が、かって、祇園の女御とよばれ、故白河法皇の寵姫であり、忠盛が、祇園の女御をもらいうけたについては、何か深いわけがあるらしく、清盛の真実の父は、白河法皇か、さもなくば、八坂の寺の僧かも知れぬということである。「そんな馬鹿な・・・」、清盛は、内心の衝撃に、一生懸命に耐えながら、夜の道をわが家へとって返した。
「俺の父は誰だ?」
という声が、ガンガンと頭の中に鳴りひびいている。家に帰りつくと、忠実な老臣木工助家貞をたたきおこすようにして、庭の闇にすわりこみ
「爺よ、俺は誰の子だ。ほんとうのことをおしえてくれ」
家貞が語ったのは、次のようなことである。二十年前、白拍子出身で、中御門の息女とふれて、祇園の社の近くに、瀟洒な住居をかまえる美女がいた。白拍子が法皇の寵姫と知って、誰いうとなく、祇園の女御とよんでいたが、法皇のおともは、いつも、忠盛と家貞だった。ある雨上りの夜、法皇の訪れと共に、住居の垣根をこえて逃げ出した怪しい僧侶があった。法皇は、荒々しくののしり、泣きながら引き止める女御をふり切って、帰って行った。その途中、忠盛は、法皇から女御を妻にするように、言われたのである。忠盛のもとへとついだ女御、すなわち泰子は、やがて、男の子を生んだ。それが清盛である。しかし、これだけのことでは、清盛が、白河法皇の子であるとも、悪僧の子であるとも、言い当てることはできない。
「爺、明らさまに言うてくれ。その上で、俺は、生涯の歩みをきめねばならぬ」
と、手をつく清盛を、家貞は、寝間につれてゆき、あたたかくふすまをかぶせながら、言った。
「和子、まことの父御が誰であろうと、和子は、まちがいなく一個の男の子では、おわさぬか。心を太々とお持ちなされ。天地を父母と思いなされ」
去り行く人
翌朝、泰子は、忠盛にこの家を出ると言い出した。昨夜の、清盛と家貞の話を、はからずも耳にして、耐え難い屈辱と憤りをおぼえたのである。清盛は心から詫びをいい、せめて、小さな子供たちのためにも思い止まってくれ、と泣くようにしてすがったが、きき入れてはくれない。気位の高い泰子にとって、清盛が、よくない噂を信じたことは、許しがたい恥辱であった。清盛は、母ならば、自分の父が誰であるか知っている筈だ、子の悩みを解いてくれるのが当り前だ、と詰めよったが、泰子は、怒って、つと立った。忠盛は、あきらめたように、無言である。泰子が、小さな弟達が、行かないで下さい、とすがるのもふり切り、牛車で、去ってしまったあと、清盛は、父をにらむようにして、言った。
「父上、父上は、この清盛を、法皇の御子として、大切にして下さったのか、それとも、悪僧の子と思うてあわれんで下さったのか」
忠盛は、無言のまま答えなかった。
僧徒の暴動
その直後、加賀の国白山寺が廃寺となった上に、失火のため焼けてしまったので、院では、その領地をとりあげ、国の所有にしようとしたところ、比叡山延暦寺は、白山寺は、その末寺であることから、領地は、当然延暦寺のもであるという訴えをおこし、白山寺の僧徒達も暴動をおこした。忠盛はそれを鎮圧すべき命令をうけて、出発したが、清盛は、同行することを拒んだ。
「もう、公卿や坊主どもの土地の番犬になるのはいやです。」
「院直き直きに、ありがたいお言葉をいただいたのだ。その思召しにそむくのか」
その時、清盛は、口惜しげに、叫んだ。
「上皇が、父上を御寵愛あそばれるわけが、やっと判りました。上皇も、祖父君の白河法皇が寵愛された藤原璋子を、お后にされ、そのお腹に、今のみかどが、お生れになったのです。上皇は、みかどを、自分の子ではないと仰せられています。上皇は、父上を、同病あわれんで、お慈悲をおかけになっているのです。そんなお情は、いただきたくありません。」
「清盛、口がすぎるぞ。思い上がったか」
こうした不和のまま忠盛は、清盛をのこして、加賀の国へ出発した。
伴卜に賭ける
それを知った五条の伴卜は、父上と喧嘩されてはいけません。もう、あなた方武士の力がなくては、どうにもならないところへ来ているのだから、自分達の力を信じなさい、と言った。事実、公卿たちの間でも、ようやく武士の力を無視することは出来なくなり、今度、忠盛が加賀の白山の騒動を無事におさめたならば、永年の功績によって、地下の武士から、殿上人に昇進し、公卿の仲間入りが出来る形勢だった。鳥羽上皇が、それをもう内々でおきめになったというのである。が、清盛は、父の出世が、何としても喜べない。又しても、上皇個人的なお慈悲である。父ひとりが、そんなお情にあずかっても、この世の中のくさった部分がどうなるものでもない。武士全体の地位があがるものではない。自分たちの実力で、それにふさわしい地位をかちとらねばならない。
それをきくと、伴卜は、はたと膝をうった。そして、清盛の考え方が気に入った。あなたの一生に賭けよう、あなたの一生を売って下さい。という、清盛は、よし、売ってやろう、その代り、高いぞ、とおどかして、絹の色糸二十貫を伴卜から貰うと、これを、時子の家へはこんだ。
「どうか、お役に立てて下さい」
時子は、おどろき、呆れた。清盛は、時子の、今織っている狩衣が、自分のものだと知ると、思わず、顔を赤らめた。時子の気持ちは、もう、清盛の若々しい心にかたむいていたのである。
加賀の国から凱旋した忠盛は、果して、上皇の思し召しにより、昇殿を許されることとなった。一家一門の名誉と、みんなはよろこんだが、清盛ひとり、苦々しい顔をしていた。忠盛が衣冠束帯に威儀を正して、昇殿したその朝、時信が、かけこんで来た。公卿の中には、依然、武士の昇殿をあくまで阻止しようという者があり、その夜忠盛を闇討ちにしようとする計画があるというのだ。それをきくや否や、清盛は、公卿たちに対するはげしい憎悪と父親に対する愛情とで、一時もその場所にいることが出来なかった。彼は、老臣の家貞と共に、禁制を無視して、御所の庭に忍びこみ、首謀者の公卿を威嚇して、忠盛を救った。
上皇は、清盛の武勇をめでられ、何の咎めもなく、忠盛と清盛は、何日かぶりで、晴れ晴れとした笑顔をみせて和解した。
「清盛は、わしのことなど、もう心にかけていまいと思うたが」
「父上のお命も、もとより惜しうございましたが、武士の力は、もう押さえきれぬことを、あいつらに、思い知らせてやりたかったのです」、、
だが、この闇討計画を洩らしたかどで、時信は、藤原氏から「放氏の罰」として、その姓を奪いとられ、追放された。このことは、かえって、清盛と時子を近しく結びつけ、二人は結婚した。時信の一家は、平の姓を名乗ることとなった。
底流に渦巻もの
忠盛は刑部卿という官職にのぼり、清盛も、左兵衛佐となり、ようやく幸福な日が訪れて来たかに見えた。しかし、時代の渦巻は、目に見えぬ底流の中に、はげしく動いている。
紫野今宮神社の例祭で「やすらい踊り」の列の中に加わっていた義弟の時忠と、家貞の子平六が、叡山の荒法師から喧嘩をうられ、彼らをさんざん打擲したという事件がおこった。直ちに法師たちは、二人の者を引きわたせと、せまったが、清盛は、非はそちらにあると、二人は引き渡せぬ、とつぱねた。
清盛には、叡山の真意がわかっていた。鳥羽上皇は、問題をおこした加賀白山の荘園を忠盛に下したまわったのである。それを恨みに思い、隙あらば、とり返さんとする叡山が、時忠、平六をわなにかけたのだ。叡山の提訴は、院の御所に於いても拒絶された。ついに、彼等は、最期の手段、神輿ぶりに訴えようとする。こうなっては、大事件である。朝廷の権威面目に関する。
関白忠通、左大臣頼長らは、清盛に、時忠、平六の二人を、おとなしく叡山の要求通りに引きわたし、事をおさめるように言いわたした。忠盛は、病中であったが、御所に伺候して、非は叡山にある旨をといた。が、面目にこだわる公卿たちは、命令をきかねば、官職を剥奪するといい、悪左府といわれる頼長は忠盛を、御殿の階から蹴落した。
憤激した清盛は、この事件の解決は、一身に引き受けよう言い放ち、父をつれて、邸へ戻ってゆく。その途中、忠盛は、病気の急変と憤激のため、一本の古扇をにぎりしめたまま生命を絶った。清盛は黙々として、忠盛の遺骸を祭り、叡山の神輿振りが、下山するのを、ひそかに期するもののある如く待っている。
その時、訪れたのは、母の泰子だった、忠盛の遺骸に焼香すると、清盛に向かい、あなたは、白河院の御子にちがいない、その証拠は、忠盛殿の持っておられた扇です。御所に行って、主上をはじめ皆さまにおねがいしましょうと、すすめる。それは、母として子の身の上に、事なかれしと念ずるあつい人情である。が、清盛は、それをしりぞけた。
「わたしは、平忠盛の子です。体内に白河さまのお血は一しずくもありません。・・・天地に生をうけた一個の男子として自分の運命をつかみとるのです」
と、毅然として言い放つ。時子や時信が、時忠にすすめて名乗って出させようとするのを止めた。
折から、千以上をかぞえる荒法師たちは、神輿を奉じて、祇園の林に到着し、今にも、院の御所に押しよせようとする。それをきいた清盛は、甲冑に身をかため、強弓を小わきに、一人、立ち上った。彼は、果して、何を以って至高の神輿にあたろうとするのか。彼の前途に待つは、風か、雨か、雲か。・・・ ( 公開当時のパンフレットより )


(パンフレットも三種ある)
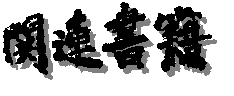
平家一門の頭領にして、強力な軍事力や経済力、そして姻戚関係を背景に、わが国初の武家政権を樹立した平清盛は、出生に不明な点も多く、一説では、白河法皇の御落胤ともいわれている。
清盛は保元・平治の乱によって源氏を一掃し、娘徳子を高倉天皇の中宮へ送り、天皇家との婚姻関係によって安徳天皇の外戚となり、一門の官職独占を図った。その“平家にあらざる者は人にあらず”とまでいわれた栄耀栄華の様と一門の没落は、琵琶法師らが伝えた「平家物語」にはじまって、吉川英治の大河小説「新・平家物語」(昭和25〜32)に、十五年戦争を潜り抜けて来たものの感慨とともに語られるに至った。
この吉川作品によって、これまで権力の座への執着ばかりが強調されて来た清盛の像が是正され、切れば血の出る青年時代等が生き生きと書かれるようになった。思えば長い雌伏の時期であったというべきか。
平清盛を映像化した作品では、何といっても、市川雷蔵主演の『新・平家物語』にとどめをさす。吉川英治の大河小説の連続映画化の第一弾で、公家達の蔑視を受けつつも、次第に勢力をつけはじめた武士階級の中で、若き日の清盛が権力の座へと登りつめていくさまを雷蔵が熱演、溝口演出によく応え、それまで平凡な二枚目スターだった彼が演技的に開眼した作品であるとされる。なお、この連続映画化は、『新・平家物語・義仲をめぐる三人の女』『同・静と義経』と続くが、中途で挫折した。また、NHK大河ドラマ「新・平家物語」では仲代達矢が若き日からその晩年まで演じた。( 別冊太陽、時代小説のヒーロー100 縄田一男から )
「新・平家物語」(しんへいけものがたり)は、吉川英治の歴史小説の大作。1950年から1957年まで「週刊朝日」に連載された。現行版は吉川英治歴史時代文庫全16巻。講談社 旧吉川英治全集(1968刊行)33〜38 全6巻
題材は「平家物語」だけでなく、「保元物語」「平治物語」「義経記」「玉葉」など複数の古典をベースにしながら、より一貫した長いスパンで源平両氏や奥州藤原氏、公家などの盛衰を描いた長編作品。
また西行や文覚など、権力闘争の外にあった同時代人や庶民たちの視点も加え、それまで怨霊の代表格であった崇徳上皇を時代に翻弄される心優しい人物として描くなど、新しい視点で平安時代から鎌倉時代への「それまでにない大戦乱となった」過度期の時代を描いている。読者も、戦後復興から変革へ向け動いていた昭和中期の時代様相に重ね、「国民文学作家」たる吉川の後期代表作となった。
1955年、1956年に大映で映画化されたほか、NHKで1972年に大河ドラマ、1993年〜1994年に人形劇として映像化された。現在は講談社吉川英治歴史時代文庫で読める。

![]()

